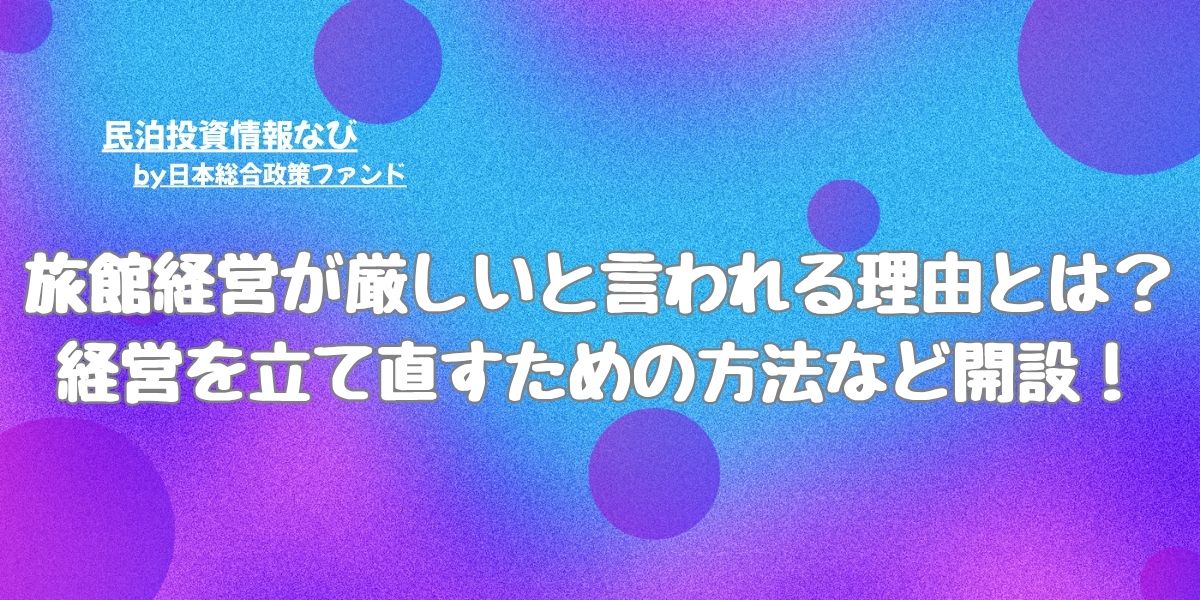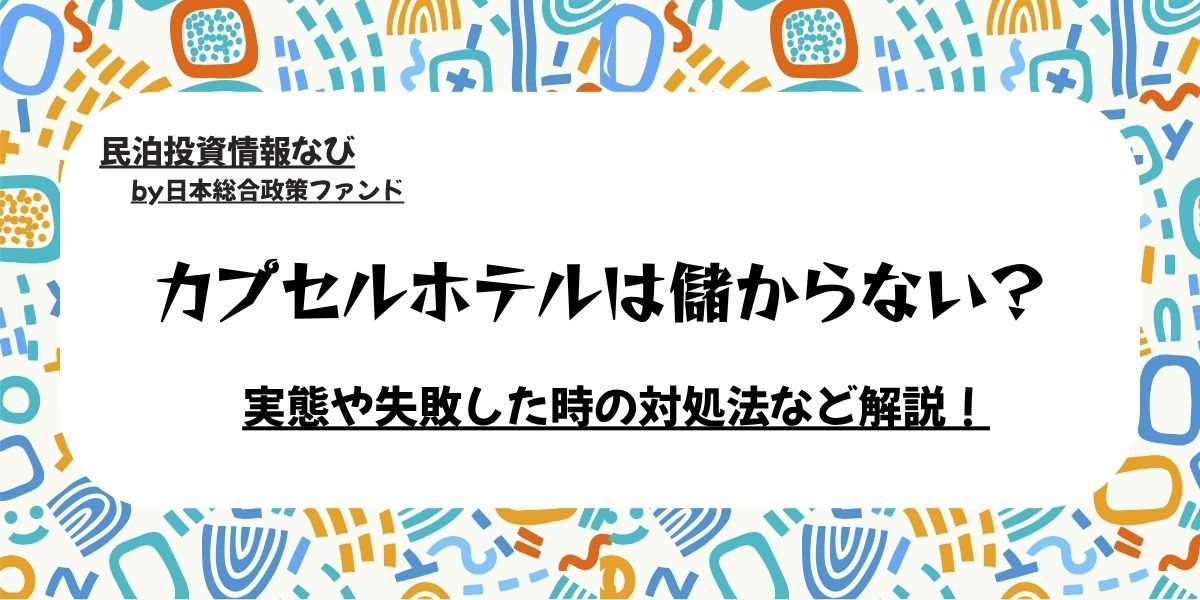旅館経営は人手不足による業務負担の増加、資金繰りの悪化、後継者問題などにより、多くの旅館経営者が従来の経営手法では立ち行かない状況に直面しています。
特に地方の中小規模旅館では、ホテルチェーンとの競争激化、顧客ニーズの多様化、デジタル化の遅れなど、複合的な課題が経営を圧迫し続けています。そのため、旅館経営は厳しいと思ったいる方もいるでしょう。
しかし、厳しい環境の中でも成功している旅館は確実に存在します。これらの旅館に共通しているのは、時代の変化を的確に捉え、自分たちの強みを活かした独自の価値提案を行っていることです。本記事では、旅館経営が厳しくなっている根本的な原因や業界の現状などを詳しく解説します。
旅館経営が厳しい主な理由は何か?

旅館経営を取り巻く環境は、複数の深刻な課題が相互に関連し合いながら厳しい状況を作り出しています。帝国データバンクの調査によると、旅館・ホテル業界では年間約100件前後の倒産が発生しており、特に中小規模の旅館では存続に関わる重大な経営課題に直面しています。
これらの問題を正しく理解するためには、それぞれの要因がどのような背景から生まれ、どのように経営に影響を与えているかを詳しく見ていく必要があります。どの理由が存在しているのでしょうか?
人手不足によって労働力が不足している
旅館業界における人手不足は、もはや一時的な課題ではなく、業界全体の構造的な問題となっています。厚生労働省の統計データによると、宿泊業の有効求人倍率は全産業平均を大幅に上回っており、特に客室係、調理スタッフ、清掃スタッフの確保が極めて困難な状況が続いています。
この人手不足の根本的な原因を理解するために、なぜ旅館業界で働く人が減少しているのかを考えてみましょう。第一に、労働条件の厳しさが挙げられます。旅館業務は朝早くから夜遅くまでの長時間労働が常態化しており、さらに土日祝日や年末年始といった一般的な休日にむしろ繁忙となる特性があります。現代の労働者が重視するワークライフバランスの実現が困難な職場環境となっているのです。
2つ目の理由に、給与水準の低さもあります。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、宿泊業の平均賃金は全産業平均を下回る水準にあり、特に地方の旅館では都市部の他業種との賃金格差が顕著に現れています。長時間労働でありながら賃金が低いという状況は、人材確保を困難にする大きな要因となっています。
この人手不足の影響は旅館運営のあらゆる側面に波及していきます。まず、既存スタッフ一人当たりの業務負担が大幅に増加します。その結果として、サービス品質の維持が困難になり、顧客満足度の低下を招く悪循環が生まれています。
また、新人教育に十分な時間を割けないという問題も深刻です。旅館のサービスには、単純な作業手順だけでなく、お客様への心遣いや細やかな配慮といった、経験を通じて身に付けるホスピタリティの文化があります。しかし人手不足により、こうした旅館固有の文化や技術の継承が困難になっており、長期的な競争力の低下につながっています。
後継者がいない
後継者問題は、特に家族経営の旅館において存続に関わる深刻な課題となっています。中小企業庁の調査によると、旅館経営者の約6割が60歳以上の高齢者であり、後継者が決まっていない施設が全体の約4割を占めているという驚くべき実態があります。
若い世代が旅館経営を継ぎたがらない理由を考えてみると、まず長時間労働や収益性の低さといった経営環境の厳しさがあります。さらに、地方立地による生活面の制約、例えば子どもの教育環境や配偶者の就業機会の限定といった問題もあります。加えて、デジタル化やグローバル化といった時代の変化に対応するためのスキルや知識の習得が困難であることも、若い世代にとって大きな負担となっています。
後継者不在の問題は、単に経営の継続性だけでなく、現在の経営判断にも深刻な影響を与えています。将来の見通しが立たない状況では、経営者は設備投資や新規事業展開に対して消極的になりがちです。その結果、施設の老朽化が進行し、サービス内容も時代遅れになって競争力の低下を加速させるという問題が生じています。
顧客ニーズが時代の変化に対応できていない
現代の旅行者の行動パターンや価値観は、従来の旅館が想定していた顧客像から大きく変化しています。この変化を理解するために、まず現在の旅行トレンドがどのように推移しているかを見てみましょう。
個人旅行の増加が最も顕著な変化です。観光庁の統計によると、団体旅行の割合は年々減少し、個人や小グループでの旅行が主流となっています。これらの個人旅行者は、自分たちの嗜好や予算に合わせたカスタマイズされたサービスを求める傾向が強くなっています。
従来の旅館では、夕食は18時から、朝食は7時からといった固定的なスケジュールでサービスを提供していました。しかし現在の旅行者は、より遅い時間の夕食を希望したり、朝はゆっくり過ごして軽めの食事を希望したりと、個人のライフスタイルに合わせた柔軟なサービスを求めています。
さらに、インバウンド観光客への対応も多くの旅館にとって新しい挑戦となっています。言語対応では、海外からの観光客はチェックインからチェックアウトまでの全過程で、自分の言語または英語でのコミュニケーションを期待していますが、多くの旅館では英語対応可能なスタッフの確保が困難な状況にあります。
決済方法の多様化も重要な課題です。海外からの観光客は、クレジットカードやモバイル決済といった現金以外の決済手段を利用することが多く、特に中国系の観光客はアリペイやウィーチャットペイといった独自の決済システムを使用しています。これらに対応していない旅館は、潜在的な顧客を逃している可能性があります。
資金繰りの逼迫・経費負担の増大
旅館経営における資金面の課題は、収益性の低下と固定費の増大という二重の圧迫によって深刻化しています。この構造的な問題を理解するために、まず収益面の課題から詳しく見ていきましょう。
旅館の収益は主に宿泊料金と食事料金から構成されていますが、これらの単価向上が非常に困難な状況にあります。競争の激化により、同じ地域内での旅館同士の競争だけでなく、ホテルやビジネスホテルとの競争も激しくなっており、価格競争に巻き込まれるケースが多くなっています。
加えて、予約サイトの手数料負担も収益圧迫の大きな要因です。現在多くの旅館が楽天トラベルやじゃらんといったオンライン予約サイトに依存していますが、これらのサイトでは売上の10%から15%程度の手数料が発生します。そのため予約の大部分をこれらのサイトに依存している旅館では、手数料負担が経営を圧迫する重要な要因となっています。
費用面では、設備の老朽化による修繕費用が大きな負担となっています。多くの旅館は建築から数十年が経過しており、屋根の修繕、配管の交換、電気設備の更新など、安全性や機能性を維持するための基本的な修繕だけでも相当な費用が発生します。光熱費や人件費、食力費などもかかりますが、近年これらの価格が上昇していますが価格転嫁できていない旅館も存在しています。
ホテル・ビジネスホテルとの競争激化によって
旅館業界が直面している競争環境の変化について、その構造的な変化を詳しく分析してみましょう。従来、旅館とホテルは比較的明確な住み分けがありました。旅館は主に温泉地や観光地での和風のおもてなしを提供し、ホテルは都市部でのビジネス利用や洋風のサービスを提供するという棲み分けでした。しかし現在では、この境界線が曖昧になり、直接的な競争関係が生まれています。
このようになった原因として、ビジネスホテルチェーンが地方展開に展開したことです。例えばアパホテル、東横インなどがあります。これらの大手チェーンは、従来都市部中心だった展開を地方の観光地にも拡大しています。これらのチェーンホテルの強みは規模の経済による運営効率の高さがあります。全国展開により調達コストを削減し、人材育成や運営ノウハウの標準化により効率的な経営を実現しています。さらに、全国統一の予約システムやポイントプログラムにより、顧客の利便性を高めています。加えて、ブランド力により安定した集客を確保しています。
一方で、従来の旅館が持っていた優位性が相対的に低下している状況もあります。温泉という資源についても、現在では人工温泉や日帰り温泉施設の普及により、旅館固有の価値とは言えなくなっています。また、和食についても、専門レストランや料亭の普及により、旅館でなければ味わえない特別なものではなくなっています。
デジタルマーケティングやWeb集客が遅れている
現代の宿泊業界において、デジタル技術を活用した集客は不可欠な要素となっていますが、多くの旅館でこの分野への対応が大幅に遅れています。この問題を理解するために、まず現代の顧客がどのように宿泊施設を選択しているかを考えてみましょう。
観光庁の調査によると、現在の旅行者の約8割がインターネットを利用して宿泊施設を検索・予約しています。特に若い世代では、この割合はさらに高くなっており、紙媒体や電話での予約はほとんど利用されていません。しかし多くの旅館では、この顧客行動の変化に対応できていません。
例えば、自社ウェブサイトの問題が最も基本的な課題です。多くの旅館のウェブサイトは、情報が古い、スマートフォンに対応していない、予約システムが使いにくい、写真や動画の質が低いといった基本的な問題を抱えています。現代の顧客は、ウェブサイトの第一印象で宿泊施設の質を判断する傾向があるため、これらの問題は直接的に予約率の低下につながっています。
検索エンジン対策(SEO対策)についても大きな課題があります。グーグルなどの検索エンジンで上位表示されるためには、継続的なコンテンツ更新、適切なキーワード設定、技術的な最適化などが必要ですが、多くの旅館ではこれらの知識や経験が不足しています。その結果、潜在的な顧客がオンラインで宿泊施設を探している際に、自社の旅館が検索結果に表示されない、または下位に表示されるという問題が生じています。OTAでのリスティングの場合でもSEO対策されていない場合もあります。
さらに、MEO対策を行うことによって費用をかけずに直接自社ウェブサイトから集客することが可能です。自社サイトを使用することでOTAからの手数料負担を削減することができます。
関連:宿泊施設のMEO対策とは?MEOが必要な理由など解説!
サービス内容や運営体制が現代の旅行者に合っていない
旅館のサービス内容や運営体制が現代の旅行者のニーズとどのようにずれているかを詳しく見ていきましょう。この問題を理解するためには、現代の旅行者が求めているサービスの特徴と、従来の旅館が提供してきたサービスの違いを明確に把握する必要があります。
接客スタイルの違いが最も顕著な問題です。従来の旅館では、お客様に対して手厚い接客サービスを提供することが美徳とされてきました。仲居さんが部屋まで案内し、お茶を入れ、食事の準備から片付けまで全てを行うスタイルです。しかし現代の旅行者、特に若い世代や個人旅行者の中には、このような密接な接客を負担に感じる人も多くいます。
さらに、食事スタイルについても大きな変化があります。従来の旅館では、夕食と朝食がセットになった一泊二食付きのプランが基本でした。しかし現代の旅行者は、より柔軟な食事オプションを求めています。夕食は外で地元のレストランを楽しみたい、朝食は軽めで済ませたい、部屋食ではなく食堂やレストランで食事をしたいといった多様なニーズがあります。
旅館業界の現状と今後の見通し

旅館業界を正しく理解するためには、まず現在の状況を客観的なデータで把握し、その上で将来に向けた可能性と課題を整理していく必要があります。業界全体が直面している厳しい現実がある一方で、新しい技術の活用や市場の変化を捉えることで、新たな成長の機会も見えてきています。
この業界の複雑さを理解するために重要なのは、単に表面的な数字だけを見るのではなく、その背景にある社会の変化や技術の進歩、そして顧客ニーズの変遷といった要因がどのように絡み合っているかを読み解くことです。以下では、統計データから見える現状の把握から始まり、業界が取り組むべき課題解決の方向性、そして将来の成長可能性について段階的に解説していきます。
倒産件数の推移と宿泊業の動向データ
人手不足対策とDXの推進
旅館業界が直面している人手不足という根本的な課題を解決するためには、従来の労働集約的な運営方式から脱却し、デジタル技術を活用した効率的な経営への転換が不可欠です。この変化を理解するために、まずDX化を押し続けることが必要です。
DXの第一段階として考えるべきは、日常業務の自動化です。これは単に新しい機械を導入するということではなく、従来人間が行っていた作業をデジタル技術で効率化することを意味します。具体的な例を挙げると、チェックイン・チェックアウトの自動化システムの導入があります。タブレット端末やセルフチェックイン機を活用することで、フロント業務の負担を大幅に軽減できるだけでなく、24時間対応も可能になります。
次に、客室管理システムの導入も重要な変革をもたらしています。従来は手作業で行っていた客室の清掃状況確認、設備の点検、在庫管理などを、デジタル技術を活用して効率化することができます。清掃スタッフがスマートフォンやタブレットを使って作業状況をリアルタイムで報告し、管理者が全体の進捗を把握できるシステムを導入することで、人員配置の最適化と作業効率の向上を同時に実現できています。
さらに、予約管理システムの高度化も人手不足解決の重要な要素です。従来の電話やファックス中心の予約受付から、オンライン予約システムへの完全移行により、24時間365日の予約受付が可能になり、同時に予約管理業務の自動化も実現できます。さらに、AIを活用した需要予測システムを導入することで、適切な人員配置や料金設定の最適化も可能になります。
顧客サービスの分野でも、DXは大きな変革をもたらしています。チャットボットの導入により、基本的な問い合わせには自動で対応し、複雑な内容のみを人間のスタッフが対応するという役割分担が可能になります。これにより、限られた人員をより付加価値の高い業務に集中させることができます。
投資対効果の観点から見ると、DXの導入には初期投資が必要ですが、中長期的には人件費の削減、業務効率の向上、顧客満足度の向上による売上増加などにより、十分な投資回収が期待できます。特に人手不足が深刻な現在の状況では、DXの推進は経営の持続可能性を確保するための必須の取り組みと言えます。
インバウンド需要のさらなる拡大
旅館業界の将来を考える上で、インバウンド観光市場の拡大は最も重要な成長機会の一つです。この市場の可能性を正しく理解し、適切に対応することで、旅館経営の新たな活路を見出すことができます。まず、この市場がどのような特徴を持ち、どのような変化を遂げているかを詳しく見ていきましょう。
日本政府観光局(JNTO)の統計によると、コロナ禍以前の2019年には年間約3,200万人の外国人観光客が日本を訪れており、政府は2030年までに6,000万人という目標を設定しています。この数字の背景を理解するために重要なのは、単に観光客数の増加だけでなく、観光客の質的な変化も同時に起きているということです。
インバウンド観光客の行動パターンを分析すると、従来の団体旅行から個人旅行への移行が顕著に見られます。特に欧米系の観光客では、日本の伝統文化や自然環境を深く体験することを目的とした長期滞在型の旅行が増加しています。このような観光客にとって、本物の日本文化を体験できる旅館は非常に魅力的な宿泊選択肢となります。
地域別の観光客動向を見ると、従来は東京、大阪、京都といった大都市圏に集中していた外国人観光客が、地方の温泉地や自然豊かな地域にも足を伸ばすようになっています。これは、リピーターの増加により、よりディープな日本体験を求める観光客が増えているためです。地方の旅館にとっては、この流れを捉えることで新たな顧客層の獲得が可能になります。
言語対応について考えてみると、完璧な多言語対応は困難でも、基本的な英語対応と翻訳技術の活用により、十分な対応が可能です。最近では、リアルタイム翻訳技術の精度が大幅に向上しており、スマートフォンアプリやタブレット端末を活用することで、言語の壁を大きく下げることができます。
インバウンド需要の拡大は、単に外国人観光客を受け入れるということではなく、旅館のサービス品質全体の向上につながる機会でもあります。国際的な水準のサービスを提供することで、国内の顧客に対するサービス品質も向上し、結果として施設全体の競争力強化につながります。
旅館経営を立て直す方法はあるか?
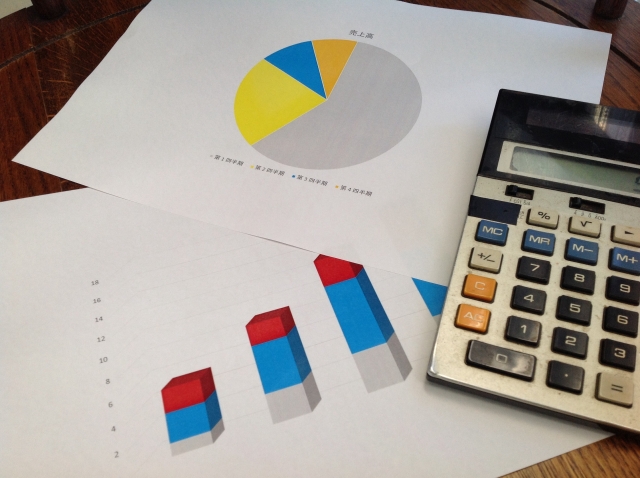
旅館経営の立て直しは、単一の施策だけでは実現できない複雑な課題です。これを理解するために、まず経営再建を成功させる基本原理について考えてみましょう。経営危機に陥った旅館が再び競争力を取り戻すためには、問題の根本原因を正確に特定し、それに対して体系的かつ継続的な改善活動を行う必要があります。
経営立て直しの過程を建物の改築に例えて考えてみると、分かりやすくなります。建物に問題がある場合、表面的な補修だけでは根本的な解決にはなりません。まず基礎や構造に問題がないかを徹底的に調査し、必要に応じて基礎工事から始める必要があります。
どのようなことを行えばいいのか見ていきましょう。
経営の根幹を見直す
旅館経営の立て直しにおいて最初に取り組むべきは、経営の根幹部分の徹底的な見直しです。これは医師が患者を診察する際に、まず全身の健康状態を把握してから具体的な治療方針を決めるのと同じプロセスです。表面的な症状だけを見て対処療法を行っても、根本的な問題が解決されなければ、やがて同じ問題が再発してしまいます。
経営の根幹を見直すための最初のステップは、現状の正確な把握です。これは思っている以上に難しい作業で、多くの経営者は自分の旅館の実態を正確に把握できていません。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。日常の業務に追われる中で、客観的な視点で自分たちの経営状況を分析する時間が取れない、または感情的な判断により現実を受け入れることが困難になっているケースが多いのです。
まず財務状況の詳細な分析から始めましょう。過去3年間の売上推移、月別の客室稼働率、平均客単価、主要な費用項目の変動、キャッシュフローの状況などを数値で正確に把握する必要があります。この際重要なのは、単に数字を並べるだけでなく、なぜその数字になったのかという背景要因を深く分析することです。
次に、市場環境の変化と自社のポジションを客観的に評価します。地域の観光動向、競合施設の状況、顧客ニーズの変化などを調査し、自分たちの旅館がその中でどのような立場にあるのかを正確に把握します。この分析を行う際は、希望的観測を排除し、事実に基づいた冷静な判断を行うことが重要です。
事業モデルの見直しも根幹的な課題です。従来の一泊二食付きの旅館モデルが現在の市場で本当に最適なのかを検討し、必要に応じて新しい事業モデルを検討しましょう。例えば、素泊まりプランの充実、日帰り利用の拡大、体験プログラムの提供、地域との連携事業など、多様な収益源を組み合わせた事業モデルの構築を検討します。
組織体制の見直しも重要です。現在の人員配置や役割分担が効率的に機能しているか、意思決定プロセスは迅速で適切か、情報共有は円滑に行われているかなどを検証します。特に家族経営の旅館では、感情的な関係と経営上の関係が混在することで、適切な経営判断が困難になるケースがあります。
集客力を強化する
集客力の強化は、旅館経営立て直しの中核となる重要な取り組みです。これを理解するために、集客を川の流れに例えて考えてみましょう。売上は川の下流で得られる水量に相当し、集客活動は上流から水を引き込む取り組みに相当します。下流で水量が不足している場合、その場で水をかき集めるのではなく、上流からより多くの水を引き込む仕組みを構築する必要があります。
デジタルマーケティングの基盤整備から始めましょう。自社ウェブサイトの全面的な見直しが最優先事項です。現代のウェブサイトは単なる情報提供ツールではなく、顧客との最初の接点であり、予約につながる重要な営業ツールとして機能する必要があります。スマートフォン対応、表示速度の向上、分かりやすいナビゲーション、魅力的な写真や動画の活用、明確な予約導線の設計などが重要な要素となります。
さらに、オンライン予約プラットフォーム(OTA)の活用も重要な戦略です。楽天トラベル、じゃらん、一休.comなどの主要プラットフォームでの露出を最大化するため、魅力的な写真の掲載、詳細な施設情報の提供、適切な価格設定、プロモーションプランの活用などを行いましょう。ただし、手数料負担を考慮し、自社サイトでの直接予約も並行して強化することが重要です。
リピーター対策も集客力強化の重要な要素です。新規顧客の獲得コストは既存顧客の維持コストの数倍かかると言われているため、一度利用していただいた顧客との関係性を継続し、再訪を促進することが効率的な集客につながります。
関連:宿泊施設のMEO対策とは?MEOが必要な理由など解説!
関連:民泊運営で集客する方法とは?集客におすすめなプラットフォームなど紹介
商品力とサービスを磨く
商品力とサービスの向上は、持続可能な経営改善を実現するための基盤となる取り組みです。これを楽器の演奏に例えて考えてみると理解しやすくなります。どんなに集客が上手くても、実際の演奏(サービス)が期待を下回れば、聴衆(顧客)は二度と来てくれません。逆に、素晴らしい演奏ができれば、口コミで評判が広がり、自然に集客力も向上します。
さらに、商品力の向上において最初に取り組むべきは、自分たちの強みの再発見と強化です。多くの旅館は、競合他社と同じようなサービスを提供しようとして、かえって特色を失ってしまうケースがあります。そのため自分たちだけが提供できる独自の価値を明確にし、それを徹底的に磨き上げることが必要です。
加えて、サービス品質の標準化も重要な取り組みです。スタッフによってサービスの質にばらつきがあると、顧客満足度の向上は困難になります。基本的な接客マナーから専門的なサービス技術まで、全スタッフが一定水準以上のサービスを提供できるよう、体系的な教育訓練プログラムを構築します。
顧客ニーズの多様化に対応するため、サービスの選択肢を増やすことも重要です。従来の画一的なサービスから脱却し、顧客の嗜好や状況に応じてカスタマイズできるサービス体系を構築します。例えば、食事の時間や場所の選択肢を増やす、部屋のタイプや設備を多様化する、体験プログラムを充実させるなどの取り組みが考えられます。
生産性を向上させる
清掃業務を例に考えてみましょう。従来は感覚と経験に頼っていた清掃作業を、チェックリストの活用、作業時間の測定、効率的な清掃用具の導入などにより体系化することで、品質の向上と時間短縮を同時に実現できます。また、清掃状況をデジタル機器で管理することで、進捗状況の可視化と適切な人員配置が可能になります。
さらに、人員配置の最適化も生産性向上の重要な要素です。繁忙期と閑散期、平日と休日、時間帯別の業務量を正確に把握し、それに応じた効率的な人員配置を行います。また、多能工化を進めることで、状況に応じて柔軟な業務分担が可能になり、全体の生産性向上につながります。
組織と人材を改革する
組織と人材の改革は、旅館経営立て直しの最も重要でありながら、最も困難な取り組みでもあります。
組織改革の一つの例として、現在の組織構造と役割分担の見直しがあります。多くの旅館、特に家族経営の施設では、明確な役割分担や責任の所在が曖昧になっているケースがあります。そのため誰が何に責任を持ち、どのような権限を有しているかを明確にすることで、効率的な意思決定と業務執行が可能になります。
コミュニケーション体制の改善も重要な要素です。情報の共有がスムーズに行われない組織では、問題の早期発見や迅速な対応が困難になります。定期的なミーティングの開催、情報共有ツールの活用、報告体制の明確化などにより、組織内のコミュニケーションを活性化することができます。
さらに、評価制度と処遇制度の見直しも重要です。頑張った従業員が適切に評価され、それが処遇に反映される仕組みを構築することで、組織全体のモチベーション向上を図りましょう。ただし、小規模な旅館では大企業のような複雑な制度は適さないため、その組織に適した簡素で公平な制度を設計することが重要です。
これらにより労働環境の改善が行われれば、従業員の定着率向上と新規採用の促進を図ることが可能になります。そのため働きやすいスケジュール、適切な休憩時間、安全で清潔な労働環境、福利厚生の充実などにより、従業員が長く働きたいと思える職場を作りましょう。
まとめ
旅館経営の厳しさは、人手不足や後継者問題、顧客ニーズの多様化、資金繰りの困難さ、競合との激化、デジタル対応の遅れといった複数の要因が複雑に絡み合って生まれています。しかし、これらの課題は決して解決不可能なものではありません。
業界全体を見渡すと、倒産件数が高い水準で推移する一方で、DXの推進やインバウンド需要の拡大といった新たな機会も生まれています。成功している旅館は、明確なコンセプトによる差別化、口コミを重視した顧客満足度の追求、高いコストパフォーマンスの実現により、持続的な成長を実現しています。
経営立て直しのためには、経営の根幹から見直し、集客力の強化、商品力とサービスの向上、生産性の改善、そして組織と人材の改革という5つの観点から総合的にアプローチすることが重要です。しかし、これらのことを行なったとしても100%経営を再建できるとは限りません。また、経営を立て直すためには並々ならぬ努力が必要です。そのため、それらの労力を使いたくない方は、M&A仲介を使用して売却することも1つの手段となります。旅館は、民泊としても使用することも可能であるため、場所によっては高値で売却することもできます。
売却をするためにおすすめのM&A仲介サービスは、日本総合政策ファンドです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。