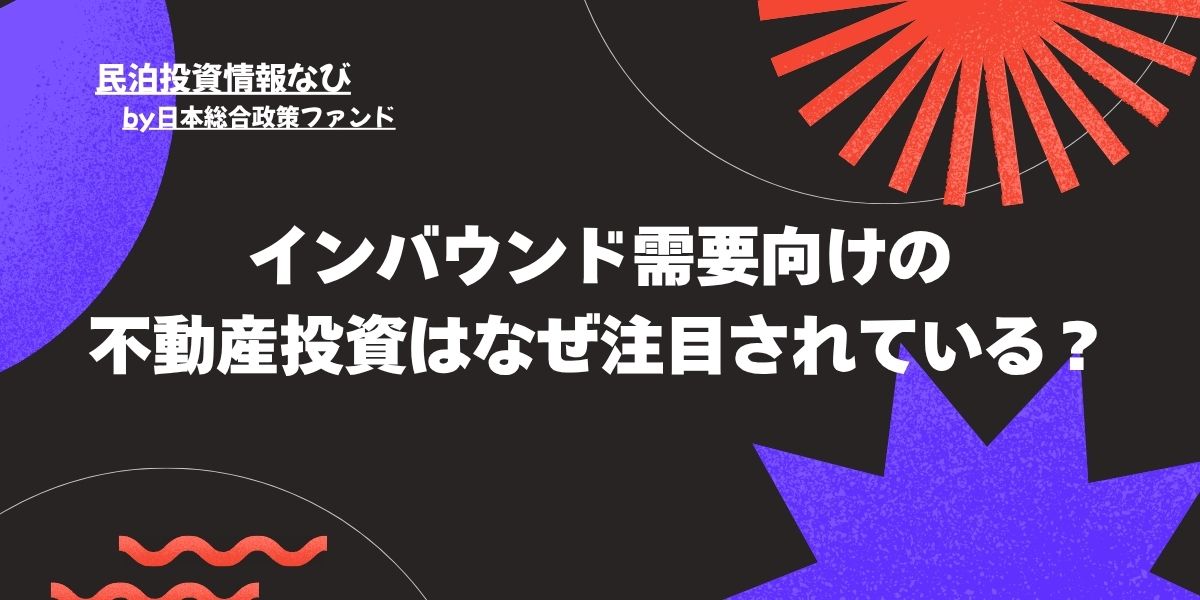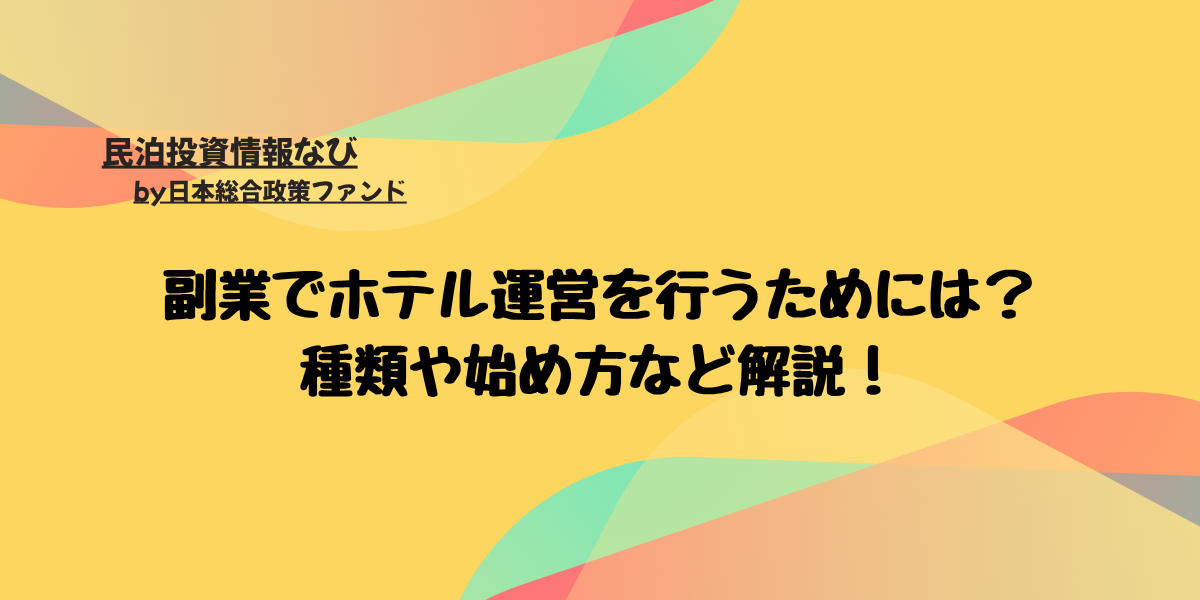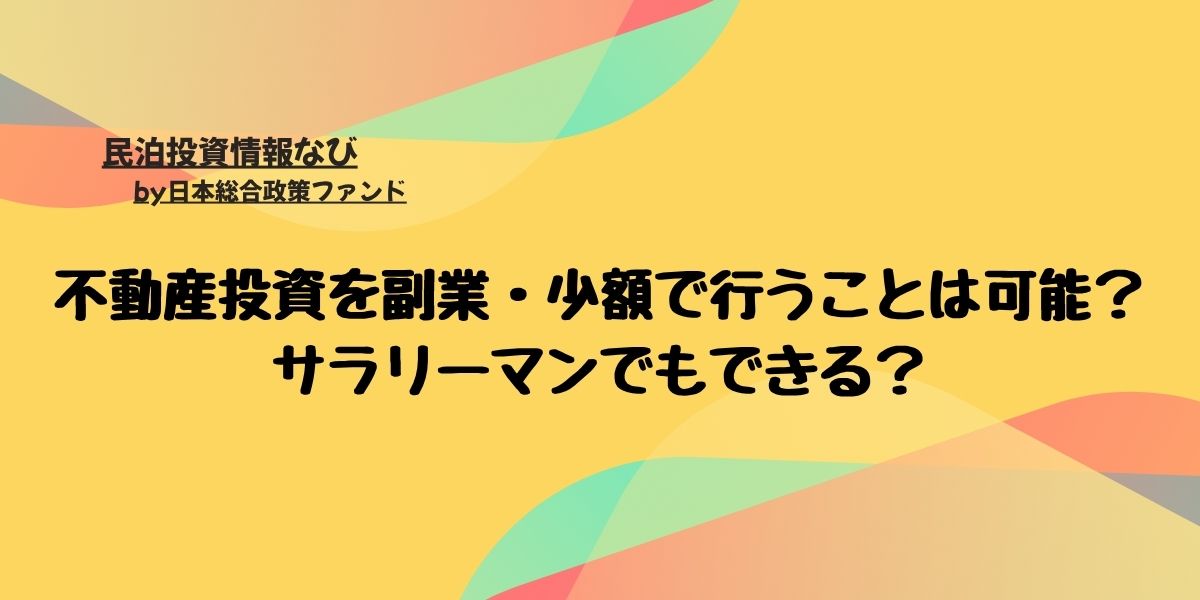訪日観光客の急増に伴い、インバウンド需要を狙った不動産投資が注目を集めています。従来の住居系賃貸では利回り3%〜5%が一般的ですが、ホテルや民泊投資では6%〜12%の高利回りも現実的です。しかし、「どんな物件を選べばいいのか」「法規制は大丈夫なのか」「リスクはどの程度あるのか」といった疑問を抱える方も多いでしょう。
実際、インバウンド投資は通常の不動産投資とは異なる特性を持ちます。円安効果や地価上昇といった追い風がある一方で、観光需要の変動や規制変更といった不確定要素も存在します。立地選定を誤れば稼働率が低迷し、法規制の確認を怠れば営業そのものができなくなるリスクもあります。
この記事では、インバウンド不動産投資がなぜ今注目されているのか、どのような物件が収益性に優れているのか、そして実際の利回りやリスク、具体的な始め方までを体系的に解説します。
インバウンド需要向けの不動産投資はなぜ注目されている?
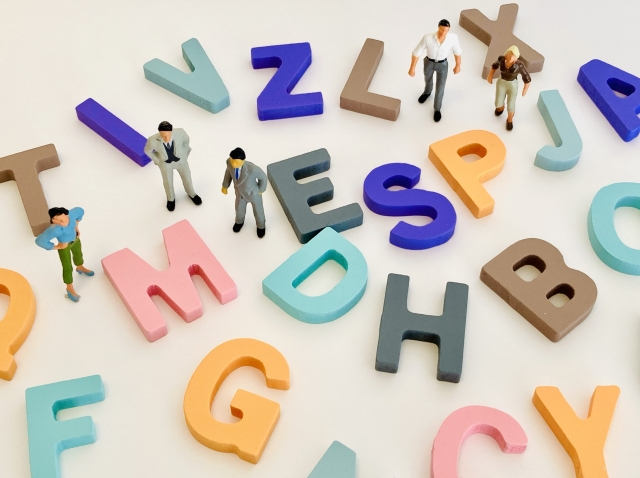
訪日観光客の急増を背景に、インバウンド需要を狙った不動産投資への関心が高まっています。円安が追い風となり、観光地の地価が上昇する中で、従来の住居系投資では考えられなかった高利回りが実現できるケースも増えてきました。
東京や大阪では宿泊施設が慢性的に不足しており、この需給ギャップが投資機会を生み出しています。加えて、日本の治安や政治の安定性は海外投資家にとって大きな魅力です。
インバウンド投資が今、これほど注目される理由を具体的に見ていきましょう。
訪日観光客が急増している
ホテル需要が高まっている
この供給不足は、ホテルの客室単価を押し上げています。東京都心部のビジネスホテルでさえ、1泊あたり15,000円〜20,000円が相場となり、コロナ前と比べて約30%上昇しました。京都や金沢といった観光都市では、繁忙期には1泊30,000円を超える価格設定も珍しくありません。
このような価格上昇は、ホテル運営事業者の収益性を高め、結果として不動産投資家にとっても魅力的なリターンを生み出しています。
加えて、ホテル需要は観光客だけでなく、ビジネス利用者や国内旅行者にも支えられています。つまり、インバウンド需要が一時的に減少しても、一定の稼働率を維持できる基盤があるのです。リスク分散の観点からも、ホテル投資は従来の住居系不動産よりも安定性が高いといえます。
高い利回りが期待できる
インバウンド需要を取り込んだ不動産投資は、従来の住居系投資と比べて高い利回りが期待できます。
例えば、東京都心の住居系マンションの平均利回りは3%〜4%程度ですが、簡易宿所(民泊)やホテル投資では、立地と運営次第で6%〜10%の利回りも現実的です。大阪や京都の観光エリアでは、さらに高い利回りを実現しているケースもあります。
高利回りの理由は、宿泊単価の高さと稼働率の安定性にあります。住居用賃貸では月額家賃が固定されますが、宿泊施設では日単位で料金を設定でき、繁忙期には通常の2〜3倍の単価を取ることが可能です。また、インバウンド観光客は季節を問わず訪れるため、オフシーズンでも一定の稼働率を維持できます。
地政学リスクが低い
物件価格の上昇が見込める
インバウンド需要の拡大は、不動産価格そのものの上昇を後押ししています。宿泊施設への投資需要が高まることで、該当エリアの物件価格は上昇傾向にあります。
ただし、物件価格の上昇には注意も必要です。過熱した市場では、実態以上に価格が吊り上がり、バブル崩壊のリスクもあります。インバウンド需要が持続可能かどうか、地域の観光資源が本質的に魅力的かを冷静に分析することが重要です。
それでも、適切なタイミングと立地を見極めれば、物件価格の上昇を味方につけた投資戦略は十分に成立します。
どんな物件がインバウンド向けの不動産投資に向く?

インバウンド投資で成果を出すには、物件選びが最も重要です。外国人観光客が求めているのは利便性と快適さであり、立地が悪ければどれだけ内装に投資しても稼働率は上がりません。
実際に収益を上げている投資家は、ターゲットとなる宿泊客を明確に定め、そのニーズに合った物件を戦略的に選んでいます。
どのような物件が実際に稼働率を維持できているのか、タイプ別に見ていきます。
都市部の駅近ワンルーム
特に山手線沿線や大阪メトロ御堂筋線沿いの物件は、外国人観光客にとって理解しやすい路線であり、予約が集中します。
築浅で管理が楽な物件
また、築浅物件は修繕費用が少なく、運営コストを抑えられるメリットもあります。
管理のしやすさも見逃せません。オートロック、宅配ボックス、無人チェックイン対応設備などが整った物件は、オーナーや管理会社の負担を軽減します。特に民泊運営では、鍵の受け渡しや夜間対応が課題になりがちですが、スマートロックやセルフチェックインシステムを導入すれば、遠隔管理が可能です。
築浅物件は購入価格が高めですが、リフォーム費用を抑えられる分、初期投資の総額は築古物件とさほど変わらない場合もあります。さらに、設備トラブルが少ないため、ゲストからのクレームやレビュー評価の低下を防げます。長期的に見れば、築浅物件のほうが安定した収益を生み出しやすいのです。
主要観光地の宿泊施設
ただし、観光地の物件は繁閑の差が大きく、オフシーズンの稼働率低下がリスクです。また、景観規制や文化財保護の観点から、リノベーションに制約がある場合もあります。
民泊や短期賃貸に適した物件
民泊に適した物件の条件は、住宅地でありながら交通アクセスが良く、周辺住民とのトラブルが起きにくい立地です。分譲マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されていないか確認が必須です。
短期賃貸は民泊よりも規制が緩く、マンスリーマンションとして運営すれば、長期滞在の外国人ビジネスパーソンや留学生をターゲットにできます。インバウンド需要は観光客だけでなく、ビジネスや学業での滞在者も含まれるため、幅広いニーズに対応できる物件が有利です。
観光地の一棟収益物件
一棟マンションや一棟アパートを丸ごと宿泊施設として運営する手法は、高い収益性を実現します。複数の部屋を同時に貸し出せるため、満室時の収入が大きく、利回り10%以上も珍しくありません。特に、観光地に近い立地では、家族連れやグループ旅行者のニーズに応えられます。
一棟物件のメリットは、運営の自由度が高いことです。民泊や簡易宿所として登録すれば、各部屋を独立して貸し出すことも、一棟貸しとして運営することも可能です。京都や金沢では、古民家を一棟リノベーションし、高級宿泊施設として再生する事例が増えています。
一方で、一棟物件は初期投資額が大きく、管理コストも高めです。清掃や設備管理を専門業者に委託する必要があり、運営ノウハウも求められます。しかし、収益性とブランド構築の可能性を考えれば、中級者以上の投資家にとって魅力的な選択肢です。
空港近くの利便性が高い物件
ただし、空港周辺は騒音や景観の問題があり、長期滞在には不向きです。あくまで1〜2泊の短期利用がメインとなるため、回転率を高める運営が求められます。それでも、リピーターが付きやすく、口コミ評価も得やすいため、安定した収益源となります。
リゾート地の別荘やコンドミニアム
北海道のニセコ、沖縄の恩納村、長野の軽井沢といったリゾート地では、別荘やコンドミニアムへの投資が活発です。これらのエリアは、外国人富裕層がバケーションやスキーリゾートとして訪れるため、高単価での宿泊運営が可能です。
さらに、オーナー自身がオフシーズンに利用し、ハイシーズンは宿泊施設として貸し出す「デュアルユース」も可能です。
インバウンド不動産投資の利回りはどれくらい?

インバウンド向け宿泊施設の利回りは、立地と運営方法次第で5%から12%程度まで幅があります。通常の賃貸マンションが3%から5%程度で推移している現状と比べれば、確かに魅力的な数字です。
投資資金をどのくらいの期間で回収できるのかを見ていきましょう。
ホテル・民泊投資の利回り
ホテル投資の表面利回りは、立地と規模によって5%〜10%が標準的です。東京都心部の小規模ホテル(客室数20〜30室)では、表面利回り6%〜8%が相場となります。一方、地方都市や観光地のホテルは、物件価格が抑えられる分、利回りが8%〜10%まで上昇するケースもあります。
民泊投資の利回りはさらに変動幅が大きく、運営形態によって4%〜12%と幅があります。ただし、民泊新法による営業日数制限(年間180日)がある地域では、実質利回りが大幅に低下します。特区民泊や簡易宿所として届出すれば365日営業が可能となり、利回りは大幅に改善できます。
初期投資の目安
インバウンド不動産投資の初期投資額は、物件タイプによって大きく異なります。都市部のワンルームマンションを民泊運営する場合、物件価格は2,000万円〜3,500万円が相場です。
これに加えて、リフォーム費用(50万円〜150万円)、家具家電の購入(30万円〜80万円)、初期登録費用(10万円〜30万円)が必要となり、総額で2,100万円〜3,800万円程度が初期投資となります。
インバウンド向けの不動産投資の主なリスクは?

インバウンド投資は高い収益性が魅力ですが、通常の不動産投資にはないリスクも抱えています。
大阪のように法規制が突然変わって営業ができなくなる可能性、観光客が減れば一気に空室が増える不安定さ、為替変動による影響、そして自然災害への備えなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。運営を任せる管理会社の質によっても収益性は大きく左右されます。
これらのリスクは避けられないものですが、事前に理解して対策を講じておけば、被害を最小限に抑えることができます。具体的にどのようなリスクがあり、どう備えるべきかを確認していきましょう。
法律や規制の変更リスク
将来的な規制変更に備えるには、複数の運営形態に対応できる柔軟性を持つことが重要です。民泊運営が困難になった場合でも、マンスリーマンションや通常の賃貸に切り替えられる物件であれば、リスクを分散できます。業界団体や専門家の情報をこまめに追い、法改正の動向を早期に把握する姿勢も欠かせません。
空室リスク
空室リスクを軽減するには、複数の需要層をターゲットにする戦略が有効です。観光客だけでなく、ビジネス出張者や国内旅行者、長期滞在の外国人ビジネスパーソンなど、多様なニーズに対応できる物件と運営体制を整えることです。都市部の駅近物件であれば、インバウンド需要が減少しても、国内需要で一定の稼働率を維持できます。
価格戦略も重要です。閑散期には割引価格で稼働率を維持し、繁忙期には単価を上げて収益を最大化する動的価格設定が効果的です。また、長期滞在プランや連泊割引を設定することで、安定した予約を確保できます。さらに、複数の予約プラットフォーム(Airbnb、Booking.com、楽天トラベルなど)に同時掲載することで、集客チャネルを多角化し、空室リスクを分散できます。
為替リスク
為替リスクへの対策として、国内需要との併用が効果的です。インバウンド依存度が高い物件ほど、為替変動の影響を受けやすくなります。国内旅行者やビジネス利用者も取り込める立地と価格設定であれば、為替変動による影響を緩和できます。
自然災害リスク
立地選定においても、ハザードマップを確認し、津波や洪水のリスクが低いエリアを選ぶことが重要です。海岸沿いや河川近くの物件は、災害リスクが高い傾向にあります。また、災害発生時の事業継続計画(BCP)を事前に策定しておくことも有効です。
物件完成リスク
新築物件やリノベーション物件への投資では、建築中の中止や遅延のリスクがあります。建設会社の倒産、資材価格の高騰、施工トラブルなどにより、予定通りに物件が完成しないケースも少なくありません。特に、地方の小規模建設会社や、実績の乏しい業者との契約では、完成リスクが高まります。
物件完成リスクを回避するには、信頼できる大手デベロッパーや実績豊富な建設会社を選ぶことが基本です。過去の施工実績や財務状況を確認し、倒産リスクの低い業者と契約することが重要です。
中古物件やすでに完成している物件への投資であれば、このリスクは回避できます。初心者投資家にとっては、新築よりも中古物件のほうが、リスク管理の面で優れている場合が多いのです。
管理会社の信頼性問題
インバウンド向け宿泊施設の運営では、多くの投資家が管理会社に業務を委託します。清掃、ゲスト対応、予約管理、価格設定など、専門的なノウハウが求められるためです。しかし、管理会社の質にはばらつきがあり、悪質な業者に委託すれば、収益性の低下やトラブルの原因となります。
管理会社選定では、実績と評判を徹底的に調査することが不可欠です。運営物件数、平均稼働率、レビュー評価、トラブル対応の実績などを確認し、信頼できる業者を選びます。また、契約内容を詳細に確認し、管理手数料の内訳、解約条件、責任範囲を明確にしておくべきです。
インバウンド向けの不動産投資はどう始める?

インバウンド需要を狙った不動産投資を始めるには、計画的な準備が必要です。物件選定から法的手続き、内装整備、集客まで、それぞれのステップで適切な判断を下すことが収益を増加させるためには必要不可欠です。特に法規制や許認可の確認を怠れば、投資そのものが無駄になるリスクもあります。
ここでは、インバウンド不動産投資を始めるための具体的な手順を解説します。
エリアや物件タイプをリサーチする
次に、競合状況を調査します。既存の宿泊施設が飽和しているエリアでは、差別化が困難です。逆に、観光需要があるのに宿泊施設が不足しているエリアは、投資チャンスです。実際に現地を訪れ、駅からのアクセス、周辺の商業施設、治安、観光地との距離などを肌で感じることも重要です。オンライン情報だけでは分からない実態が、現地視察で明らかになります。
宿泊可能な物件か確認する
物件が宿泊施設として運営可能かどうかの確認は、投資判断の最重要ポイントです。まず、用途地域を確認します。住宅宿泊事業法に基づく民泊は、住居専用地域でも一定の条件下で営業できますが、自治体条例で制限されている場合があります。旅館業法に基づく簡易宿所の場合、用途地域によっては営業が認められないケースもあります。
分譲マンションの場合、管理規約が民泊や短期賃貸を禁止していないか確認が必須です。近年、多くのマンション管理組合が民泊禁止の規約改正を行っており、購入後に運営できないトラブルが頻発しています。購入前に管理組合に直接問い合わせ、書面で確認を取ることが安全です。
また、消防法や建築基準法の要件も満たす必要があります。簡易宿所として営業する場合、火災報知器や誘導灯の設置、避難経路の確保などが義務付けられます。建物の構造や築年数によっては、大規模な改修が必要になる場合もあります。事前に専門家(建築士や行政書士)に相談し、法的要件を満たせるか確認することが、無駄な投資を避けるための鍵です。
物件購入または賃貸契約を行う
物件の法的適格性が確認できたら、購入または賃貸契約に進みます。購入の場合、融資を活用するか自己資金で一括購入するかを決めます。金融機関の多くは、民泊や簡易宿所向けの融資に慎重であり、通常の不動産投資ローンよりも審査が厳しい傾向にあります。事業計画書を作成し、収益性と返済能力を明確に示すことで、融資承認の可能性が高まります。
賃貸契約で始める場合、転貸(サブリース)が可能な物件を探します。オーナーの許可なく民泊運営はできないため、契約前に用途を明確に伝え、書面で承諾を得ることが必須です。賃貸であれば初期投資を抑えられますが、契約期間や更新条件、退去時の原状回復費用などを慎重に確認する必要があります。
物件購入時には、瑕疵担保責任や契約不適合責任の内容を精査します。中古物件の場合、隠れた欠陥が後から発覚するリスクがあります。ホームインスペクション(住宅診断)を実施し、構造や設備の状態を専門家に確認してもらうことで、予期せぬ修繕費用を回避できます。
民泊営業許可や必要な申請を取得する
消防設備の設置も義務です。火災報知器、消火器、誘導灯などを設置し、消防署の検査を受けます。建物の規模や構造によって必要な設備が異なるため、事前に消防署に相談し、適切な設備を整えることが重要です。検査に不合格となれば、営業開始が遅れ、収益機会を逃すことになります。
許認可取得には専門知識が求められるため、行政書士や民泊コンサルタントに依頼するのも一案です。費用は10万円〜30万円程度かかりますが、手続きの確実性とスピードを考えれば、合理的な投資といえます。自力で進める場合は、自治体の担当窓口に何度も足を運び、不備のない書類を揃えることが成功の鍵です。
内装や設備を整備する
営業許可が取得できたら、内装と設備の整備に入ります。インバウンド向け宿泊施設では、清潔感と機能性が最優先です。床や壁のクロス張り替え、水回りの清掃・修繕、照明の更新などを行い、第一印象を良くします。外国人ゲストは清潔さに敏感であり、レビュー評価に直結するため、妥協は禁物です。
Wi-Fi環境の整備は必須です。高速インターネット回線を導入し、複数のデバイスが同時接続できる環境を整えます。外国人観光客の多くは、スマートフォンで情報収集や連絡を行うため、Wi-Fiの品質が満足度を左右します。パスワードは分かりやすく表示し、接続方法を多言語で案内することも重要です。
多言語対応も差別化のポイントです。施設内の案内表示を英語・中国語・韓国語などで作成し、ゲストがストレスなく過ごせる環境を整えます。家電の使い方、ゴミの分別方法、緊急連絡先などを多言語で説明したガイドブックを用意することで、トラブルを未然に防げます。また、スマートロックやセルフチェックインシステムを導入すれば、24時間対応が可能となり、運営効率が向上します。
民泊サイトに登録し集客する
すべての準備が整ったら、予約プラットフォームに登録します。Airbnbは世界最大の民泊プラットフォームであり、インバウンド集客には欠かせません。魅力的な写真と詳細な説明文を掲載し、物件の特徴や周辺環境をアピールします。写真はプロのカメラマンに依頼することで、予約率が大幅に向上します。
Booking.comや楽天トラベルなど、複数のプラットフォームに同時掲載することで、集客チャネルを多角化できます。各プラットフォームには異なるユーザー層がおり、Airbnbは個人旅行者、Booking.comはビジネス利用者、楽天トラベルは国内旅行者が多い傾向にあります。複数登録により、稼働率の最大化が可能です。
価格設定は競合物件を参考にしつつ、動的価格戦略を採用します。繁忙期には単価を上げ、閑散期には割引で稼働率を維持する柔軟な価格調整が、収益最大化の鍵です。また、初期段階ではレビュー獲得を優先し、やや低めの価格設定で予約を集め、高評価を積み重ねることが長期的な成功につながります。レビューが増えれば、検索順位が上がり、自然と予約が入るようになります。
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり、改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかっていませんか?さらに、厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか?
しかし、すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
そこでおすすめするのが、日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。

日本総合政策ファンドの最大の強みは、AI/DXテクノロジーを駆使した効率的なマッチングとデューデリジェンスです。お客様の投資条件や希望に最適な民泊物件を、膨大なデータベースから迅速に見つけ出します。以下のような価値ある資産を含む物件も多数取り扱っています。
- 旅館業法または特区民泊に基づく営業許可(年間365日運営可能)
- 即戦力となる清掃スタッフなどの運営体制
- 稼働開始に必要な家具家電や内装設備一式
さらに、物件だけでなく、運営ノウハウも一緒に取得できることが最大のメリットです。成功している民泊事業の運営方法、料金設定、集客戦略などの専門知識も継承できるため、民泊事業未経験の方でも安心して参入できます。
まずは無料で日本総合政策ファンドのコンサルタントに相談してみませんか?お客様の投資条件や希望を分析し、最適な民泊物件候補をご提案します。
まとめ
投資を始めるには、エリアと物件タイプのリサーチから着手し、宿泊施設として運営可能かを法的に確認した上で、物件取得と許認可取得を進めます。内装整備では清潔感とWi-Fi環境、多言語対応が重要であり、最終的に複数の予約プラットフォームに登録することで集客を最大化できます。