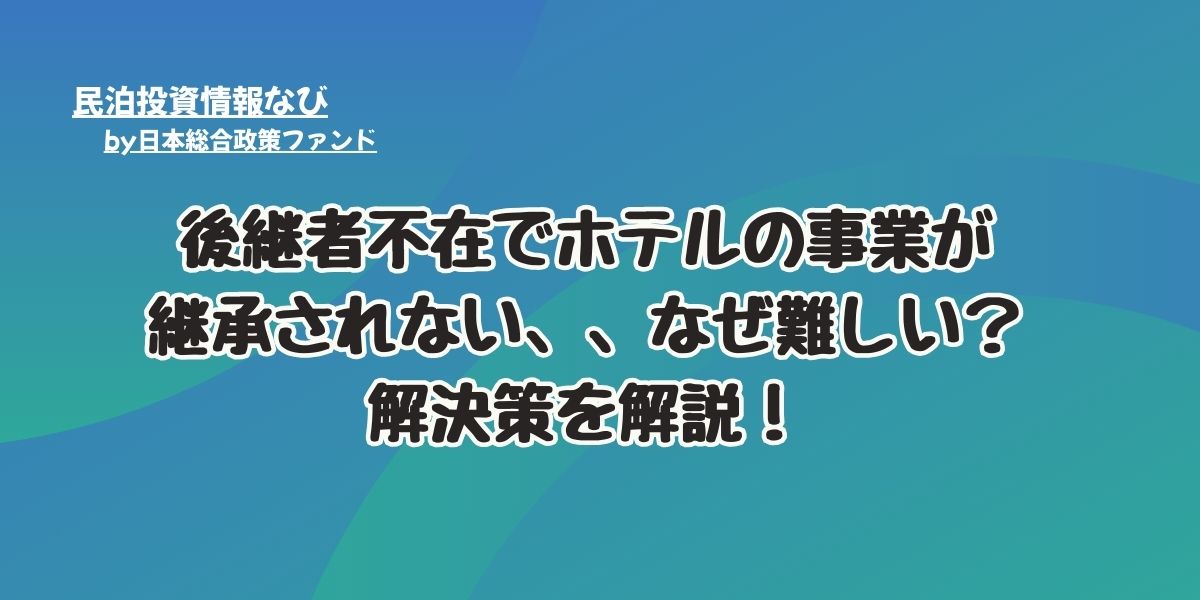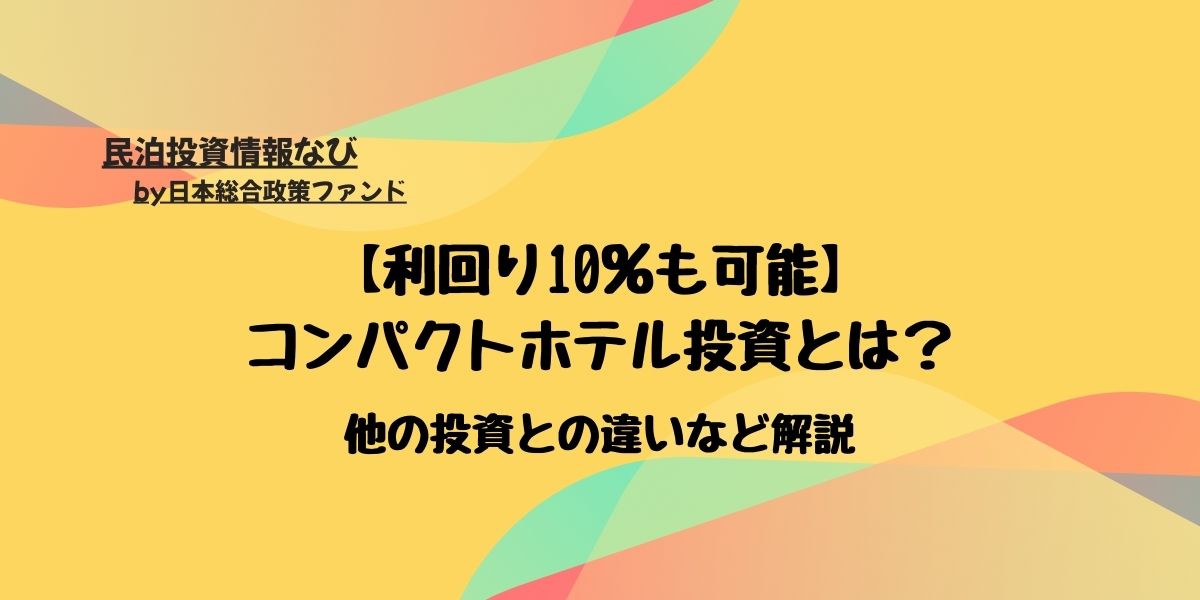「子供たちはホテル経営を継ぐ気がない」「このままでは廃業するしかないのか」-そんな悩みを抱えているホテル経営者の方は決して少なくありません。
ホテル事業の承継が困難な理由は明確です。運営ノウハウの属人化、24時間365日体制の過酷な労働環境、継続的にかかる人件費と維持管理費など、他の業種にはない特有の課題があります。しかし、だからといって廃業する必要はありません。ホテル事業を継承してもらうための方法があります。
この記事では、ホテル事業承継の現実的な課題から、後継者が不在の場合の事業継承の方法まで紹介します。
ホテル事業承継はなぜ難しい?

ホテル業界の事業承継は、他の業種と比較して極めて困難な課題を抱えています。観光庁の統計によると、全国の宿泊施設における後継者不在率は約65%に達しており、この数字は製造業の約45%、小売業の約52%を大きく上回る深刻な状況となっています。
特に地方の老舗旅館や中小規模のホテルでは、経営者の高齢化が急速に進む一方で、後継者の確保に苦戦する事例が続出しています。実際に全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の調査では、経営者の平均年齢が63.2歳となっており、10年前と比較して5歳以上も上昇している実態が明らかになっています。
この背景には、ホテル業特有の複雑な経営構造や、24時間365日体制の運営負荷、さらには近年の観光需要の変動やコロナ禍による業界全体の不安定さなど、多層的な課題が絡み合っています。
運営ノウハウが属人化している
加えて、ホテル業界特有の複雑な人間関係も属人化の要因となっています。地元の観光協会や行政との連携、同業他社との協力関係、地域の食材供給業者との信頼関係など、これらの人的ネットワークは一朝一夕で構築できるものではありません。
子世代がホテル経営を敬遠する傾向が強い
人件費・維持管理費が常にかかる
さらに、維持管理費の負担も深刻です。ホテルの建物や設備は24時間稼働するため、通常の建物よりも劣化が早く、定期的なメンテナンスや修繕が欠かせません。エレベーター、空調設備、給排水設備、電気設備など、どれか一つでも故障すれば営業に大きな支障をきたすため、予防保全の費用も相当な金額になります。
さらに厄介なのは、これらのコストが景気や観光需要の変動に左右されないという点です。コロナ禍で売上が大幅に減少した期間でも、建物の維持管理は続けなければなりません。
後継者が不在なら選択肢は?

ホテル経営において親族内での事業承継が困難な場合、経営者には複数の選択肢が存在します。それぞれの手法には特徴があり、メリットやデメリットによって適切な手法を活用しましょう。
親族外承継を行う
従業員承継の最大のメリットは、既存の運営ノウハウや顧客関係、従業員との信頼関係を維持しながら事業継続できることです。従業員が承継することのメリットは既にホテルの運営実態を熟知しているため、新たな学習コストや適応期間を最小限に抑えることが可能である点です。
ただし、従業員承継には資金調達の課題があります。ホテル事業の承継には相当な資金が必要となるため、一般的な従業員が自己資金だけで対応するのは困難です。この解決策として、段階的な株式譲渡や経営者保証の段階的解除、日本政策金融公庫の事業承継支援融資などの活用が有効です。現場で目にする典型的なパターンは、現経営者が一部の株式を残して段階的に譲渡し、承継者の経営能力を確認しながら完全承継を進める方法です。
外部人材の招聘による承継も選択肢の一つです。ホテルチェーンでの勤務経験がある人材や、他のホテルで支配人経験を持つ専門人材を招いて経営を委ねる方法です。この場合、既存の枠組みにとらわれない新しい発想での経営改革が期待できる一方で、地域性や既存顧客との関係構築に時間がかかるリスクもあります。
M&A仲介を使用して売却する
M&A仲介を利用する最大のメリットは、専門的なマッチングサービスによって最適な買い手を見つけられることです。優良な仲介会社は、ホテル業界に精通したアドバイザーが在籍し、売り手の事業内容や希望条件に応じて適切な買い手候補をリストアップしています。
仲介会社選びでは、ホテル業界での実績とネットワークを重視することが重要です。宿泊業特有の評価方法や業界動向を理解している仲介会社であれば、より精度の高い企業価値算定と効果的な買い手開拓が期待できます。特に立地や建物の特性、常連客の属性、地域との関係性など、数値化しにくい価値要素を適切に評価できる仲介会社を選ぶことが成功の分かれ目となります。
売却プロセスは通常6ヶ月から1年程度の期間を要します。初期段階では事業内容の整理と企業価値の算定を行い、次に買い手候補へのアプローチ、意向表明書の受領、基本合意の締結、デューデリジェンスの実施、最終契約の締結という流れで進みます。各段階で売り手の意向を確認しながら進めるため、納得できない条件での売却を強要されることはありません。
地域金融機関や公的機関の支援を活用する
さらに重要なのは、これらの支援機関が持つネットワークです。税理士、弁護士、不動産鑑定士、中小企業診断士など、事業承継に必要な専門家との連携体制が整っており、ワンストップで総合的な支援を受けることができます。実務的な観点から見ると、複数の専門家を個別に探して依頼するよりも、支援機関を通じて紹介を受ける方が効率的で費用対効果も高くなります。
M&Aでホテル事業承継を成功させるコツは?

M&Aによるホテル事業承継は、適切なプロセスを踏むことで売り手・買い手双方にとって理想的な結果をもたらします
しかし、成功の背景には周到な準備と戦略的なアプローチが不可欠です。特にホテル業界では、立地特性、顧客基盤、従業員のスキル、地域との関係性など、財務諸表だけでは表現できない価値要素が多く、これらを適切に評価し買い手に伝える技術が成否を分けます。
成功するM&Aには明確な目的設定、信頼できる仲介会社の選定、買い手との良好な関係構築、従業員への適切な配慮という4つの重要な要素があります。
関連:ホテルM&Aが注目されている理由とは?買い手と売り手のメリットなど解説!
なぜM&Aで事業継承を行うのか目的を明確化する
M&Aによる事業承継を検討する際、最も重要なのは「なぜM&Aを選択するのか」という目的の明確化です。この目的が曖昧なまま進めてしまうと、交渉の途中で方向性を見失い、結果的に満足できない結果に終わってしまう可能性が高くなります。
実際にサポートした案件で最も多い目的は、経営者の高齢化による引退準備です。特に70歳を超えた経営者の場合、体力的な限界や健康面の不安から、責任の重いホテル経営からの解放を求めるケースが大半を占めています。この場合の目的は明確で、適正価格での売却と従業員の雇用継続、そして自身の老後資金の確保が主な動機となります。
一方で、事業拡大や新規事業への資金調達を目的とするケースも増えています。現場で目にする典型的なパターンは、既存のホテル事業を売却した資金で別の地域に新しいホテルを開業したり、全く異なる業種への進出を図ったりする経営者です。この場合は単純な引退ではなく、経営者としてのセカンドキャリアを見据えた戦略的な選択となります。
また、目的の明確化は交渉戦略にも影響します。引退が目的なら一括での株式譲渡を、事業発展が目的なら段階的な資本参加から始めるアプローチを選択するなど、目的に応じて最適な取引スキームが変わってきます。そのため、目的を明確にしましょう。
M&A仲介会社の選ぶ
M&A仲介会社の選定は、ホテル事業承継の成否を左右する最も重要な決定の一つです。全国には数百社のM&A仲介会社が存在しますが、ホテル業界に精通し、適切なサービスを提供できる会社は限られています。仲介会社選びでは、手数料体系、サービス内容、担当者の専門性を総合的に評価する必要があります。
手数料体系については、透明性と合理性を重視して検討する必要があります。一般的には売却価格に応じた成功報酬型が主流ですが、着手金、中間金、最低手数料の有無や金額設定は会社によって大きく異なります。
しかし、最も安い手数料の会社を選べば良いというわけではありません。手数料が安すぎる会社は、案件に十分な時間と労力をかけられない可能性があり、結果的に売却価格が低くなってしまうリスクがあります。
さらに、担当者の専門性も重要な判断材料です。ホテル業界での勤務経験がある担当者や、宿泊業のM&Aを数多く手がけた経験を持つ担当者であれば、業界特有の価値要素を適切に評価し、買い手に効果的にアピールできます。特に立地の将来性、競合状況の分析、改装投資の必要性、運営ノウハウの価値など、専門的な知識が必要な分野での助言能力が重要です。
買い手とのコミュニケーションをとる
M&Aプロセスにおいて買い手との効果的なコミュニケーションは、成約の可能性を高めるだけでなく、売却後の事業継続にも大きく影響します。ホテル業界のM&Aでは、財務数値だけでは表現できない価値要素が多いため、売り手が直接買い手に事業の魅力や可能性を伝える機会が特に重要になります。
初回の面談では、ホテルの歴史や理念、地域での役割について率直に語ることが効果的です。実際にサポートした案件では、創業時の苦労話や地域イベントでの貢献活動、常連客との心温まるエピソードなどを売り手が熱心に語った結果、買い手が「このホテルの価値と責任を引き継ぎたい」と強い意欲を示したケースがあります。数字では表現できない無形資産の価値を理解してもらうためには、こうした感情に訴える情報共有が不可欠です。
経営課題についても隠さずに説明することが信頼関係の構築につながります。設備の老朽化、人材不足、競合の影響など、現在抱えている問題点を正直に開示し、同時にそれらの解決策や改善の可能性についても説明します。よく相談を受けるケースとして、売り手が問題点を隠そうとした結果、デューデリジェンスの段階で発覚し、買い手の信頼を失ってしまう事例があります。
コミュニケーションの頻度と方法も成功要因の一つです。仲介会社を通じた正式な情報交換だけでなく、必要に応じて売り手と買い手が直接対話する機会を設けることで、相互理解が深まります。現場で目にする典型的なパターンは、月1回程度の定期的な進捗確認会議を設け、疑問点や懸念事項をその都度解決していく方法です。
交渉過程では感情的にならず、建設的な議論を心がけることが重要です。価格や条件面で意見が分かれた場合でも、相手の立場を理解し、妥協点を見つける姿勢を示すことで、最終的な合意に至る可能性が高まります。実務的な観点から見ると、小さな条件の違いで交渉が決裂してしまうケースは意外に多く、柔軟性を持った対応が求められます。
従業員とも適切なコミュニケーションをとる
M&Aプロセスにおける従業員とのコミュニケーションは、事業承継の成功を左右する極めて重要な要素です。ホテル業界では人材こそが最大の競争力であり、優秀な従業員の流出は事業価値の大幅な下落につながるため、細心の注意を払った対応が必要となります。
情報開示のタイミングと範囲については、慎重な戦略が求められます。M&A検討の事実を早すぎる段階で開示すると、従業員の不安から離職が相次ぐリスクがあります。一方で、あまりに遅いタイミングでの開示は従業員の信頼を損ない、売却後の協力を得られなくなる可能性があります。多くの人々は、事業の売却(M&A)は良くないイメージを持っています
そのため、従業員への説明では、M&Aの必要性と将来のメリットを明確に伝えることが重要です。そして従業員から出た意見を聞き、従業員の雇用と処遇について具体的で安心できる説明をすることで不安解消を行うことができます。
まとめ
ホテル事業承継の困難さは、運営ノウハウの属人化、子世代の経営敬遠、継続的なコスト負担という構造的な課題に起因しています。しかし、これらの課題を理解した上で適切な対策を講じれば、必ず解決の道は見つかります。
親族内での承継が困難な場合でも、従業員承継、M&A仲介による売却、地域金融機関や公的機関の支援など、多様な選択肢が用意されています。特にM&Aによる事業承継では、目的の明確化、信頼できる仲介会社の選定、買い手・従業員との丁寧なコミュニケーションが成功の鍵となります。