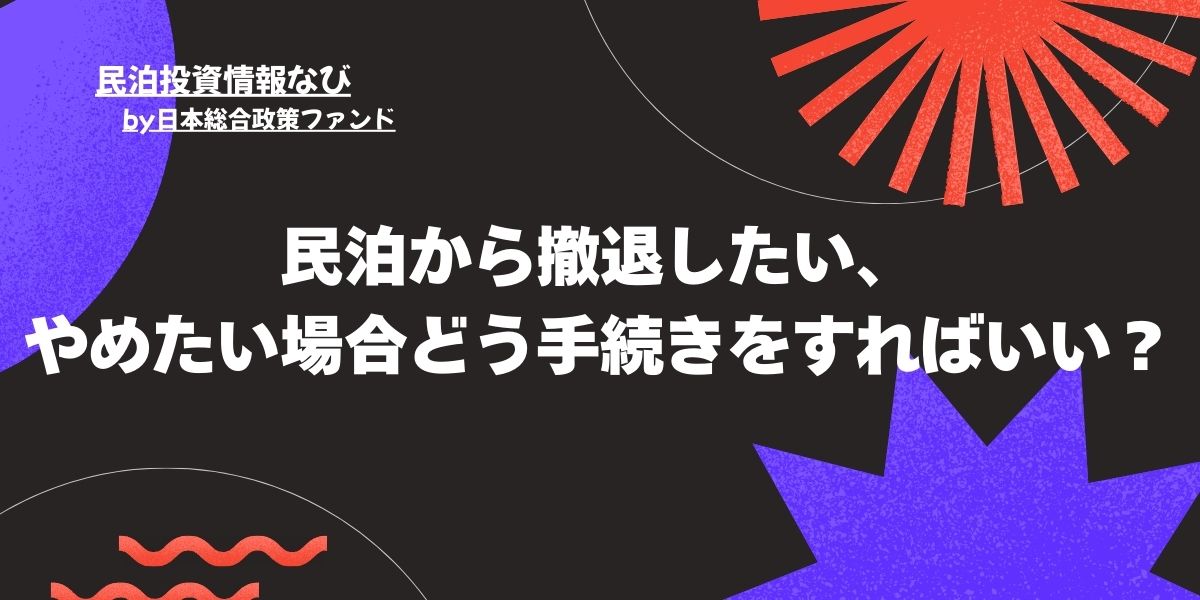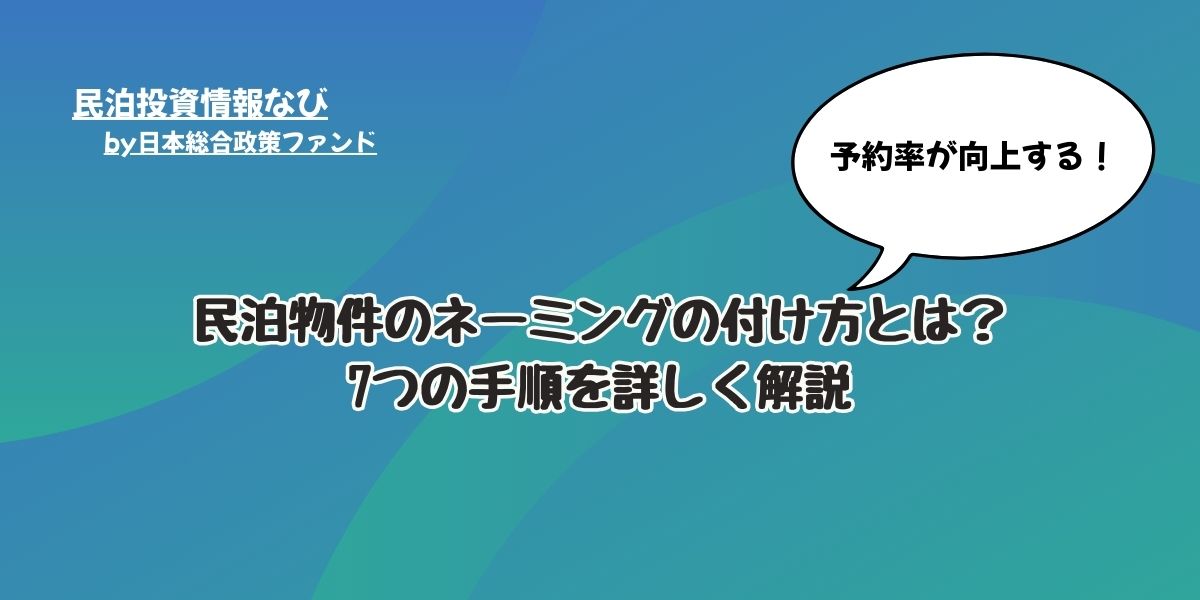「投げ売りしないと損失が膨らむ一方…」「撤退したいけど物件が売れない…」「民泊事業、いつ見切りをつければいいの?」—こうした悩みを抱える民泊オーナーが急増しています。かつて利回りが100%以上見込めるとして”夢の投資先”と謳われた民泊ビジネスですが、規制強化や市場競争の激化により、思うような収益が得られず撤退を検討されている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、民泊物件の投げ売りが増加している背景から、撤退時に注意すべきリスク、最適な撤退タイミング、そして物件を迅速に売却する方法までを徹底解説します。
民泊物件の投げ売りが増加する背景とは?

民泊事業者の間で「投げ売り」や「撤退」という言葉をよく耳にするようになりました。なぜ民泊物件の投げ売りが増加しているのか、その背景には複数の要因が絡み合っています。
規制強化による収益性の低下によって
加えて、消防法や建築基準法の適合義務、24時間対応可能な管理体制の整備など、安全面や管理面での要件も厳格化されました。これらの対応には追加コストがかかるため、特に小規模事業者にとっては大きな負担となりました。
供給過多による競争激化による収益の悪化によって
民泊市場の成長期には多くの参入者が殺到しましたが、その結果として供給過多の状況が生まれました。特に観光地や都市部の人気エリアでは、民泊物件が乱立する状況となりました。
東京、大阪、京都などの主要観光地では、外国人観光客の増加を見越して多くの投資家が民泊事業に参入しました。しかし、同じエリアに類似した物件が増えすぎたことで、価格競争が激化しています。
また、ホテルチェーンも民泊に対抗して価格を下げる動きを見せており、宿泊業界全体で価格競争が激化しています。特にビジネスホテルの価格帯と民泊の価格帯が重なるようになり、清掃やアメニティ面でサービス品質に差がある中で選ばれるのは難しくなっています。
資金繰りの悪化によって支払いが困難になったため
民泊事業は、物件購入やリフォーム費用など、初期投資に多額の資金を必要とします。多くの事業者はローンを組んで参入しましたが、想定よりも収益が上がらないことで資金繰りが悪化するケースが増えています。
民泊物件の購入には、一般的な住宅ローンより金利の高い投資用ローンを利用するケースが多く、毎月の返済負担は決して軽くありません。当初の事業計画では高い稼働率と単価を見込んでいたものの、実際には思うように予約が入らないことで、キャッシュフローが悪化しています。
さらに、民泊には予約サイトへの手数料(15-20%程度)、清掃費、アメニティ費、修繕費、光熱費など様々なランニングコストがかかります。これらの支出が収益を圧迫し、ローン返済が困難になるケースが増加しています。
特に複数物件を運営している事業者の場合、一部の不採算物件が全体の収支を圧迫する「足を引っ張る」状況に陥ることがあります。このような状況では、不採算物件を早期に売却して資金回収を図る判断をする事業者が増えています。
また、資金繰りの悪化は単に物件の維持が困難になるだけでなく、サービス品質の低下につながり、さらに予約が減少するという悪循環を生み出すこともあります。このような状況から脱却するために、赤字覚悟での投げ売りに踏み切るケースも見られます。
社会情勢や経済状況の悪化によって需要が減少したため
民泊市場は外部環境の変化に大きく左右される特性があります。特にコロナウイルスの影響は甚大で、インバウンド需要が急減したことで多くの民泊事業者が打撃を受けました。
2020年以降の入国制限によって、それまでの主要顧客であった外国人観光客が激減し、多くの民泊物件は長期間にわたって予約がゼロという状況に直面しました。このような需要の蒸発は、事業継続の判断を迫る重大な出来事となりました。
このような社会情勢や経済状況の変化によって、事業継続の見通しが立たなくなった事業者が増加し、撤退や投げ売りの動きが加速しています。
民泊撤退時に注意すべきこととは?

民泊事業からの撤退を検討する際、単に物件を売却して終わりというわけにはいきません。撤退の過程では様々なリスクが潜んでいます。
事業者の方々が陥りがちな盲点や見落としやすいポイントを中心に、撤退時のリスクについて詳しく解説します。
契約違反や規制変更による罰金・訴訟のリスク
民泊事業からの撤退を急ぐあまり、既存の契約関係や法的義務を軽視してしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。特に注意が必要なのは、各種契約や法規制に関連するリスクです。
まず、民泊物件を管理委託している場合、管理会社との契約には解約条項や違約金の規定があることが一般的です。契約期間の途中での解約となると、残存期間分の管理料相当額を請求されるケースもあります。
また、予約サイトとの契約も重要です。Airbnbなどの大手予約サイトでは、突然のリスティング削除によってゲストに損害が生じた場合、ホスト(事業者)に賠償責任が発生する可能性があります。
さらに、行政への届出についても慎重な対応が必要です。住宅宿泊事業法に基づく「廃業等届出書」の提出を怠ると、行政処分の対象となる可能性があります。撤退後も民泊として運営されていると誤認され、定期報告の未提出として過料の対象となるケースもあります。
さらに、賃貸物件で民泊を運営していた場合、原状回復義務が発生します。一般居住用とは異なる民泊仕様の改修部分については、撤退時に完全な原状回復が求められることが多く、想定以上の費用負担につながることがあります。
初期投資の回収不足や追加費用の発生のリスク
民泊事業からの撤退を決断した際、多くの事業者が直面するのが初期投資の回収不足と予想外の追加費用の問題です。これらの財務的リスクは、撤退後の生活や次の事業展開にも影響を及ぼします。
典型的なケースとして、物件購入時に投資用ローンを組んでいる場合、売却価格がローン残債を下回る「債務超過」状態に陥るリスクがあります。不動産市況の悪化や物件の価値低下により、当初の購入価格を大きく下回る価格でしか売却できないことがあります。
また、民泊専用にリフォームした物件は、一般居住用としての価値が低下していることがあります。
加えて、撤退時には各種解約手続きにも費用がかかります。インターネット回線、スマートロックのシステム解約など、月額サービスの中途解約には違約金が発生するケースも少なくありません。こうした費用は小さく見えますが、複数の契約を解除する場合、合計すると無視できない金額になることがあります。
予約のキャンセル処理が不十分なことによるトラブル発生のリスク
予約のキャンセル処理を適切に行わない場合、最悪のシナリオとして「ゲストが実際に到着したが、宿泊できない」という事態が発生します。
このようなトラブルは、単に一度の予約キャンセルの問題で終わらないことが多いです。
予約キャンセルには丁寧な対応が必要です。単にシステム上でキャンセル処理をするだけでなく、各ゲストへの個別連絡と謝罪、代替宿泊先の提案などが求められます。特に繁忙期の予約キャンセルは、ゲストにとって深刻な問題となるため、十分な余裕をもって対応することが重要です。
予約管理の混乱を防ぐためには、撤退の決断後、すぐに新規予約の受け付けを停止し、既存予約の整理に取り掛かるべきです。また、撤退完了までのスケジュールを明確にし、余裕をもったタイムラインを設定することで、ゲストへの影響を最小限に抑えることができます。
民泊事業を撤退できるベストな時期は?

民泊事業からの撤退を検討する際、「いつ撤退するか」というタイミングは、その後の資産価値や財務状況に大きな影響を与えます。撤退の意思決定は感情的になりがつですが、冷静な判断が必要です。市場動向や自身の状況を的確に分析し、最適なタイミングで撤退することが、損失を最小限に抑えるポイントになります。ここでは、民泊事業からの撤退に適したタイミングについて詳しく解説します。
民泊市場がピークを迎えた時
投資の世界では「高く売り抜ける」ことが理想とされますが、民泊事業においても同様の考え方が適用できます。市場がピークを迎えた時期は、物件価値が最大化している可能性が高く、投資回収の観点から見ると最適な撤退タイミングといえます。
市場がピークにあるサインとしては、民泊物件の取引価格の高騰が挙げられます。例えば、2017年から2018年にかけては、民泊新法施行前の期待感から、都心部の民泊向け物件の価格が急上昇しました。この時期に売却した事業者は、物件価値の上昇分も含めて高いリターンを得ることができました。
また、新規参入者の急増も市場ピークのサインです。「今から民泊を始めたい」という問い合わせや相談が増加し、民泊セミナーが頻繁に開催されるような時期は、市場が過熱している可能性があります。こうした状況では、経験の浅い新規参入者が高値での物件購入に前向きなケースも多く、売り手にとって有利な環境が整っています。
さらに、実際の稼働率や収益性以上に物件価格が上昇している状況も、ピークのサインです。収益還元法で算出される適正価格より高い取引が増えてきたら、市場が過熱している可能性が高いです。
市場のピークを見極めるのは簡単ではありませんが、一定期間の市場動向を観察し、「これ以上の上昇は見込めない」と判断できるタイミングで撤退を検討することが重要です。
予約が減少傾向にある時
自身の運営する民泊物件の予約状況は、撤退のタイミングを判断する上で重要な指標になります。予約の減少傾向が一時的なものではなく、構造的な問題に起因する場合は、早めの撤退を検討すべきタイミングといえます。
予約減少の具体的なシグナルとしては、前年同月比での稼働率の継続的な低下が挙げられます。特に、繁忙期の稼働率が前年を下回るようになった場合は注意が必要です。季節要因や一時的なイベントによる変動ではなく、3ヶ月以上連続して前年割れが続く場合は、市場環境の構造的な変化が起きている可能性があります。
また、価格設定を下げても予約が増加しない状況も要注意です。以前は価格を下げれば予約が入っていたのに、大幅な値下げをしても予約が増えないというケースは、需要の質的な変化が起きている可能性を示しています。
予約データの分析においては、単なる表面的な数字だけでなく、予約の質的な変化にも注目することが重要です。
契約の更新時期
物件に関わる様々な契約の更新時期は、撤退のタイミングとして検討する価値があります。契約更新のタイミングで撤退することで、違約金や追加コストを最小限に抑えられる可能性が高まります。
まず、賃貸物件で民泊を運営している場合、賃貸借契約の更新時期が重要です。一般的に契約更新時には解約しても違約金が発生しないケースが多く、更新のタイミングで撤退を決断することで、余分なコストを抑えられます。
管理委託契約についても同様で、契約期間の満了時に解約するのがベストです。契約期間の途中で解約すると、違約金として残存期間の管理料の一部または全部を請求されるケースがあります。
契約更新時期に合わせた撤退計画を立てる際は、各契約の更新日をカレンダーにマッピングし、最もコスト効率の良いタイミングを見極めることが重要です。多くの契約が重なる時期を見つけ、そのタイミングに向けて計画的に撤退の準備を進めることで、スムーズな出口戦略を実現できます。
規制が厳格化する前
民泊事業は行政の規制に大きく影響される事業です。新たな規制導入や既存規制の厳格化が予定されている場合、その施行前に撤退することで、規制対応コストや物件価値の低下を回避できる可能性があります。
規制強化の兆候としては、まず自治体や国レベルでの法改正の動きに注目すべきです。
また、地域の住民感情や自治体の姿勢変化も重要なサインです。例えば、地域住民からの苦情が増加し、自治体が民泊に対して厳しい姿勢を示し始めた場合、将来的に厳しい条例が制定される可能性があります。特に、マンションの管理組合が民泊禁止の方向で動き始めた場合は、早めの撤退を検討すべきでしょう。
規制変更の情報収集においては、業界団体や専門家のセミナー、ニュースレターなどを活用することが効果的です。
財務的な負担が増加する前
民泊事業の財務面での負担増加が予測される場合、その前に撤退することで損失を最小限に抑えられます。財務的負担には、金利上昇、税制変更、修繕費用の増加など様々な要因が考えられます。
まず、変動金利のローンで物件を購入している場合、金利上昇のタイミングは重要な判断材料となります。金融政策の変更や市場金利の上昇傾向が見られる場合、将来的なローン返済負担の増加を見越して、早めの撤退を検討すべきです。
また、固定資産税の評価替えのタイミングも考慮すべき要素です。固定資産税は3年ごとに評価替えが行われ、場合によっては税負担が増加することがあります。評価替えの時期と税額の予測情報を得た上で、増税前の撤退を検討することも一つの戦略です。
さらに、物件の経年劣化による修繕費用の増加も重要な要素です。建物の築年数が上がるにつれて、設備の更新や修繕の必要性が高まります。特に、築10年、15年、20年といった節目には大規模な修繕が必要になることが多く、そうした大型支出が発生する前に撤退することで、追加投資を避けることができます。
民泊からの撤退は、感情的な判断ではなく、市場の動向や自身の状況を冷静に分析した上での戦略的な決断が求められます。上記のような要素を総合的に判断し、最適なタイミングで撤退することで、投資回収を最大化し、次のステップへの移行をスムーズに進めることができます。
民泊物件をすばやく売却する方法には何がある?

民泊事業からの撤退を決断した後、次に直面するのが物件の売却です。民泊市場の変化が激しい中、いかに迅速かつ適正な価格で売却するかは、撤退の成否を左右する重要なポイントとなります。
ここでは、民泊物件を迅速に売却するための実践的な方法について解説します。
民泊M&A仲介会社を使用する
民泊M&A仲介会社の最大の強みは、すでに民泊事業に取り組んでいる事業者や新規参入を考えている投資家など、ターゲットを絞ったバイヤー層へのアプローチが可能な点です。これにより、単なる不動産としてではなく、「稼働中の事業」として物件を評価してもらえる可能性が高まります。実際に、過去の実績や予約データ、運営ノウハウなども含めた「事業譲渡」として取引することで、物件単体よりも高い価格での売却に成功した事例も多数あります。
民泊M&A仲介会社を活用する際のポイントとしては、まず手数料体系の確認が挙げられます。一般に成約価格の3〜5%程度の手数料が発生しますが、会社によって異なるため事前に確認が必要です。また、専門会社といっても得意なエリアや物件タイプがある場合が多いため、自分の物件に合った仲介会社を選ぶことが大切です。
さらに、M&A仲介会社を通じた売却の場合、単に物件を引き渡すだけではなく、一定期間の運営サポートや顧客データの引継ぎなどが条件となることもあります。こうした条件も含めて検討し、自分の状況に合った売却方法を選ぶことが重要です。
また、秘密保持契約を結んだ上での売却も可能なため、「売却中」という情報が広まることなく、現在の予約や運営に影響を与えずに売却プロセスを進められる点も大きなメリットです。
\民泊特化のM&A仲介会社/
不動産会社を使用する
一般の不動産会社を通じた売却は、最もオーソドックスな方法です。地域密着型の中小不動産会社から全国チェーンの大手不動産会社まで、様々な選択肢があります。しかし、民泊物件の売却においては、いくつかの注意点があります。
最大の課題は、民泊物件としての価値が適切に評価されない可能性がある点です。多くの不動産会社は一般的な居住用不動産の取引を主としており、民泊特有の価値要素(稼働率や収益性、予約チャネルの整備状況など)を適切に評価するノウハウを持っていないことがあります。そのため、収益物件としての価値よりも単なる居住用物件として査定されてしまい、本来の価値よりも低い価格設定になってしまうケースがあります。
また、民泊向けにリフォームした物件は、一般居住用としては使いにくい間取りになっていることも多く、そうした物件は一般の買い手にとっての魅力が低下するため、売却に時間がかかりやすいという問題もあります。
不動産会社を選ぶ際のポイントとしては、まず民泊や収益不動産の取引実績があるかどうかを確認することが重要です。
また、複数の不動産会社に査定を依頼し、査定価格やマーケティング戦略を比較検討することも有効です。単に高い査定価格を出した会社を選ぶのではなく、市場分析や販売戦略の具体性、担当者の知識や熱意なども総合的に判断しましょう。
売却を迅速に進めるためには、最初から適正な価格設定をすることが重要です。「高く売り出して、様子を見て値下げする」という戦略は、結果的に売却期間の長期化につながることが多いです。市場動向を冷静に分析し、6ヶ月以内に売却できる現実的な価格設定を心がけましょう。
まとめ
民泊事業からの撤退は、単なる「物件売却」ではなく、様々な要素を考慮した戦略的な判断が求められます。本記事では、民泊物件の投げ売りが増加している背景として、規制強化による収益性の低下、供給過多による競争激化、資金繰りの悪化、社会情勢の変化による需要減少などを解説しました。
撤退のベストタイミングとしては、市場のピーク時、予約減少傾向の初期段階、契約更新時期、規制強化前、財務負担増加前などが考えられます。
物件売却には民泊M&A仲介会社の活用や適切な不動産会社の選定が重要です。撤退を検討されている方は、これらの知識を踏まえて計画的かつ冷静な判断を行い、次なる投資機会へとスムーズに移行されることをお勧めします。