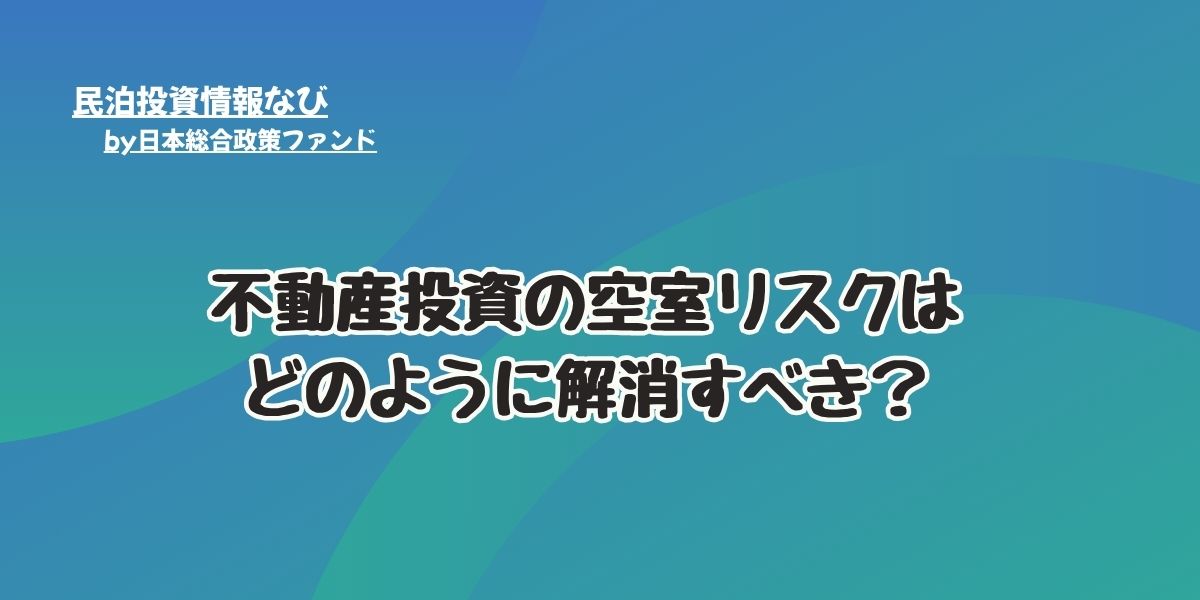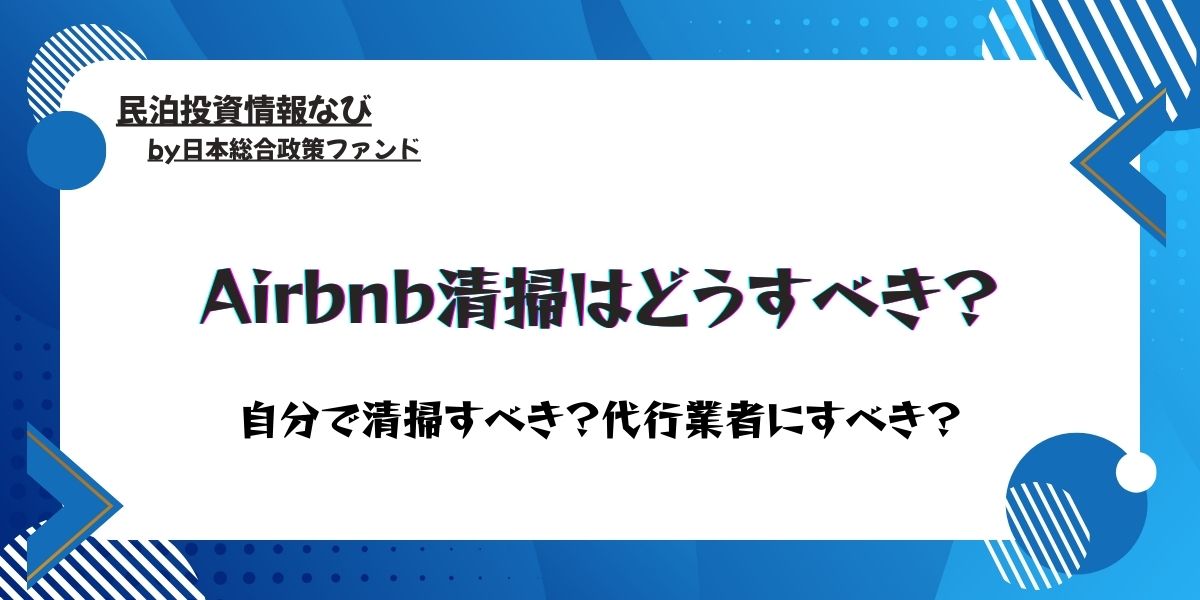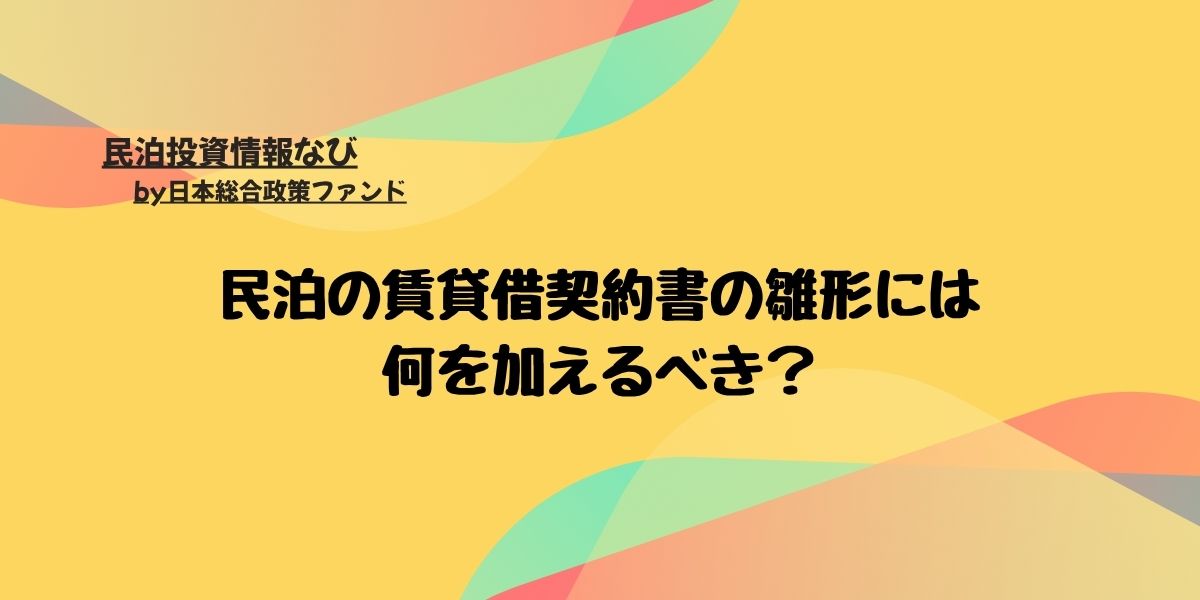不動産投資を始めたものの、空室が続いて家賃収入が途絶える不安を抱えていませんか?毎月のローン返済や管理費は待ってくれません。
空室リスクは、物件選びのミスや市場環境の変化によって誰にでも起こりえます。家賃設定が相場より高い、立地が悪い、競合物件が増えているなど、原因は複数絡み合っています。これらの原因を正確に把握しなければ、的外れな対策に時間とお金を浪費してしまいます。
この記事では、空室が発生する具体的な原因、資金繰りへの影響、そして実際に効果が出る対処法について解説します。
空室が発生する主な原因を知っていますか?
空室が続く要因は、単純に”タイミングが悪い”だけではありません。家賃設定のミス、立地の問題、物件の老朽化、競合増加など、複数の要素が複雑に絡み合っています。これらの原因を正確に理解しなければ、的外れな対策にお金と時間を浪費する可能性が高まります。
以下が、実際によく見られる4つの原因を具体的に解説します。
家賃設定が不適切である
家賃を決める際、「周辺相場より少し高くても良い物件なら借りてくれるはず」と考えがちです。
しかし現実には、相場から5000円でも高ければ内見すら入らないケースが多発します。
家賃相場の調査不足で失敗する理由は明確です。不動産ポータルサイトの掲載物件を見て「この程度の家賃で良いだろう」と安易に決めると、実際の成約家賃とズレが生じます。掲載されている家賃は”希望価格”であり、実際の成約価格ではありません。
さらに、築年数や設備を無視した価格設定も危険です。築20年の物件を築10年相場で募集しても、入居者は冷静に比較します。エアコンが古い、バストイレ別でない、収納が少ないなど、物件スペックが劣っているのに家賃だけ強気だと、競合に流れます。
立地や周辺環境が良くない
立地条件は、変更不可能な要素だからこそ、購入前の判断が決定的です。駅から遠い、坂道が多い、周辺に商業施設がない、治安が悪いなど、立地の問題は入居者募集に直結します。
駅からの距離は最も重要な指標です。徒歩10分を超えると、一気に需要が落ちます。徒歩15分以上になると、よほど家賃を下げるか、他の魅力的な要素がない限り、選択肢から外されます。バス便の物件はさらに厳しく、バスの本数や終バス時刻も入居希望者は細かくチェックします。
周辺環境の変化も見逃せません。近隣に大型商業施設ができれば好材料ですが、逆に主要なスーパーや病院が撤退すると、一気に不便になります。地域の人口動態や企業の動向を継続的に追わないと、気づいたときには手遅れです。
立地問題への対策は限られています。家賃を下げるか、ターゲットを変更するしかありません。駅から遠いなら、車通勤者向けに駐車場を無料にする、ペット可にして選択肢を広げるなど、別の魅力を付加する必要があります。
物件の内装や外見が古いまま
内見時の第一印象は決定的です。玄関を開けた瞬間、壁紙が黄ばんでいる、床が傷だらけ、照明が暗いなど、マイナス要素が目立つと、内見者は即座に候補から外します。クリーニングだけでは解決できない劣化は、リフォーム投資が必要です。
水回りの古さは特に敬遠されます。キッチンのシンクが錆びている、浴室のカビが目立つ、トイレが和式のままなど、水回りの問題は生活の質に直結するため、優先度が高いです。最新設備にする必要はありませんが、清潔で機能的な状態を保つべきです。
さらに、外観の印象も重要です。エントランスが汚い、外壁にヒビが目立つ、共用部にゴミが散乱しているなど、外から見える部分の管理が行き届いていないと、内見前に候補から外されます。区分マンションの場合、管理組合の修繕計画が遅れていると、個別の努力だけでは改善できません。
設備の老朽化も見逃せません。エアコンが古い、給湯器の調子が悪い、インターホンが故障しているなど、生活に必要な設備が不十分だと、入居後のトラブルにもつながります。入居前に点検し、必要なら交換する判断が必要です。
競合物件が増加している
同じエリアに新築物件や大規模リノベ物件が次々と登場すると、既存物件の競争力は一気に低下します。競合増加の影響を過小評価すると、空室リスクは急激に高まります。
新築マンションの竣工ラッシュは、賃貸市場に大きな影響を与えます。新築は設備が最新で、デザインも洗練されており、初期費用が多少高くても選ばれやすいです。築浅物件が増えると、築10年以上の物件は相対的に見劣りしてしまいます。
空室率が高まると資金繰りはどうなる?

空室が発生すると、家賃収入がゼロになります。しかし支出は一切減りません。ローン返済、管理費、修繕積立金、固定資産税など、毎月確実に支払いが発生します。
この収入と支出のバランスが崩れると、資金繰りは急速に悪化します。空室が続くほど、オーナーの手出しが増え、最悪の場合は破綻につながります。
以下、空室率上昇が引き起こす具体的な資金繰りの問題を解説します。
固定費の支払いが厳しくなる
不動産投資の固定費は、入居者の有無に関係なく発生します。空室期間が長引けば、これらの固定費がそのまま赤字として積み重なります。
ローン返済は最大の固定費です。毎月10万円の返済がある物件で、家賃収入が10万円だったとします。空室になれば、10万円が丸々持ち出しになります。1ヶ月なら耐えられても、3ヶ月続けば30万円、半年なら60万円の赤字です。貯金を切り崩すか、給与収入から補填するしかありません。
管理費と修繕積立金、固定資産税なども空室期間中も確実に請求が来ます。
これらの支払いが滞れば、最悪の場合、物件を差し押さえられます。ローンの延滞が続くと、金融機関は容赦なく法的手続きに入るため早めの空室を解消することが必要です。
新規入居者募集のための追加コストがかかりやすい
空室が長引けば、ただ待っているだけでは埋まりません。入居者を確保するために、追加のコストが発生します。
空室を埋めるためには、広告費の増額は避けられません。通常の仲介手数料だけでは反応が薄い場合、広告費を上乗せする必要があります。特にSUMMOやLIFULLなどのプラットフォームを活用すると使用量が発生します。
さらに、リスティング広告を使用するとインプレションはつきますが、追加で費用がかかいます。
敷金・礼金の引き下げも、実質的なコスト増です。競合物件が敷金・礼金ゼロで募集している中、自分だけ高額な初期費用を設定しても、選ばれません。敷金・礼金を下げれば入居者は決まりやすくなりますが、初期収入が減り、退去時の原状回復費用も自己負担になります。
将来的に売却価格の下落リスクもある
空室率が高い物件は、売却時にも不利です。買主は収益性を最重視するため、空室が多い物件は敬遠されます。売却価格の下落は、資産価値の毀損を意味します。
長期空室物件は、買主にネガティブな印象を与えます。「なぜこの物件は空室が続いているのか?」と疑念を持たれ、価格交渉で大幅に値下げを要求されます。立地の問題、設備の劣化、管理の不備など、空室の原因を買主は厳しくチェックします。
売却を急げば、さらに価格は下がります。資金繰りが悪化し、早急に現金化したい状況では、買主に足元を見られますが、売却のタイミングを逃すと、損失は拡大します。
空室が長期化した時の対処法

空室が3ヶ月以上続けば、何らかの対策が必要です例えば、家賃調整、リフォーム、用途変更など、複数の選択肢を検討し、最も合理的な方法を選ぶべきです。
ここでは実際に効果が出やすい3つの対処法を、具体的なデータと実例を交えて解説します。
家賃設定を見直す
家賃を下げれば入居者は決まりやすくなります。しかし、どの程度下げるべきか、判断に迷うオーナーは多いです。下げすぎれば収益性が悪化し、中途半端な値下げでは効果が出ません。
相場との乖離を正確に把握する必要があります。
もし、家賃を下げるタイミングは、募集開始から1ヶ月が目安です。1ヶ月間反応がなければ、価格設定が間違っています。そのため、早めに家賃を修正し、機会損失を最小限に抑えるべきです。
家賃を下げる代わりに、付加価値を提供する方法もあります。家賃は据え置きで、フリーレント1ヶ月、礼金ゼロ、家具家電付きなど、条件を変えることで差別化できます。
物件のリフォームを行う
リフォームは、物件の競争力を高める有効な手段です。しかし、どこまで投資すべきか、費用対効果を慎重に見極める必要があります。無計画なリフォームは、資金を浪費するだけに終わります。
水回りの改善は最優先です。キッチン、浴室、トイレは、入居者が最も重視するポイントです。古いシンクや浴槽、和式トイレは、それだけで敬遠される理由になります。
壁紙と床の張り替えは、印象を大きく変えます。黄ばんだ壁紙や傷だらけの床は、内見者に悪い印象を与えます。特に若者(ワンルーム)をターゲットした不動産物件向けになると古い外見と内見は悪影響となります。そのため壁紙や床の張り替えは好印象なイメージを与えることになります。
リフォームのタイミングは、入居者が退去した直後が最適です。空室期間中にリフォームを完了させ、すぐに募集を開始します。入居中にリフォームを計画しても、退去を待つ間に時間を浪費します。
賃貸から民泊運営にシフトする
民泊は、空室対策の選択肢として注目されています。賃貸で入居者が決まらない物件でも、民泊なら収益を上げられる可能性があります。ただし、法規制、運営負担、収益の不安定さなど、リスクも多いです。
民泊運営には、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出が必要です。年間営業日数は180日以内に制限され、消防設備の設置、近隣住民への説明など、手続きが煩雑です。無許可で営業すれば、罰金や営業停止のリスクがあります。
運営の手間は、賃貸より大幅に増えます。清掃、鍵の受け渡し、ゲスト対応、トラブル処理など、日常的な業務が発生します。代行業者に委託すれば、売上の20%〜30%を手数料として支払う必要があります。しかし、民泊運用代行を使用したとしても賃貸よりも大幅な利益の向上が見込めます。
さらに、民泊から賃貸への切り替えも可能です。民泊で収益を上げながら、並行して賃貸入居者を募集します。良い入居者が見つかれば、民泊を終了して賃貸に戻します。柔軟な運用が可能なら、民泊は有効な選択肢です。
関連:【利回り8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
まとめ
空室リスクは、不動産投資における最大の脅威です。家賃設定のミス、立地の問題、物件の劣化、競合の増加など、複数の要因が絡み合って空室は発生します。空室が続けば、ローン返済や管理費などの固定費が重くのしかかり、資金繰りは急速に悪化します。新規入居者募集のための広告費やリフォーム費用も追加で発生し、損失はさらに膨らみます。
対処法は状況によって異なります。家賃設定が高ければ、相場に合わせた値下げが必要です。物件が劣化していれば、水回りや内装のリフォームが効果的です。賃貸で行き詰まった場合、民泊への用途変更も選択肢になります。
民泊は2025年10月現在、円安とインバウンド需要の増加によって多くの収益を産むことが可能となっています。そのためおすすめします。