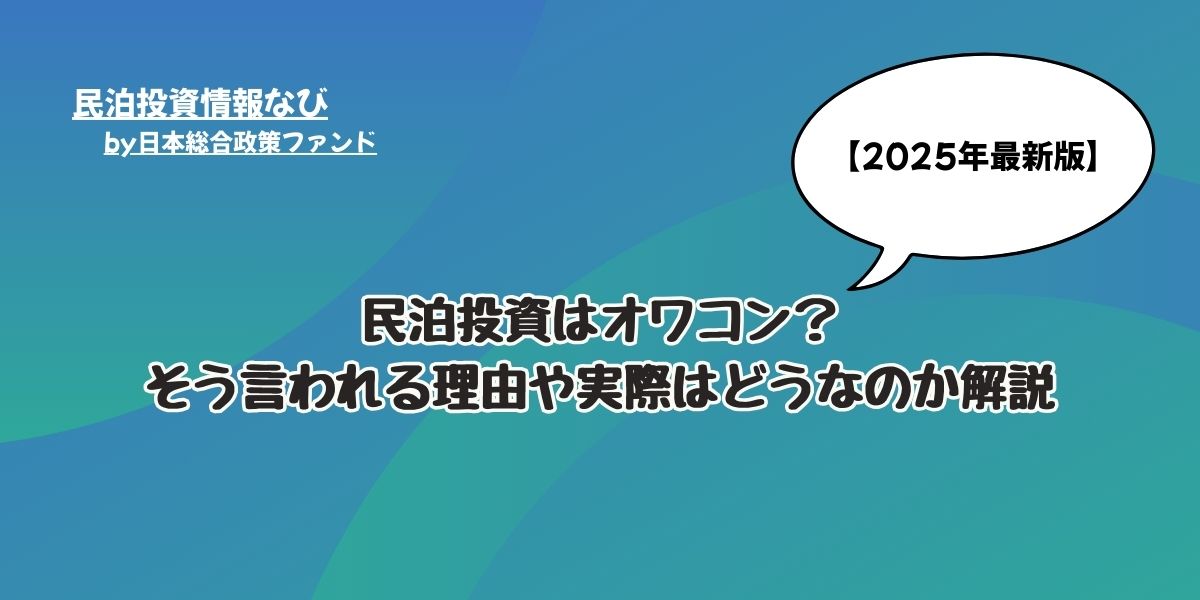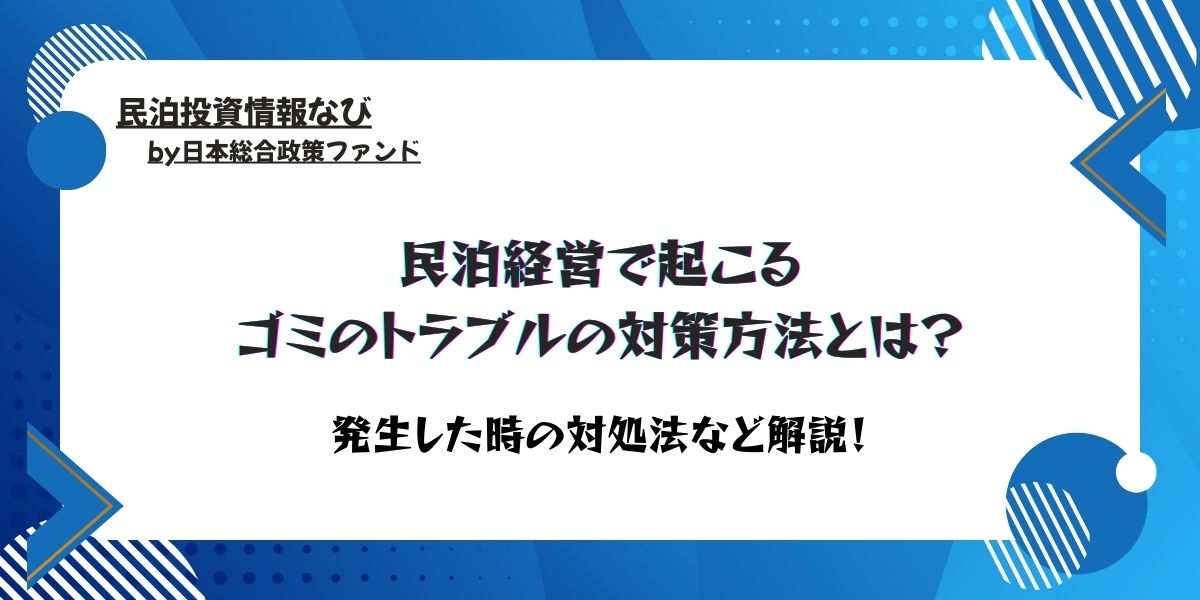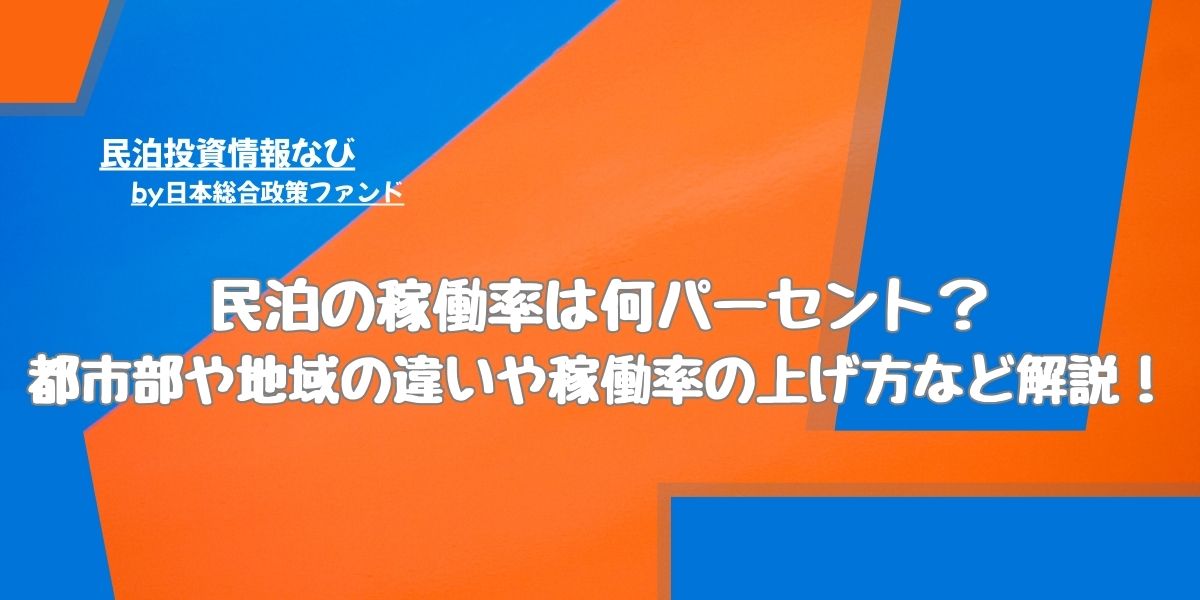「民泊はもうオワコンなの?」と不安を感じていませんか。確かに、以前のような右肩上がりの成長は落ち着き、市場は成熟期を迎えています。不動産投資として民泊事業の立ち上げを考えている方や、すでに運営中だけれど今後の見通しに不安を感じている方にとって、現在の市場状況を正確に把握することが重要です。
この記事では、「なぜ民泊はオワコンと言われるのか」「実際の2025年の民泊市場はどうなのか」「新規参入するならどのような戦略を取るべきか」について解説します。
関連:民泊市場はレットオーシャン?それでも運営を成功させるためには?
民泊投資はもうオワコン?そう言われる理由を解説

ここでは、民泊が「オワコン」と言われる背景について詳しく見ていきましょう。規制強化や市場の変化など複数の要因が絡み合っています。
民泊の供給が需要を上回る「供給過多」の状態であるため
東京都内だけでも登録民泊施設は6,000件を超え、大阪では4,000件以上が存在します。これに対して実際の稼働率は平均40%前後と低迷しています。多くの民泊物件がゲストを獲得できていない状況です。
関連:民泊市場はレットオーシャン?それでも運営を成功させるためには?
民泊に対する規制が厳しくなっているため
住宅宿泊事業者として正式に登録するためには、消防設備の設置や定期的な防火対策の実施など、さまざまな安全基準を満たす必要があります。これにより初期投資額が大幅に増加しました。
多くの自治体では独自の上乗せ規制を設けています。東京都の一部地域では、住居専用地域における民泊営業が平日のみに制限されたり、年間の営業日数が180日以下に制限されたりしています。
外国人観光客の受け入れには「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」に基づく措置も必要です。外国語対応やセキュリティ対策の強化が求められるため、運営コストが上昇します。
規制強化の影響は特に新規参入者に大きく、以前のように気軽に民泊ビジネスを始めることが難しくなっています。法令遵守のための専門知識やコンサルティング費用も必要となり、参入障壁は確実に高くなっています。
運営コストが増加しているため
清掃費については、ゲストが退去するたびに専門的な清掃が必要となります。一般的な清掃費は1回あたり5,000円〜10,000円程度ですが、繁忙期には価格が上昇する傾向があります。大型連休やイベント時期には清掃スタッフの確保が難しく、通常の1.5倍程度のコストがかかることも珍しくありません。
リネン(シーツやタオル)の交換・クリーニング費用も見逃せません。高品質なサービスを提供するためには、ホテル並みの清潔さが求められるため、プロのクリーニングサービスを利用する必要があります。
ゲスト対応の人件費も大きな負担です。チェックインやチェックアウト対応、トラブル時の緊急対応など、24時間体制での対応が求められることもあります。これらをすべてオーナー自身で行うことは現実的ではないため、管理会社に委託するケースが増えています。その場合、売上の15%〜25%程度が管理費として差し引かれることになります。
リスク分散が難しいため
通常の賃貸経営と比較すると、民泊はさまざまなリスク要因を抱えています。収入の不安定さが挙げられます。通常の賃貸住宅であれば月々安定した家賃収入が見込めますが、民泊の場合は季節変動や予約状況によって大きく収入が変動します。
国際情勢や感染症の流行など、外部要因の影響を大きく受けるのも民泊の特徴です。2020年のコロナ禍では、多くの民泊オーナーが長期間にわたり収入が途絶えるという事態に直面しました。単一の収入源に依存するリスクは非常に高いと言えます。
複数の民泊物件を所有してリスク分散を図ろうとしても、管理負担や初期投資額の大きさから、多くのオーナーにとって難しい選択となります。民泊では一物件あたりの投資額が大きいため、効果的なリスク分散が困難です。
民泊特有のトラブル(騒音問題、近隣とのトラブル、設備の破損など)に対応するためのコストや時間も無視できません。これらの問題が発生した際の対応は、オーナーにとって大きな精神的・経済的負担となります。
物件の売却が困難であるため
一般的な不動産投資では、資産価値の上昇や家賃収入の安定性を見込んで投資しますが、民泊用に改修した物件はその特殊性から売却時に苦労することが少なくありません。
民泊用に改修した物件は、一般的な居住用不動産とは内装や設備が大きく異なります。ワンルームマンションを4〜6人が宿泊できるように改装したり、玄関にデジタルロックを設置したりするなど、民泊特有の改修が施されています。こうした物件を一般の居住用として売却しようとすると、元の状態に戻すための追加コストが発生します。
民泊物件を購入する層は限定的です。一般の住宅購入者はもちろん、投資家の中でも民泊に特化した投資を行う人は減少傾向にあります。そのため、売却希望者が増える一方で買い手が減少しており、売却までの期間が長期化したり、大幅な値下げを余儀なくされたりするケースが増えています。
関連:民泊投資の出口戦略はどうするべき?どう進めるべきか紹介!
実際、2025年民泊市場はどう?

ここでは、2025年の民泊市場の現状と、期待される成長機会について詳しく見ていきましょう。大阪万博の開催や訪日外国人観光客数のさらなる増加が見込まれており、民泊市場にも新たな成長のチャンスが訪れると予測されています。
訪日観光客4000万人時代の到来
2025年には訪日外国人観光客が4000万人を超えると予測されています。インバウンド需要の回復と拡大は、民泊市場にとって大きな追い風となります。
関西万博開催によるホテルの不足→民泊の需要も上昇
2025年の大阪万博開催により、関西圏を中心にホテルの供給不足が予想されています。万博開催は、民泊が新たな顧客層を開拓し、市場を再活性化させる好機となる可能性があります。
適切な運営で高い利回りが期待できる
かつての民泊バブル期のような、100%〜200%のように非常に高い利回りを期待することは難しくなりました。しかし、適切な物件を選び、効果的な運営を行うことで、依然として高い利回りを実現できる可能性は十分にあります。
運営代行サービスを活用することで、清掃や顧客対応の負担を軽減し、効率的な運営が可能です。民泊市場は成熟期に入り、淘汰が進んでいますが、工夫次第で安定した収益と高い投資対効果が期待できる点は、依然として民泊投資の魅力と言えるでしょう。
関連:【利回り率8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
オワコンと言われているけど民泊投資は始めてもいい?

「民泊投資はもう時代遅れ」という声を聞くと、これから参入するのは不安になりますよね。確かに、以前のような爆発的な成長は期待できないかもしれません。しかし、市場が成熟し、淘汰が進んだ今だからこそ、冷静に市場を見極め、戦略的に参入することで、民泊投資で成功することも十分に可能です。
民泊投資を始めるなら民泊市場の課題を直視することが重要です。供給過多による競争激化、厳格化する法規制、上昇する運営コスト、そしてリスク分散の難しさなど、これらの課題は確かに存在します。しかし同時に、これらの課題によって市場の淘汰が進み、質の高いサービスを提供できる事業者にとっては、むしろチャンスが広がっているとも言えます。
次のポイントに注意することをお勧めします。立地選定においては、主要観光地や都心部の供給過多エリアを避け、中規模都市や地方の観光地など、まだ需給バランスが取れているエリアを検討すべきです。また、物件タイプも従来の「アパートの一室」から、一棟貸しや古民家再生など、差別化できる物件へとシフトすることが重要です。
出口戦略についても検討しておくことが大切です。民泊専用物件としての売却は難しいケースが多いため、一般居住用への転用や長期賃貸への切り替えなど、複数のシナリオを準備しておくべきでしょう。
民泊市場は厳しい面もありますが、その分、参入障壁が高まったことで、本気で取り組む事業者にとっては差別化しやすい環境が生まれています。「オワコン」という声に惑わされず、冷静な市場分析と戦略的なアプローチで、今からでも民泊投資で成功することは十分に可能です。
関連:【民泊を始めたい方必見!】民泊の始め方とは?物件選定から運営開始まで紹介!
新規に民泊を運営するならどう参入すべき?

成熟期を迎えた民泊市場で、これから新規に運営を始めるのは、ハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、参入方法を工夫することで、リスクを抑えながら民泊ビジネスをスタートできます。
ここでは、新規参入を検討している方向けに、市場動向を踏まえ、具体的な参入ステップと注意すべきポイントを解説します。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身の状況や目的に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
新規物件で民泊を始める
新規物件で民泊を始める方法には、物件を購入するケースと賃貸物件を活用するケースがあります。
物件購入の場合
物件購入による参入は、中長期的な資産形成を視野に入れた方法です。不動産価値の上昇も期待できる一方で、初期投資額が大きくなるため、資金力が必要となります。
特に注目すべきは「二次交通」の利便性です。最寄り駅から徒歩10分以内、もしくはバス停やシェアサイクルステーションが近くにあることが望ましいでしょう。周辺環境も重要で、スーパーやコンビニなどの生活施設が充実しているエリアは、ゲストの満足度向上につながります。
物件タイプとしては、差別化できる特徴を持った物件が有利です。古民家を改装した和風テイストの民泊や、デザイナーズマンションを活用したハイグレード民泊など、特色のある物件は高単価での運営が可能となります。また、一棟貸しタイプの物件は、グループ旅行や家族連れに人気があり、安定した需要が期待できます。
物件購入の際の注意点としては、民泊営業が可能か事前に確認することが不可欠です。区分所有建物(マンション)の場合、管理規約で民泊営業が禁止されているケースも多いため、必ず確認しましょう。また、消防設備の設置義務や建築基準法の規定にも留意する必要があります。
初期投資額としては、物件購入費の他に、内装工事費(100万円〜300万円程度)、家具・家電購入費(50万円〜150万円程度)、消防設備設置費(10万円〜50万円程度)などが必要となります。さらに、住宅宿泊事業者登録費用(5万円前後)も忘れてはなりません。
関連:民泊物件を購入する方法とは?手順や失敗例、見つからない場合の対処法など解説
賃貸物件の場合
賃貸物件を活用した民泊は、初期投資を抑えられるメリットがあります。物件所有者の許可を得た上で、賃貸物件を転貸する形で民泊を運営する方法です。この場合、物件購入費が不要となるため、初期投資額を大幅に削減できます。特に民泊ビジネスの経験がない方や、リスクを最小限に抑えたい方にとって、検討する価値のある選択肢です。
賃貸物件を活用する際の最大のハードルは、大家さんの許可を得ることです。民泊に理解のある大家さんを見つけることが難しい場合もありますが、民泊専用の賃貸物件や、民泊向けサブリース物件も増えてきているため、そうしたサービスの活用も検討するとよいでしょう。
賃貸物件で民泊を始める際には、契約内容をしっかりと確認することが重要です。特に転貸の可否、民泊利用の可否、契約期間、賃料改定条件などを詳細に確認しましょう。また、原状回復義務の範囲についても事前に明確にしておくことが重要です。
関連:賃貸物件で民泊を始めることができる?民泊を開始するための手順など紹介!
民泊M&A仲介を使用して民泊を始める
すでに運営されている民泊事業を買収する方法も、新規参入の選択肢として注目されています。この方法のメリットは、すでに運営実績のある事業を引き継げることで、一からの立ち上げに比べてリスクを低減できる点にあります。
民泊M&A仲介サービスを利用すれば、売却希望の民泊事業者と買収希望者をマッチングしてもらえます。近年は民泊市場の淘汰が進んでいることもあり、売却を検討する事業者が増えているため、条件の良い案件を見つけられる可能性も高まっています。
民泊事業の買収を検討する際には、以下のようなポイントをチェックすることが重要です。過去2〜3年間の収支データを詳細に確認しましょう。月別の稼働率や平均単価、運営コストの内訳などを分析することで、事業の実態を把握することができます。
物件の状態や設備の老朽化具合もしっかりとチェックする必要があります。買収後に大規模な修繕や設備更新が必要となると、追加投資が発生するため、物件の現状をできるだけ詳しく調査しましょう。
現在の運営体制や予約管理システム、清掃スタッフなどの協力業者についても確認することが重要です。民泊事業の買収価格は、年間収益の2〜3倍が一般的な相場とされていますが、物件の立地条件や収益性によって大きく変動します。
関連:民泊M&Aが注目される理由とは?市場の動向や適切な価格設定の方法など解説!
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり、改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかっていませんか。さらに、厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか。
しかし、すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
そこでおすすめするのが、日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。

日本総合政策ファンドの最大の強みは、AI/DXテクノロジーを駆使した効率的なマッチングとデューデリジェンスです。お客様の投資条件や希望に最適な民泊物件を、膨大なデータベースから迅速に見つけ出します。以下のような価値ある資産を含む物件も多数取り扱っています。
- 旅館業法または特区民泊に基づく営業許可(年間365日運営可能)
- 即戦力となる清掃スタッフなどの運営体制
- 稼働開始に必要な家具家電や内装設備一式
物件だけでなく、運営ノウハウも一緒に取得できることが最大のメリットです。成功している民泊事業の運営方法、料金設定、集客戦略などの専門知識も継承できるため、民泊事業未経験の方でも安心して参入できます。
まずは無料で日本総合政策ファンドのコンサルタントに相談してみませんか。お客様の投資条件や希望を分析し、最適な民泊物件候補をご提案します。
まとめ
民泊がオワコンと言われる背景には、供給過多、規制強化、運営コストの増加といった要因があることを解説しました。しかし、2025年には訪日観光客数の増加や大阪万博開催といった追い風も吹きます。適切な戦略で参入すれば、民泊ビジネスで成功することも十分に可能です。
新規参入の方法としては、新規物件で始める方法と、民泊M&Aを利用する方法を紹介しました。それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、ご自身に合った方法を選ぶことが重要です。
民泊市場は変化のスピードが速く、常に最新情報をキャッチアップしていく必要があります。この記事が、民泊投資を検討されている皆様にとって、冷静な判断と的確な戦略を立てるための一助となれば幸いです。