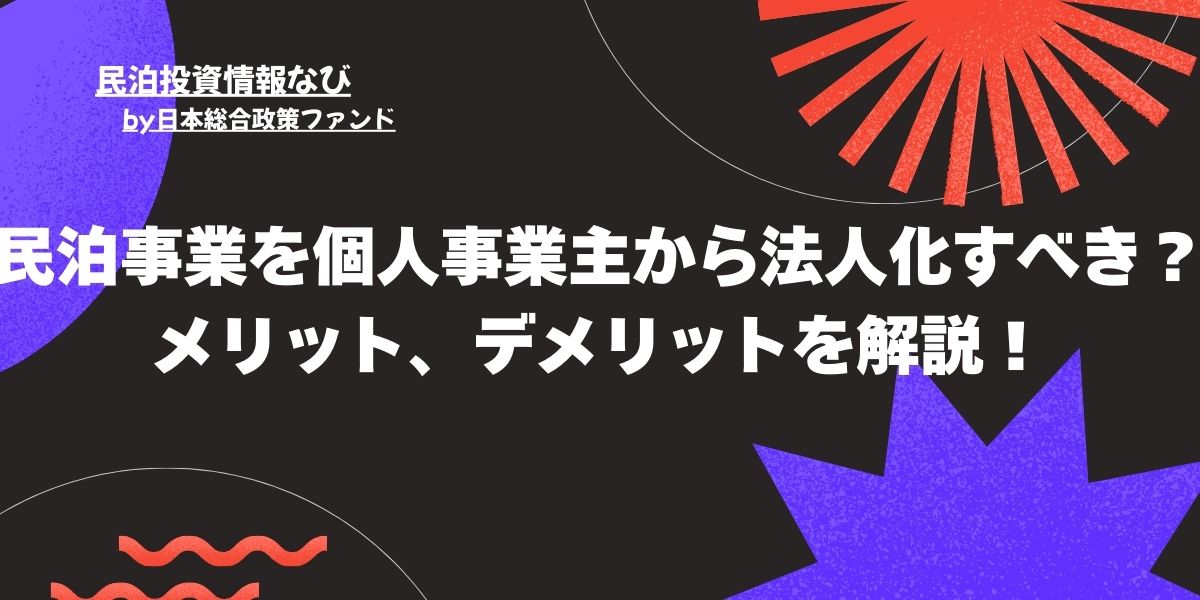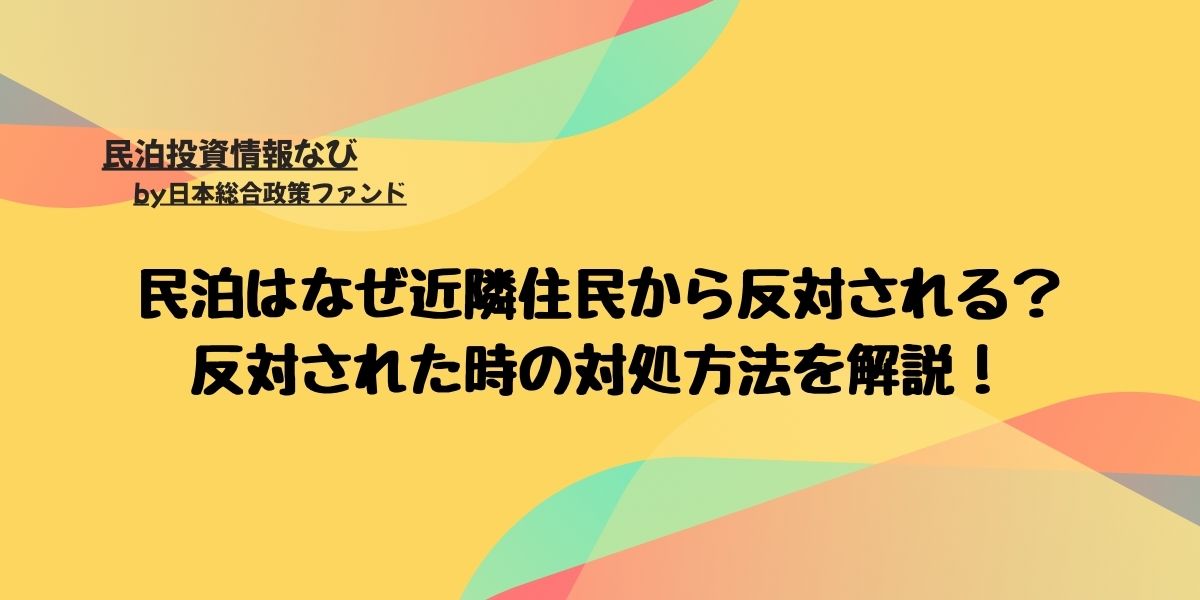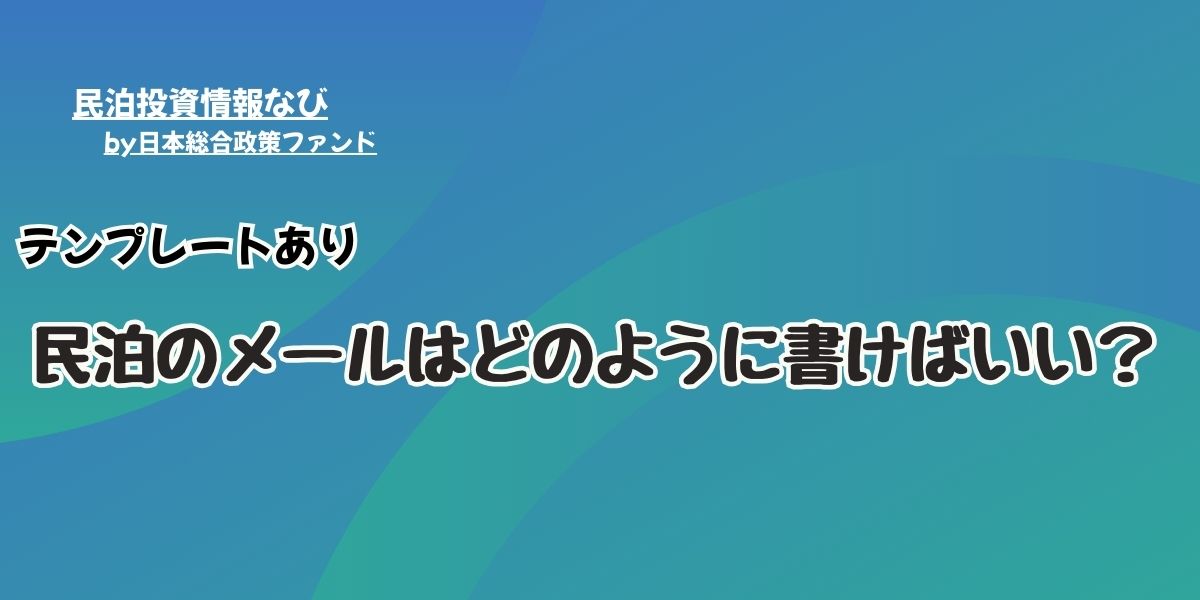民泊事業を始めて軌道に乗り始めたオーナーの方なら、「そろそろ法人化すべきだろうか」と悩んでいることでしょう。
法人化には節税効果や社会的信用の向上といったメリットがある一方で、設立・維持コストの負担や事務手続きの複雑化などのデメリットも存在します。
本記事では、民泊事業の法人化におけるメリット・デメリット、法人化が向いているケース、そして最適な法人形態の選び方まで、詳しく解説します。
民泊事業を法人化するメリットとは?

法人化には様々なメリットがありますが、民泊事業特有の観点からも検討する必要があります。
ここでは民泊事業を法人化することで得られる具体的なメリットについてみていきましょう。
節税効果が期待できる
民泊事業を法人化する最も大きなメリットの一つが節税効果です。個人事業の場合、所得税は累進課税制度が適用されるため、収入が増えるほど税率が上がっていきます。最大で45%もの税率になることもあるのです。
一方、法人の場合は法人税率が一律で適用されます。年間所得800万円以下の中小企業であれば、法人税率は15%と低く抑えられています。特に民泊事業で複数の物件を運営し、年間利益が増えてきた場合には、この税率の差が大きな節税につながります。
また、役員報酬を調整することで、個人と法人の課税バランスを最適化できる点も見逃せません。例えば、法人の利益から適切な額を役員報酬として支払うことで、法人税と所得税の合計負担を最小化できる可能性があります。
関連:【最終利益に大幅な差が】民泊経営で節税することはできる?詳しく解説!
社会的信用の向上により契約や融資が受けやすくなる
法人化することで社会的信用が高まり、様々な場面で有利になります。特に民泊事業では物件の契約や金融機関からの融資を受ける機会が多いため、この信用力の差は非常に重要です。
まず、物件のオーナーや不動産会社との交渉において、個人事業主よりも法人の方が信頼性が高いと判断されることが多いです。特に民泊用途での物件契約は通常の賃貸契約より審査が厳しいことが多いのですが、法人であれば「事業として真剣に取り組んでいる」という印象を与えやすく、契約成立の可能性が高まります。
また、事業拡大のために融資を受ける際も、法人の方が有利です。銀行や金融機関は、個人事業主よりも法人に対して融資を行う傾向があります。これは法人の方が財務状況が明確で、事業継続性も高いと判断されるためです。民泊事業は物件数を増やすごとに初期投資が必要になるため、この融資のしやすさは大きなメリットといえるでしょう。
関連:民泊を始める資金はいくら必要?融資をうけることは可能?
経費計上の幅が広がることにより事業運営の柔軟性が増す
法人化することで経費として認められる範囲が広がり、事業運営の柔軟性が大きく向上します。個人事業主の場合、経費計上できる項目に制限がありますが、法人ではより幅広い支出を経費として計上できるのです。
民泊事業では物件の内装や家具、アメニティなどの購入費用が発生しますが、法人であればこれらをすべて経費として計上できます。また、清掃スタッフや管理スタッフの人件費も明確に経費計上できるため、人材を雇いやすくなります。
事業規模の拡大が促進される
法人化することで、民泊事業の規模拡大がスムーズになります。個人事業では資金調達や人材確保に限界がありますが、法人化によりこれらの制約を大きく緩和できるのです。
まず、前述した融資の受けやすさにより、複数物件の同時取得や高級物件への投資など、大規模な事業展開が可能になります。民泊市場は競争が激しくなっているため、この資金力の差は競争優位性につながります。
また、従業員の雇用もしやすくなります。法人であれば雇用保険や社会保険の整備、給与体系の確立など、安定した雇用環境を提供できます。民泊事業は清掃やゲスト対応など人手が必要な業務が多いため、優秀な人材を確保できるかどうかが成功の鍵を握っています。
さらに、法人として明確な組織体制を構築することで、オーナー自身の負担を減らしながら事業を拡大できます。例えば、物件管理、予約管理、ゲスト対応などの業務を分担し、効率的な運営体制を築けるのです。民泊事業は24時間365日の対応が求められるため、この運営効率化は非常に重要です。
株式譲渡などで事業をスムーズに他社へ引き継げる
法人化しておくことで、将来的な事業承継や売却がスムーズになります。個人事業の場合、事業譲渡は複雑な手続きが必要ですが、法人であれば株式譲渡という形で比較的簡単に事業を引き継ぐことができるのです。
民泊事業は物件や設備、運営ノウハウなど多くの資産を持つため、これらをまとめて譲渡できることは大きなメリットです。特に複数物件を運営している場合、個別に譲渡するよりも法人ごと売却する方が効率的で、より高い評価額を得られる可能性があります。
さらに、相続対策としても有効です。個人事業の場合、相続時に物件ごとに相続手続きが必要になりますが、法人であれば株式の相続だけで済むため、手続きが簡素化されます。長期的な事業継続を考える上で、この点も重要なメリットといえるでしょう。
関連:民泊M&Aとは?物件譲渡などの手法やメリット、デメリットなど解説!
顧客に対してプロフェッショナルな印象を与えられる
法人として民泊事業を運営することで、顧客に対してより専門的で信頼できる印象を与えることができます。これは特に海外からの宿泊客が多い民泊事業において無視できない重要なメリットです。
まず、法人名での運営により、個人経営よりも「プロフェッショナルな宿泊施設」という印象を与えられます。
また、法人としての公式ウェブサイトや予約システムを整備することで、よりプロフェッショナルなサービス提供が可能になります。個人運営では限界があるシステム投資も、法人であれば経費として計上できるため、積極的に取り組めます。
さらに、複数物件を同一ブランドで展開することで、リピーター獲得や知名度向上にもつながります。法人として一貫したサービス品質やブランドイメージを確立することは、長期的な事業成功の鍵となるでしょう。
加えて、観光庁や自治体による「優良民泊事業者」認定なども、法人の方が取得しやすい傾向があります。これらの公的認証は顧客からの信頼獲得に大きく貢献するため、積極的に取得を目指したいところです。
民泊事業を法人化するデメリットは何?

民泊事業の法人化には多くのメリットがありますが、同時に見過ごせないデメリットも存在します。
ここでは法人化によって生じる具体的なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
法人設立にかかる初期費用が必要になる
法人を設立するには、個人事業主として始める場合と比べて相当な初期費用と時間がかかります。この初期投資は民泊事業の資金計画に大きな影響を与える可能性があるため、十分に考慮する必要があります。
まず、法人設立には登録免許税が必要です。株式会社の場合は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社の場合は6万円の登録免許税が課されます。
さらに、法務局への登記申請手数料、印鑑証明書の取得費用、法人印の作成費用なども発生します。また、専門家に依頼する場合は、司法書士や行政書士への報酬も必要になります。
毎年発生する法人住民税や社会保険料などコストが発生する
赤字でも税金を払う必要がある
個人事業主と比較して、法人の場合は赤字であっても一定の税金を支払わなければならないという点は大きなデメリットです。これは特に民泊事業のような季節変動が大きい事業において重要な考慮点となります。
前述したように、法人住民税の均等割部分は利益の有無に関わらず課税されます。さらに、法人事業税の一部も所得に関係なく課税される場合があります。これらの税金は、例え民泊事業が赤字であっても免除されることはないのです。
また、法人には消費税の納税義務が生じやすいという点も見逃せません。個人事業主の場合、前々年の売上が1,000万円以下であれば消費税の納税が免除されますが、法人の場合は設立から2年間の免税期間を過ぎると、規模の小さい事業でも消費税の納税が必要になります。民泊事業では設備投資や修繕費などの支出が多いため、売上に対する消費税負担は無視できない金額になることがあります。
さらに、損益通算の面でも法人は不利になる場合があります。個人事業主であれば、複数の事業や給与所得、不動産所得などを合算して所得税を計算できますが、法人の場合はそれぞれの法人ごとに計算する必要があります。
個人事業主に比べて会計処理が複雑になる
法人として民泊事業を運営する場合、会計処理の複雑さは避けられないデメリットです。個人事業主の場合は比較的簡易な帳簿記録で済むことが多いですが、法人では正規の複式簿記による会計処理が求められます。
法人の場合、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書などの財務諸表を作成する必要があります。また、各種税務申告書類も複雑になり、法人税や法人住民税、事業税、消費税などの申告・納付が必要です。
また、法人では会計ソフトの導入が事実上必須となり、日々の取引記録も細かく正確に行う必要があります。民泊事業では宿泊料金の入金や備品購入、清掃費用の支払いなど多くの取引が発生するため、これらの記録を適切に管理するための時間と労力が必要になります。
さらに、法人では株主総会や取締役会などの開催と議事録の作成も必要です。特に株式会社の場合、年に一度の定時株主総会は法的に義務付けられています。これらの手続きも、個人事業主にはない追加の事務負担となります。
個人事業主よりも利益配分の柔軟性が低下する
法人化することで、利益の使い方や配分に関する柔軟性が低下することも重要なデメリットです。個人事業主の場合、事業で得た利益は全て自分のものとして自由に使うことができますが、法人の場合は様々な制約があります。
まず、法人の利益を個人的に使用するためには、役員報酬や配当といった形式を取る必要があります。役員報酬は事前に決定した金額を定期的に支払うもので、業績に応じて随時変更することは税務上難しいとされています。また、配当も株主総会の決議が必要であり、手続き面での制約があります。
このような制約は、特に民泊事業のような収益の変動が大きい事業において不便に感じることがあります。
また、法人から個人への資金移動は厳格に管理されており、不適切な方法で行うと「役員借入金」や「貸付金」として処理され、後々税務上の問題を引き起こす可能性があります。
法人解散に清算手続きが必要になる
将来的に民泊事業を終了する際、個人事業の場合は比較的簡単に廃業できますが、法人の場合は複雑な清算手続きが必要になります。この点は長期的な事業計画を立てる上で考慮すべき重要なデメリットです。
法人を解散する場合、
①解散決議
②官報公告
③債権者保護手続き
④清算結了登記 など、複数のステップを踏む必要があります。
また、法人を清算する際には、残余財産の分配に対して課税される場合があります。法人内に蓄積された利益剰余金が多い場合、これらを分配する際に追加の税負担が生じる可能性があるのです。
さらに、清算中も法人住民税の均等割部分は課税され続けるため、清算期間が長引くほどコストが増加します。民泊事業の場合、物件の売却や賃貸借契約の解約など、清算に時間がかかるケースも少なくないため、この点も考慮する必要があります。
関連:民泊から撤退したい、やめたい場合どう手続きをすればいい?
民泊法人化が向いているケースとは?

民泊事業の法人化はすべての民泊オーナーに適しているわけではありません。特定の条件や状況にあるオーナーにとっては法人化のメリットが大きく、他のケースでは個人事業主のままでいる方が有利な場合もあります。
ここでは、民泊事業の法人化が特に適している具体的なケースについて見ていきましょう。
事業規模が大きい場合
また、規模が大きくなるほど、経費の種類や金額も増えてきます。民泊事業では、清掃費、備品費、リネン交換費、修繕費など様々な経費が発生しますが、法人の方が経費計上の幅が広く、より多くの項目を経費として認めてもらいやすいという特徴があります。
さらに、規模が大きくなると在庫管理や資産管理も重要になります。法人化することで、これらの管理が明確になり、会計上も適切に処理できるようになります。特に民泊事業では、タオルやアメニティなどの在庫や、家具・家電などの資産管理が重要ですが、法人化によってこれらの管理が体系化されるメリットは大きいでしょう。
従業員を雇用する場合
民泊事業を拡大していく過程で従業員を雇用する必要が出てきた場合、法人化は非常に有効な選択肢となります。従業員の雇用に関しては、法人と個人事業主では様々な違いがあり、法人の方が多くの面で有利になるのです。
まず、社会的信用の面で法人の方が従業員を採用しやすくなります。特に優秀な人材を採用する際、個人事業主よりも法人の方が安定性や将来性を感じさせるため、採用活動がスムーズに進むことが多いです。
次に、社会保険や福利厚生の面でも法人の方が整備しやすくなります。法人であれば社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することで、従業員の福利厚生を充実させることができます。また、退職金制度や社宅制度なども導入しやすくなります。
融資や投資を受けたい場合
民泊事業の拡大には物件取得や設備投資など多額の資金が必要になることが多く、融資や投資を活用したい場合には法人化が大きなアドバンテージとなります。
投資を受ける観点でも法人化は有利です。個人事業主の場合、出資を受ける仕組みが限られていますが、法人であれば株式発行や第三者割当増資など、様々な方法で資金調達が可能になります。例えば、将来的にはビジネスパートナーに一部出資してもらい、共同経営者として迎え入れることも容易になります。
また、法人化することで、資本政策の設計も可能になります。例えば、議決権のある株式とない株式を使い分けることで、経営権を維持しながら資金調達を行うといった高度な戦略も取れるようになります。民泊事業を大規模に展開する場合、このような柔軟な資本政策は非常に有効です。
さらに、補助金や助成金の面でも法人の方が有利なケースが多いです。観光振興や地域活性化に関連する補助金の中には、法人を対象としたものが多く、個人事業主は対象外となっているものもあります。特に地方での民泊事業展開を考える場合、こうした補助金の活用は重要な資金源となります。
リスクを限定したい場合
民泊事業には様々なリスクが伴います。物件の損傷、事故やトラブル、契約不履行など、予期せぬ問題が発生する可能性は常にあります。法人化はこれらのリスクから個人資産を守るための有効な手段となります。
最も重要なのは有限責任の原則です。株式会社や合同会社などの法人格を取得することで、事業の負債やトラブルが発生した場合でも、原則として出資額以上の責任を負わなくて済みます。つまり、民泊事業で大きな損失が出たり、訴訟などのトラブルに発展したりしても、個人の財産に影響が及ばない仕組みになっています。
具体的な例を挙げると、民泊施設での火災や水漏れなどが発生し、建物や隣接する物件に大きな損害を与えてしまった場合、個人事業主であれば個人資産(自宅や預金など)までが賠償の対象となる可能性がありますが、法人であれば基本的に法人の資産内で責任が限定されます。
民泊事業を長期的に継続していく上で、このようなリスク管理は非常に重要です。特に以下のような状況にある場合は、リスク管理の観点から法人化を積極的に検討すべきでしょう。
- 高額な物件(1億円以上など)を運営している場合
- 外国人観光客の比率が高く、文化や習慣の違いからトラブルが発生しやすい場合
- 複数のスタッフを雇用しており、労務トラブルの可能性がある場合
- 事業規模が大きく、契約関係も複雑になっている場合
リスク管理は事業が順調な時こそ重要です。問題が発生してからでは遅いケースも多いため、事業拡大に合わせて早めに法人化を検討することをお勧めします。
民泊事業の法人化に適した形態

民泊事業を法人化する際に、最も重要な選択の一つが法人形態の決定です。日本では主に「株式会社」と「合同会社」の二つの形態が一般的に選ばれています。それぞれに特徴があり、民泊事業の規模や将来計画、運営方針によって最適な選択肢は異なります。
ここでは、民泊事業に適した法人形態について、それぞれのメリット・デメリットを詳細に解説します。
株式会社
株式会社は最も一般的な法人形態です。
株式会社の最大の特徴は社会的信用の高さです。取引先や金融機関、物件オーナーなどに対して、「株式会社」という名称自体が信頼感を与えます。特に民泊事業では物件契約や清掃サービスの発注など、様々な取引が発生するため、この信用力は大きなメリットになります。
資金調達の柔軟性も株式会社の大きなメリットです。株式発行による資金調達が可能であり、将来的な事業拡大時に投資家から資金を集めやすい構造になっています。民泊事業を10棟、20棟と拡大していく計画がある場合、この資金調達の容易さは非常に重要です。さらに、銀行融資においても株式会社は有利に働くことが多く、物件取得のための融資も受けやすくなります。
さらに、事業承継や売却の容易さも株式会社の利点です。株式の譲渡によって所有権を移転できるため、将来的に事業を第三者に売却する際もスムーズに進めることができます。民泊事業で複数の物件を運営している場合、個別に物件を売却するよりも法人ごと売却する方が効率的で、より高い評価額を得られる可能性が高いです。
一方で、株式会社にはいくつかのデメリットも存在します。まず、設立コストが比較的高いという点があります。また、維持コストも高く、決算公告や株主総会の開催などの法的義務が生じます。民泊事業の規模が小さい段階では、これらのコストや手続きが負担に感じられることもあるでしょう。
また、情報公開の義務も株式会社の特徴です。登記事項は誰でも閲覧可能であり、役員の氏名や住所(都道府県まで)、資本金額などが公開されます。プライバシーを重視する場合には、この点がデメリットになる可能性があります。
税制面では、株式会社と合同会社に大きな違いはありませんが、繰越欠損金の期間が最長10年と定められている点は覚えておく必要があります。
株式会社を選ぶべき具体的なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
- 複数の投資家から資金を集めて事業を拡大する計画がある
- 将来的に企業売却を視野に入れている
- 高級物件を中心に展開し、社会的信用が特に重要
- 従業員を多く雇用し、組織的な運営を行う予定
- 複数の事業部門(例:民泊運営と清掃サービス提供)を持つ計画がある
株式会社は手続きやコストの面ではやや煩雑ですが、社会的信用の高さと将来的な拡大可能性を重視する場合に最適な選択肢といえるでしょう。
合同会社
合同会社は、簡易な手続きと柔軟な運営が特徴で、特に少人数での経営や小規模からのスタートを考えている場合に適しています。
合同会社の最大のメリットは設立の容易さとコストの低さです。定款認証が不要であるため公証人手数料(約5万円)がかからず、登録免許税も6万円と株式会社より低額です。
さらに、運営面での簡便さも特筆すべき点です。株式会社で義務付けられている株主総会や取締役会などの機関設置が不要で、決算公告の義務もありません。
税務面では、基本的に株式会社と同様の税制が適用されるため、法人税率などは変わりません。ただし、出資者と経営者が同一である「同族会社」としての取り扱いを受けやすく、これにより役員報酬の調整などを通じた節税が行いやすいという特徴があります。
一方で、合同会社にもいくつかのデメリットが存在します。最も大きな点は社会的信用度の問題です。日本では株式会社に比べて合同会社の認知度や理解度が低く、取引先や金融機関からの信用を得にくい場合があります。
また、資金調達の制限も考慮すべき点です。合同会社では株式発行による資金調達ができないため、大規模な資金調達が必要になった場合に制約を受ける可能性があります。基本的には出資者(社員)からの追加出資や金融機関からの借入に頼ることになります。
将来的に株式会社への組織変更が可能ではあるものの、手続きに一定のコストと手間がかかる点も考慮しておくべきでしょう。
合同会社を選ぶべき具体的なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。
- 少人数(1~3人程度)での経営を予定している
- 初期投資を抑えて小規模からスタートする計画
- 事務手続きの簡素化を重視している
- 物件数が少なく(1~3棟程度)、当面は小規模経営を続ける予定
- 出資者間での柔軟な利益分配を行いたい
- 個人的なプライバシーをある程度保護したい
合同会社は、小規模でありながらも法人格を持ち、有限責任の恩恵を受けられるバランスの良い選択肢です。特に民泊事業を副業として始める場合や、小規模からスタートして様子を見ながら拡大を検討したい場合に適していると言えるでしょう。
まとめ
民泊事業の法人化は、節税効果や社会的信用の向上、経費計上の幅の広がり、事業規模の拡大のしやすさなど、多くのメリットがあります。一方で、設立コストや維持費用の負担、会計処理の複雑化、赤字でも発生する税金など、考慮すべきデメリットも存在します。
法人化が特に向いているのは、複数物件を運営している場合や従業員を雇用する場合、融資を受けて事業拡大を目指す場合、個人資産へのリスクを限定したい場合です。
また、法人形態の選択においては、社会的信用や資金調達のしやすさを重視するなら株式会社、設立・運営コストの低さや手続きの簡便さを優先するなら合同会社が適しています。