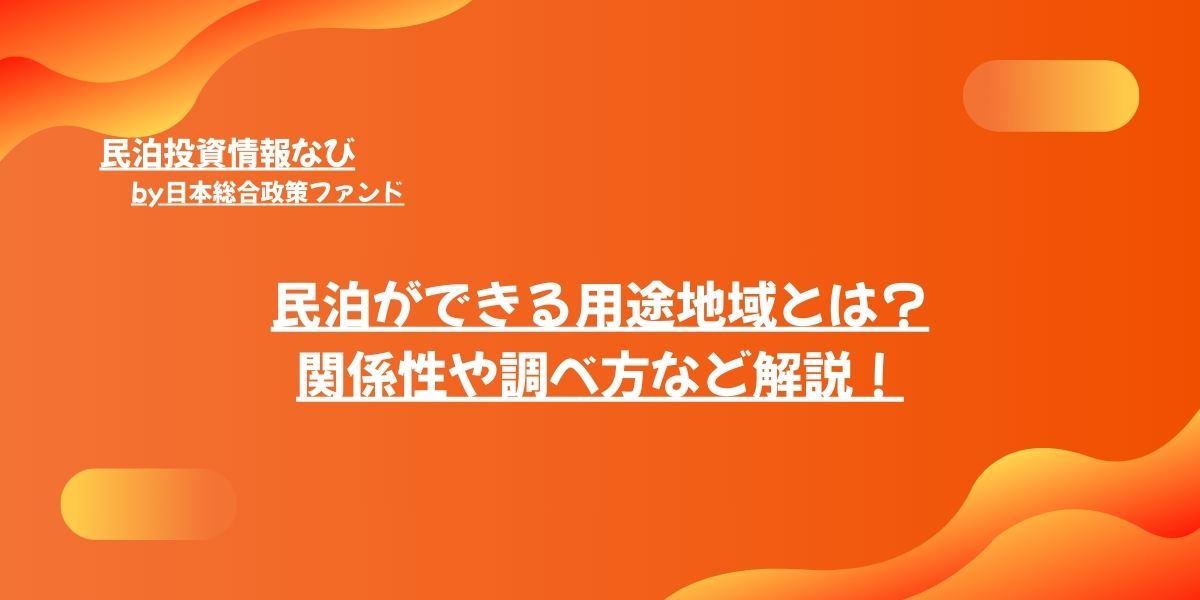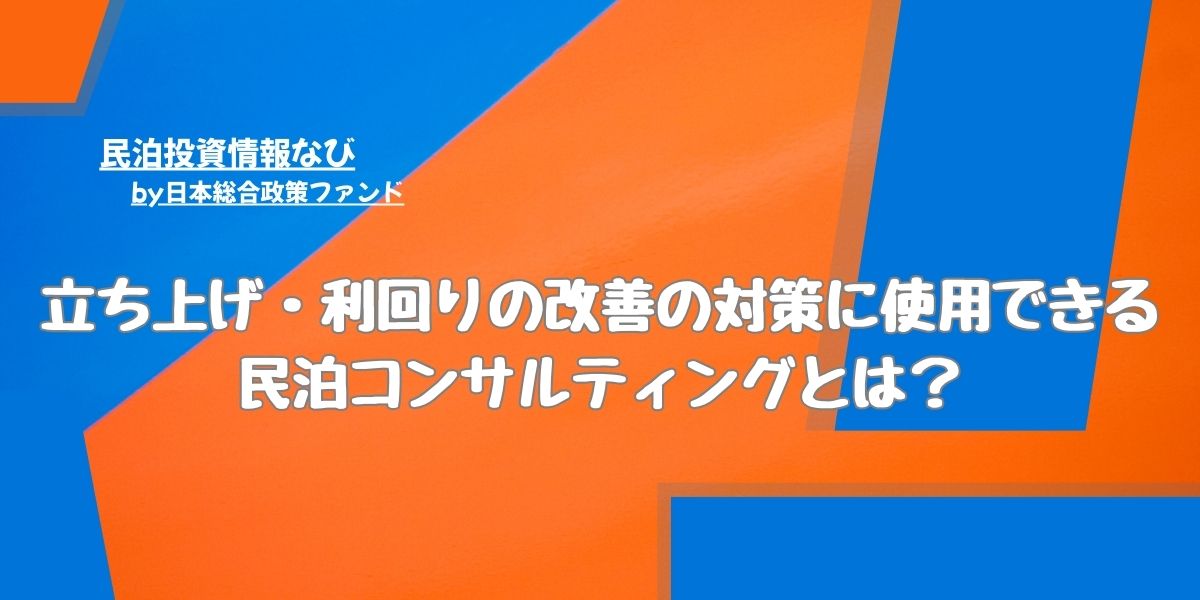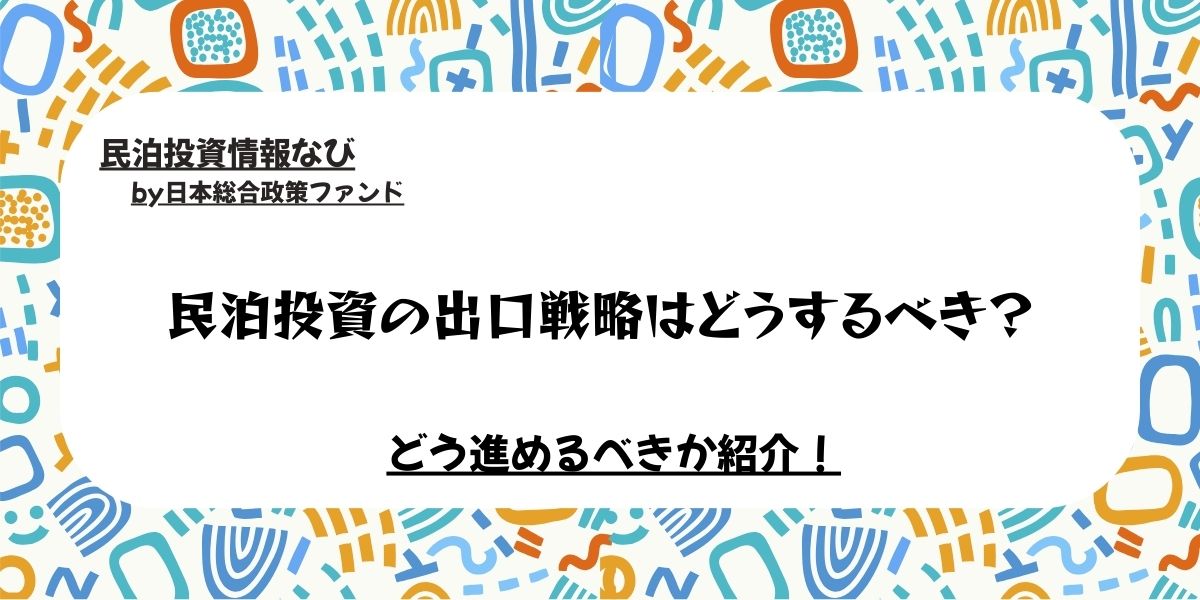民泊事業を始めようとしている方の中には、物件は見つけたものの、「この場所で本当に民泊を営業できるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。実は、「用途地域」によっては民泊を営業できないこともあり、用途地域の確認は民泊事業の成否を左右する重要なポイントです。
用途地域とは、都市計画法に基づいて定められた土地利用のルールで、全部で13種類あります。用途地域によって、どのような建物が建てられるか、どのような事業が営業できるかが決まります。民泊事業の場合も、用途地域によって営業の可否が大きく変わります。
実際に用途地域を確認せずに営業を始めてしまった場合、営業停止や罰金といった厳しい処分を受けることもあります。マンションなどの区分所有建物では、区分所有法に基づく競売請求により、所有している不動産自体を失うリスクもあります。
本記事では、不動産投資や副業として民泊事業に関心をお持ちの方に向けて、用途地域制度の基本から、民泊との関係性、違反した場合のリスク、そして確実な調べ方まで、詳しく解説します。
用途地域とは?

ここでは、用途地域の基本から見ていきましょう。
民泊事業を始めようと考えたとき、まず壁となるのが「用途地域」という言葉です。この言葉を初めて耳にする方も少なくないでしょう。しかし、民泊経営において用途地域の理解は避けて通れない重要なポイントです。
用途地域制度の目的
用途地域制度は、都市計画法第8条に基づいて定められた土地利用のルールです。この制度が導入されている理由は、街の秩序を守り、住環境を保護するためです。
私たちの暮らす街には、静かに住みたい人、商売をしたい人、工場を経営したい人など、様々な目的を持った人が共存しています。もし何の規制もなければ、住宅街の真ん中に突然大きな工場が建設されるかもしれません。そうなると、騒音や排気ガスなどで周辺住民の生活環境が悪化してしまいます。
用途地域制度は、このような問題を防ぐために「この地域ではこのような建物が建てられる」というルールを明確にしています。都市計画法第9条では、用途地域は「住居の環境を保護するため定める地域」「商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」「工業の利便を増進するため定める地域」などに分類されると定められています。
また、用途地域制度には環境保護の側面もあります。良好な住環境や自然環境を守るために、建物の高さや敷地面積に対する建築物の割合(建ぺい率・容積率)などが制限されています。
用途地域の種類と特徴についての違い

用途地域は全部で13種類あり、それぞれの地域によって建てられる建物や営業できる事業が細かく定められています。民泊事業を始める際には、物件がどの用途地域に分類されているかを必ず確認する必要があります。
用途地域は大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分けられており、それぞれの特性と民泊事業への影響を理解しておきましょう。
住居系
住居系の用途地域は、主に住宅が建ち並ぶエリアを保護するために設けられています。住居系は全部で7種類あり、第一種低層住居専用地域から準住居地域まで、住環境の保護レベルに応じて段階的に分かれています。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は、最も住環境が守られるべき地域です。この地域では、基本的に戸建て住宅やマンションなどの住居系建築物しか建てられません。民泊に関しては、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく住宅宿泊事業は条件付きで可能ですが、旅館業法に基づく簡易宿所は原則として営業できません。
第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域になると、住環境保護の制限が少し緩和されます。そのため、中高層マンションが建築可能で、一部の店舗やオフィスも認められるようになります。民泊については、住宅宿泊事業は可能ですが、旅館業としての営業は依然として制限されています。
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、さらに制限が緩和され、一定規模までの店舗や事務所、ホテルなどが建設可能になります。特に準住居地域では、自動車関連施設や小規模な工場なども建てられるようになるため、民泊事業においても旅館業法に基づく営業が可能になるケースが増えてきます。
住居系地域で民泊を始める場合、周辺住民とのトラブルが発生しやすいため、騒音対策や利用者へのマナー徹底など、より慎重な運営が求められます。特に、第一種低層住居専用地域のような静かな住宅街では、周辺住民からの苦情が発生しやすいことを念頭に置いておきましょう。
商業系
商業系の用途地域は、店舗やオフィスなどの商業施設が集まるエリアを想定しています。商業系は近隣商業地域、商業地域の2種類に分かれています。
近隣商業地域は、主に地域住民の日常的な買い物の場として機能するエリアです。スーパーマーケットやドラッグストア、飲食店など、生活に密着した店舗が集まっています。この地域では住宅も建てられるため、住宅と商業施設が混在しているのが特徴です。そのため、民泊事業については、住宅宿泊事業はもちろん、旅館業法に基づく簡易宿所やホテル・旅館の営業も基本的に可能です。
商業地域は、最も商業活動が盛んな地域で、大型の店舗やオフィスビル、娯楽施設などが集中しています。こちらも住宅の建設は可能ですが、にぎやかな環境のため住居としての快適性は下がる場合があります。民泊事業に関しては、ほぼすべての形態での営業が可能で、最も自由度の高い地域といえるでしょう。
商業系地域で民泊を運営する場合、周辺に様々な店舗があるため、利用者の利便性が高いというメリットがあります。観光客が飲食や買い物を楽しめる環境が整っているため、高い集客が期待できます。ただし、商業地域は物件価格や賃料が高くなる傾向があるため、投資判断の際には収益性をしっかり計算することが重要です。
工業系
工業系の用途地域は、主に工場や倉庫などの生産・流通施設を集めるエリアです。工業系は準工業地域、工業地域、工業専用地域の3種類に分かれています。
準工業地域は、軽工業の工場と住宅が混在する地域です。住宅や店舗、事務所などもある程度建てられるため、様々な用途の建物が混在しているのが特徴です。民泊事業については、住宅宿泊事業も旅館業法に基づく営業も基本的に可能です。工場などによる騒音や臭いがある場合もあるため、物件選びには注意が必要です。
工業地域になると、環境を悪化させるおそれのない工場の建設が可能になります。住宅や店舗も建てられますが、工場が集まる環境のため、住環境としては厳しい場合があります。民泊事業は法的には可能ですが、観光客にとって魅力的な立地とは言えないケースが多いでしょう。
工業専用地域は、工場の操業環境を保護するための地域で、住宅や店舗、ホテルなどの建設は原則として認められていません。したがって、民泊事業を行うことはできません。
工業系地域で民泊を検討する場合、準工業地域が最も現実的な選択肢となります。交通アクセスが良い場合や、ビジネス目的の宿泊需要が見込める場合には、ビジネス客向けの宿泊施設として特化させる戦略も考えられます。
民泊と用途地域の関係とは?

民泊事業を始める際、用途地域の制限を理解することは非常に重要です。用途地域によって民泊事業の可否が決まるだけでなく、どの法律に基づいて営業するかによっても制限が異なります。
民泊事業には大きく分けて「旅館業法に基づく営業」「住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく営業」「国家戦略特区における特区民泊」の3つの形態があり、それぞれ用途地域との関係性が異なります。主な内容は以下の通りです。
- 旅館業法の場合
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)の場合
- 特区民泊の場合
- その他:自治体による独自の民泊規制
それぞれの関係性について詳しく見ていきましょう。
旅館業法の場合
旅館業法は従来からあるホテルや旅館、簡易宿所などの宿泊施設を規制する法律です。民泊を旅館業法で運営する場合、主に「簡易宿所営業」として許可を取得することになります。簡易宿所は、宿泊する場所を多人数で共用する比較的簡易な構造の宿泊施設を指します。
旅館業法での営業は、用途地域による制限が厳しくなっています。特に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では、原則として旅館業の営業が認められていません。これらの地域で旅館業を営業するためには、建築基準法の用途変更が必要になりますが、住居専用地域では基本的に変更が認められないため、実質的に営業ができないと考えておく必要があります。
一方、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では一定の条件を満たせば旅館業の営業が可能になります。例えば、延べ面積3,000㎡以下のホテル・旅館であれば営業が認められます。そして、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域では、規模に関わらず旅館業の営業が可能です。工業専用地域では旅館業の営業はできません。
旅館業法での営業は、365日営業できる点や宿泊人数の制限がない点がメリットです。しかし、施設基準が厳しく、専用の玄関や宿泊者名簿の備え付け、フロントの設置など、多くの要件を満たす必要があります。このため、一般的な住宅をそのまま簡易宿所として使用することは難しく、改修工事が必要になるケースが多いです。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の場合
民泊新法の最大の特徴は、用途地域による制限が旅館業法に比べて緩やかである点です。原則として、すべての用途地域で営業が可能です。これは、住宅を住宅のまま運用することを前提としているためです。つまり、第一種低層住居専用地域のような住環境保護が厳しい地域でも、住宅宿泊事業として民泊を営業することができます。
ただし、民泊新法には独自の制限もあります。最も大きな制限は、年間提供日数が180日(泊)までという上限です。これは、住宅としての機能を守るための措置です。また、住宅宿泊事業を行う場合は、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の市長)への届出が必要です。
さらに、住宅宿泊事業を行う際には、宿泊者の衛生の確保、騒音防止のための説明、宿泊者名簿の作成と保存、外国人宿泊者の旅券の写しの保存といった管理義務が課されます。これらの義務を果たすために、自ら管理するか、住宅宿泊管理業者に委託するかを選択することになります。
民泊新法での営業は、一般住宅をそのまま活用できる点や、届出制であるため許可を取るよりもハードルが低い点がメリットです。しかし、年間営業日数の制限があるため、事業計画を立てる際にはこの点を考慮する必要があります。
特区民泊の場合
特区民泊の大きな特徴は、旅館業法の適用除外となることです。つまり、旅館業法の厳しい施設基準を満たさなくても、一定の要件を満たせば宿泊サービスを提供できます。現在、特区民泊の制度を導入している地域は東京都大田区、大阪府全域、大阪市、北九州市などがあります。
特区民泊と用途地域の関係については、基本的に住居系の用途地域を含むすべての用途地域で営業が可能です。ただし、自治体によって追加の条件が設けられている場合があります。例えば、東京都大田区では「住居専用地域であっても可能」としている一方、大阪市では「住居専用地域では不可」という制限を設けています。
特区民泊の要件としては、滞在期間が2泊3日以上であること(法令上は「6泊7日以上」とされていましたが緩和される傾向にあります)、居室面積が25㎡以上であること、専用のトイレ・浴室・洗面設備が設置されていることなどが挙げられます。また、特区民泊を営業するためには、自治体の長(区長や市長など)の認定を受ける必要があります。
特区民泊は、年間営業日数の制限がない点や、旅館業法よりも施設基準が緩い点がメリットです。しかし、特区という限られた地域でしか実施できない点や、滞在期間に下限が設けられている点は制約となります。
その他:自治体による独自の民泊規制
民泊に関する法制度は国レベルで整備されていますが、各自治体が条例によって独自の上乗せ規制を設けることも可能です。これらの独自規制は、用途地域による制限とは別に、さらに民泊事業を制限する要素となります。
例えば、京都市では「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」により、住居専用地域等では週末(金・土・日曜日)と祝日の前日のみ民泊営業を認めるという独自規制を設けています。これにより、週の半分以上で営業ができなくなり、実質的に年間営業日数は100日程度に制限されます。
これらの自治体独自の規制は、地域特性や住民の意見を反映したものであり、地域によって大きく異なります。そのため、民泊事業を始める際には、物件が所在する自治体の条例や規則を確認することが不可欠です。自治体のホームページで情報を確認するか、直接自治体の担当窓口に問い合わせることをお勧めします。
また、マンションやアパートなどの集合住宅では、管理規約によって民泊が禁止されているケースも多いです。そのため、用途地域や法律上は民泊が可能な場合でも、物件ごとの制限を確認することも重要です。
用途地域を違反するとどうなる?

民泊事業を始める際に用途地域の制限を軽視してしまうと、深刻な法的リスクに直面することになります。違反が発覚した場合、営業停止や罰金といった行政処分だけでなく、マンションなどの区分所有建物では区分所有法に基づく措置が取られることもあります。これらのペナルティは事業の継続を困難にするだけでなく、社会的信用にも大きなダメージを与えかねません。
実際に、多くの無許可民泊が行政指導や近隣住民からの通報によって摘発されています。主なリスクは以下の通りです。
- 営業の停止を命じられる
- 罰金刑が科される
- 区分所有法に基づく措置がとられる
それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
営業の停止を命じられる
用途地域違反で民泊営業を行った場合、最も一般的な行政処分が「営業停止命令」です。これは旅館業法や住宅宿泊事業法に基づいて行われる処分であり、即時に事業活動を停止しなければならなくなります。
営業停止命令が出されると、即日から営業を続けることができなくなります。すでに予約を受けている宿泊客がいる場合でも、キャンセルして返金対応をしなければなりません。このような急な対応は、宿泊客からの信頼低下やプラットフォームでの評価ダウンにつながり、再開後の営業にも大きな影響を及ぼします。
営業停止期間は違反の重大性によって異なりますが、軽微な違反でも30日程度、重大な違反の場合は6ヶ月以上の停止命令が出されることもあります。この間、収入が途絶えるだけでなく、固定費(家賃や光熱費など)は発生し続けるため、経営を圧迫する要因となります。
さらに深刻なケースでは、営業許可の取消処分が行われることもあります。許可が取り消された場合、再度許可を取得するまで営業を再開することはできません。また、取消処分を受けた場合、一定期間(通常は1年以上)は新たな許可申請が認められないケースが多いです。
このような事態を避けるためには、事前に物件の用途地域を確認し、その地域で認められている民泊の形態を選択することが不可欠です。また、営業開始後も法令遵守を徹底し、定期的に制度変更がないかチェックすることをお勧めします。
罰金刑が科される
用途地域違反で民泊営業を続けると、行政処分だけでなく刑事罰の対象となることもあります。特に悪質なケースや、行政指導を無視して営業を続けるケースでは、罰金刑が科される可能性が高まります。
旅館業法第25条では、無許可営業に対して「6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金」が規定されています。また、営業停止命令に違反して営業を続けた場合は「6ヶ月以下の懲役若しくは3万円以下の罰金又はこれを併科」とさらに重い罰則が適用されます。
住宅宿泊事業法第48条では、無届営業に対して「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科」という厳しい罰則が定められています。また、業務改善命令や業務停止命令に違反した場合も同様の罰則が科されます。
建築基準法第100条では、用途地域に適合しない建築物の使用は違法とされ、「100万円以下の罰金」の対象となります。さらに、是正命令に従わない場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と重い刑罰が科されることもあります。
こうした罰金刑は、金銭的な負担だけでなく、前科として記録に残るため、将来的な事業展開や就職活動にも影響を及ぼす可能性があります。特に法人として民泊事業を行っている場合、両罰規定により法人自体にも罰金が科されることがあり、企業イメージの低下につながります。
罰金刑を避けるためには、営業前に必ず用途地域を確認し、適法に営業できる条件を整えることが重要です。また、法改正や条例の制定などにも常に注意を払い、違法状態に陥らないよう注意することが必要です。
区分所有法に基づく措置がとられる
マンションなどの区分所有建物で用途地域違反の民泊を行った場合、行政処分や刑事罰に加えて、区分所有法に基づく措置を受けるリスクもあります。区分所有法は、マンション等の共同住宅における所有者間のルールを定めた法律です。
区分所有法第57条では、建物の使用方法が規約に違反し、区分所有者の共同生活の維持に著しい支障を生じさせる行為(いわゆる「違法行為」)に対して、他の区分所有者は当該行為の停止を請求できると定められています。つまり、マンションの規約で民泊が禁止されている場合や、住居専用地域で旅館業法に基づく営業を行っているような場合、他の住民から使用停止を求められる可能性があります。
さらに深刻なケースでは、区分所有法第59条に基づく「競売請求」の対象となることもあります。これは、区分所有者が建物の使用に関する規約に違反し、その違反行為によって共同生活上の障害が著しく、他の方法ではその障害を除去することが困難であると認められる場合に、他の区分所有者が裁判所に対して当該区分所有者の区分所有権の競売を請求できるというものです。
実際に、東京都内のマンションで無断で民泊営業を行っていた所有者に対して、管理組合が区分所有法第59条に基づく競売請求を行い、裁判所がこれを認めたケースがあります。この判決により、民泊営業者は自分の所有するマンションの部屋を強制的に売却されることになりました。
こうした区分所有法に基づく措置は、単に民泊営業ができなくなるだけでなく、所有している不動産自体を失うという極めて重大な結果をもたらします。マンションなどの区分所有建物で民泊を始める際には、用途地域の確認だけでなく、マンションの管理規約も必ず確認し、必要に応じて管理組合の承認を得ることが重要です。
違反しないために!用途地域の調べ方

民泊事業を適法に運営するためには、物件の用途地域を正確に把握することが不可欠です。用途地域の調査は、民泊事業の計画段階で最初に行うべき重要なステップです。
調査方法は主に以下の3つがあります。
- 市区町村の都市計画図の活用
- 行政の窓口での確認
- 不動産業者を通じた用途の確認
それぞれの調査方法について詳しく見ていきましょう。
市区町村の都市計画図の活用
多くの自治体では「都市計画情報マップ」や「都市計画Webマップ」などの名称で、都市計画図をWeb上で公開しています。これらのマップは自治体のホームページの「都市計画」「まちづくり」などのセクションから見つけることができます。
都市計画図を閲覧する際の手順は以下の通りです。まず、調べたい物件の住所を入力するか、地図上で場所を指定します。地図が表示されたら、用途地域を示すレイヤー(層)を選択します。通常、用途地域は色分けされており、地図上に表示されます。赤色や黄色が住居系、青色が商業系、緑色が工業系といったように、色によって用途地域の種類が区別されています。
都市計画図には用途地域以外にも、高度地区、防火・準防火地域、特別用途地区などの情報も記載されていることがあります。これらの情報も民泊営業に影響を与える可能性があるため、合わせて確認しておくと良いでしょう。
行政の窓口での確認
より確実に用途地域を確認するには、物件が所在する市区町村の都市計画課(または都市計画担当部署)に直接問い合わせる方法があります。行政窓口では、最新かつ正確な情報を得ることができるほか、用途地域に関する具体的な質問や民泊営業に関する相談も可能です。
行政窓口で用途地域を確認する際には、物件の住所(住居表示と地番両方あると確実)を準備しておきましょう。また、物件の位置が分かる地図や登記簿謄本などの資料があれば、より正確な確認ができます。行政窓口へ訪問する前に、電話で必要書類を確認しておくと安心です。
窓口では以下のような質問をすることで、より詳細な情報を得ることができます。
- 物件の正確な用途地域と建ぺい率・容積率は何か
- 当該用途地域では旅館業法に基づく営業は可能か
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく営業に関して、自治体独自の条例や規制はあるか
- 当該地域で民泊営業を行う際の注意点や制限事項はあるか
- 今後、当該地域の用途地域変更の予定はあるか
また、都市計画課だけでなく、保健所(旅館業法関連)や住宅宿泊事業担当課(民泊新法関連)にも相談することで、用途地域以外の規制や手続きについても把握することができます。行政窓口では、担当者から直接アドバイスを受けられることが大きなメリットです。
行政窓口での確認はやや手間がかかりますが、オンライン情報だけでは分からない細かな規制や条例についても知ることができます。特に自治体独自の条例がある地域では、窓口での確認が非常に重要になります。
不動産業者を通じた用途の確認
不動産業者は用途地域に関する専門知識を持っており、物件購入や賃貸の際に適切なアドバイスをしてくれます。特に民泊目的で物件を探している場合は、その旨を不動産業者に伝えることで、用途地域の制限を考慮した物件を紹介してもらえます。
不動産業者を通じて用途地域を確認する際のポイントは、民泊営業の目的と形態(旅館業法か民泊新法か)を明確に伝えることです。これにより、あなたの事業計画に適した物件を効率よく探すことができます。
不動産業者が提供する物件情報には、通常、用途地域や建ぺい率・容積率といった情報が含まれています。これらの情報を確認することで、物件が民泊営業に適しているかどうかを判断することができます。ただし、物件情報だけでは分からない自治体独自の規制もあるため、不動産業者に具体的に確認することが重要です。
例えば、以下のような質問をしてみましょう。
- この物件では民泊営業(旅館業法または民泊新法)は可能か
- この地域で民泊営業を行っている物件はあるか
- この地域で民泊営業を行う際の注意点や制限はあるか
- マンションの場合、管理規約で民泊は禁止されていないか
- 近隣住民とのトラブル事例はあるか
不動産業者は、過去の取引事例や地域の特性についての知識も持っているため、数字だけでは分からない地域の雰囲気や周辺環境についても情報を得ることができます。これは、民泊事業の成功において非常に重要な要素です。
ただし、不動産業者から得た情報だけを頼りにするのではなく、最終的にはオンラインでの調査や行政窓口での確認も合わせて行うことをお勧めします。特に重要な判断を行う際には、複数の情報源から得た情報を照らし合わせることが大切です。
用途地域の調査にはある程度の時間と手間がかかりますが、これは将来的なリスクを大きく軽減するための重要な投資だと考えましょう。しっかりとした事前調査を行い、安心して民泊事業を展開していただければと思います。
まとめ
用途地域は民泊事業の成否を左右する重要な要素です。住居系、商業系、工業系という大きく3つに分類される用途地域によって、旅館業法や民泊新法、特区民泊といった営業形態の選択肢が変わってきます。
特に住居専用地域では制限が厳しく、違反した場合は営業停止命令や罰金刑、マンションでは区分所有法に基づく競売請求といった深刻な事態に発展することもあります。安心して民泊事業を展開するためには、オンラインの都市計画図や行政窓口での確認、不動産業者の専門知識を活用して、物件の用途地域を正確に把握することが欠かせません。
法令遵守は単なる義務ではなく、長期的に安定した事業運営を実現するための基盤となります。用途地域の確認は、民泊事業の計画段階で最初に行うべき重要なステップです。適切な準備と知識を持って、地域社会と調和した民泊事業を展開していきましょう。