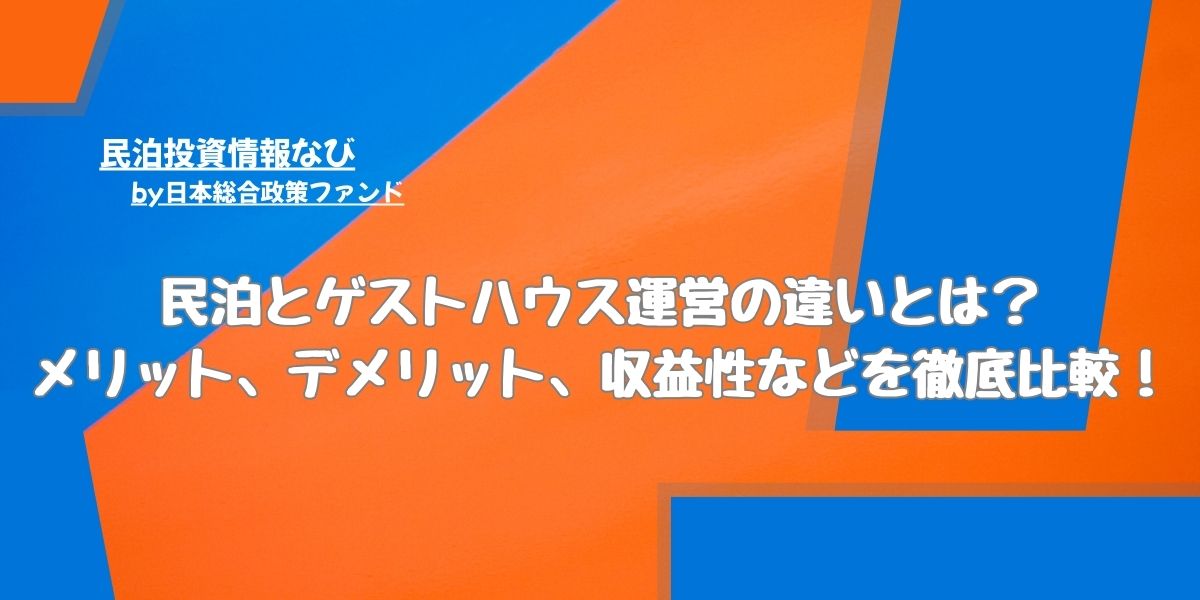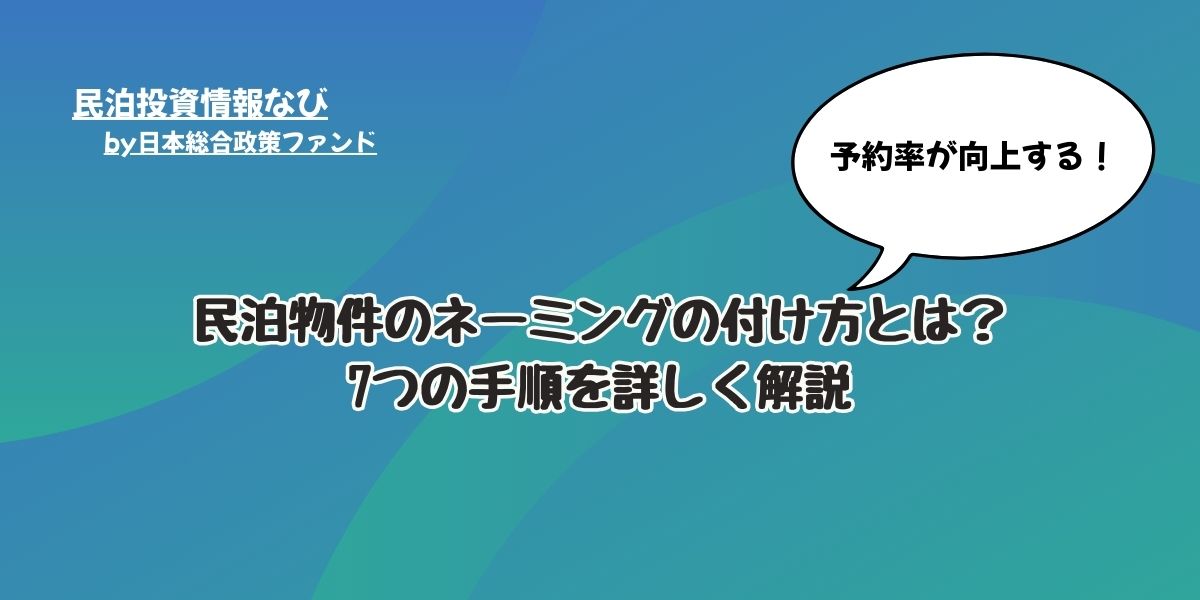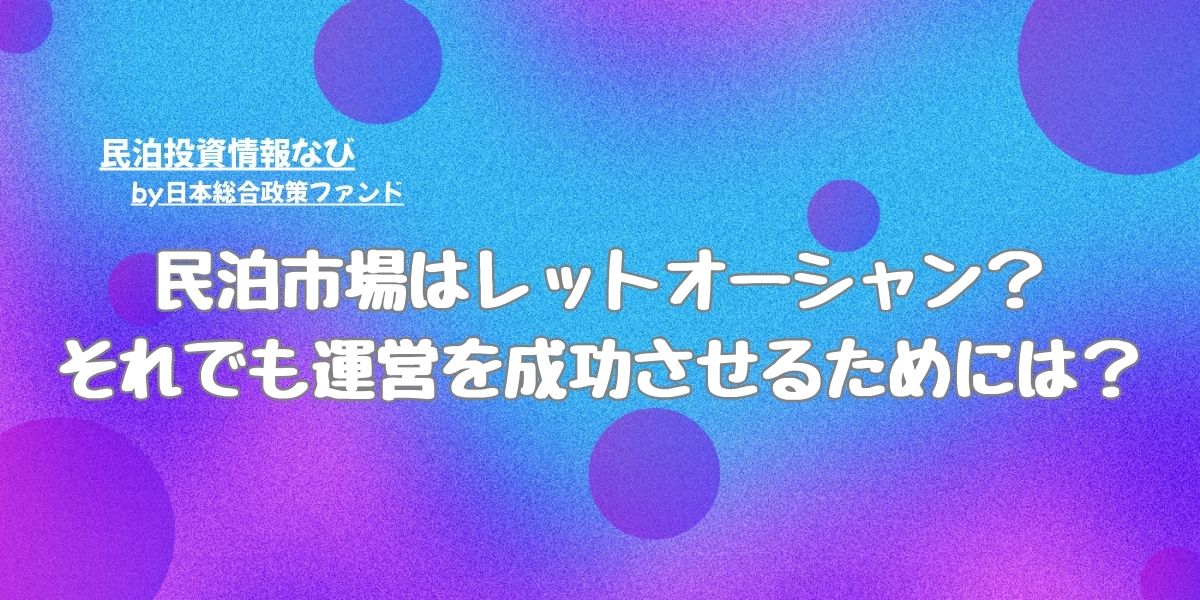「民泊とゲストハウス、どちらを始めるべきか」と悩んでいませんか? 宿泊施設運営に興味を持つ方にとって、この選択は事業の成否を左右する重要な決断です。
両者は似ているようで、法規制、初期投資、運営方法、収益構造が大きく異なります。自身の目標や状況に合わない選択をすると、想定外の負担やトラブルに直面する可能性があります。本記事では、メリット・デメリット、法規制、利用者層、初期投資、収益性まで、民泊とゲストハウスの違いを詳しく解説します。
民泊とゲストハウスのメリット

民泊とゲストハウスは、それぞれ異なる特徴を持つ宿泊施設です。
投資規模、運営形態、収益モデルによって、最適な選択肢は変わります。ここでは、民泊とゲストハウスそれぞれのメリットについて見ていきましょう。
民泊運営のメリット
**少ない初期投資で始められる**
- 既存の住宅をそのまま活用できるため、大規模な改修工事が不要
- 一般的なホテルやゲストハウスと比べて、高い宿泊料金を設定可能
- 稼働率が低くても収益を確保しやすい
- 遠隔での運営が可能で、副業としても成立する
**高い客単価を実現できる**
人気エリアでは、一泊当たりの客単価がゲストハウスの2〜3倍になることもあります。施設全体を一組の利用者に貸し出すため、プライバシーを重視する家族連れや友人グループから支持を得ています。
**運営の自由度が高い**
常時スタッフを配置する必要がなく、清掃やチェックインのサポートさえ整えば、遠隔での運営も可能です。民泊運営代行サービスを利用すれば、本業を持ちながらの副業運営も実現できます。内装や提供するサービスについても自由度が高く、オーナー自身の個性を反映させた宿泊体験を提供できるでしょう。
ゲストハウスのメリット
**安定した収益構造を構築できる**
- 複数の部屋を同時に運営できるため、一つの物件から得られる収益の上限が高い
- 稼働率の変動リスクを分散できる
- 繁忙期と閑散期の収益格差を緩和しやすい
- 特定の部屋が空室でも他の部屋からの収入を確保できる
**人との交流を促進できる**
共有スペースを設けることで、国内外の旅行者が自然に交流できる環境が生まれます。この「人との出会い」を求めて、専門的にゲストハウスを選ぶ層も少なくありません。
**法的安定性が高い**
ゲストハウスは旅館業法に基づく営業形態となるため、自治体によって条例で民泊が制限されるケースがあっても、適切な許可を取得することで継続的な営業が可能です。運営者やスタッフが常駐していることで、宿泊者に対してきめ細かいサービスの提供ができます。
民泊とゲストハウスのデメリット
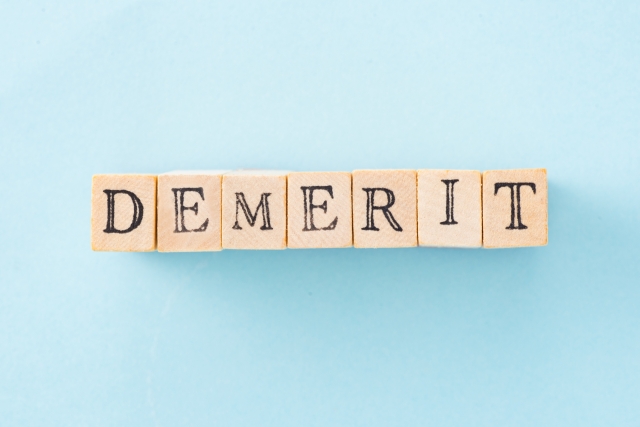
宿泊施設運営には、魅力的な面だけでなく、様々な課題や制約も存在します。
実際に運営に携わると、表面的には見えない苦労や予想外の障壁に直面することがあります。ここでは、民泊とゲストハウス運営のデメリットを見ていきましょう。
民泊運営のデメリット
**法規制への対応が複雑**
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や定期的な報告義務がある
- 地域によって営業日数が制限されたり、マンションの管理規約で禁止されているケースがある
- 規制に違反した場合、罰則の対象となる可能性がある
- 常に最新の法規制を把握する必要がある
**収益面での不安定さ**
季節や観光イベントの有無によって予約状況が大きく変動します。閑散期には予約が極端に減少し、収入が不安定になりがちです。一組の宿泊者のキャンセルがそのまま売上ゼロにつながるリスクがあります。
**近隣トラブルの可能性**
住宅地にある民泊では、宿泊者の騒音や生活習慣の違いから近隣住民とのトラブルが発生することがあります。外国人観光客が多い場合、文化や習慣の違いからゴミの分別や深夜の騒音などの問題が生じやすい状況です。
**管理面での負担**
チェックインやチェックアウト対応、清掃、設備トラブルへの対応など、宿泊者が入れ替わるたびに一定の作業が発生します。突発的なトラブル(設備の故障など)への即時対応が求められるため、常に連絡が取れる状態を維持する必要があり、プライベートな時間の確保が難しくなります。
ゲストハウスのデメリット
**初期投資が高額**
- 旅館業法に基づく許可を取得するため、専用の玄関や廊下の確保、防火設備の設置など、構造面での条件を満たす必要がある
- 消防法や建築基準法の適合も求められるため、専門家への相談費用も必要
- 改修工事には相当のコストがかかり、既存住宅の活用よりも大規模な投資が必要
**人件費の負担が大きい**
常時スタッフが常駐する運営形態が基本となるため、人件費が経営を圧迫する要因になりがちです。24時間対応が必要な場合、シフト制での人員配置が必須となり、採用・育成・マネジメントなど、人事面での負担も増大します。
**収益性の課題**
一部屋あたりの宿泊料金が民泊に比べて低くなる傾向があります。施設の維持管理コストも見逃せない問題です。共用スペースを含む全ての設備を常に良好な状態に保つための清掃や修繕、定期的な設備更新などが必要です。
**宿泊者同士のトラブル対応**
共同生活空間では、生活習慣や価値観の違いからトラブルが発生することがあります。マナーの悪い宿泊者によって他の宿泊者の満足度が下がるリスクもあり、トラブル発生時の適切な対応やルール作りが必要です。
民泊とゲストハウスの運営方法の違い

民泊とゲストハウスは一見似ていますが、運営方法には大きな違いがあります。
営業形態や法規制の違いを理解せずに始めると、後から大きな問題に直面することもあります。それぞれの特徴を理解して、自分の状況に合った選択をするための判断材料としてください。
民泊とゲストハウスの営業許可の違い
**適用される法律が異なる**
民泊は「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づいて運営され、自治体への届出制となっています。ゲストハウスは「旅館業法」の簡易宿所営業として許可が必要です。この違いは単なる手続きの違いではなく、営業条件や施設基準に大きく影響します。
民泊の場合、年間営業日数が180日(自治体によってはさらに制限あり)に制限されます。ゲストハウスは365日営業が可能です。民泊では住宅と認められる物件でなければならず、専ら人の居住の用に供されている建物であることが条件となります。
**施設基準の違い**
ゲストハウスの営業許可取得には、フロント設置や玄関の独立性、廊下幅の確保など、より厳格な施設基準を満たす必要があります。防火・避難設備については消防法に基づく厳しい基準があり、スプリンクラーや非常用照明の設置が求められるケースも多いです。
民泊の運営方法
**個人オーナーが小規模に行うことが一般的**
運営の基本的な流れとしては、まず自治体への届出を行い、民泊仲介サイト(Airbnbやbooking.com等)に登録して予約受付を開始します。予約管理からチェックイン対応、清掃、トラブル対応まで、基本的にオーナー自身が行います。
物件全体を一組の宿泊者に貸し出すのが一般的です。チェックインの方法としては対面での鍵の受け渡しだけでなく、スマートロックの活用や鍵の受け渡しボックスの設置など、非対面での対応も可能です。これにより、オーナーが常駐しなくても運営できる柔軟性があります。
**設備面での準備が必要**
通常の住宅設備に加えて、無料Wi-Fi、アメニティ、調理器具などの提供が求められます。宿泊者向けの説明書やハウスルールの作成、緊急時の連絡先の明示など、コミュニケーション面での準備も欠かせません。多言語対応ができると外国人観光客の受け入れもスムーズになります。
関連:民泊でスマートロックを導入するメリット、デメリットとは?
ゲストハウスの運営方法
**本格的な宿泊施設経営の形態**
旅館業法に基づく簡易宿所として、より本格的な宿泊施設経営の形態を取ります。営業許可の取得から始まり、施設基準を満たすための改修工事や設備投資が必要です。防火設備や構造面での条件を満たすためには、専門家(建築士や消防設備士など)の協力を得ることが一般的です。
**人的サービスの提供が必須**
多くの場合、複数の宿泊者や宿泊グループが同時に滞在します。フロントでの受付や館内での案内など、人的サービスの提供が欠かせません。これに伴い、スタッフの採用や育成、シフト管理といった人事面での業務も発生します。
**共用スペースの管理が重要**
リビング、キッチン、シャワー、トイレなどの共用スペースの管理が重要です。多くの人が利用する設備は摩耗や故障のリスクが高く、定期的なメンテナンスが必須となります。清掃も毎日行う必要があり、水回りの衛生管理は徹底する必要があります。
予約管理については、自社ウェブサイトの構築に加え、OTA(Online Travel Agent)と呼ばれるBooking.comやHostelworldなどの予約サイトへの登録が一般的です。
民泊とゲストハウスの利用者層の違い

宿泊施設を運営する上で最も重要なのは、「誰に」向けてサービスを提供するかを明確にすることです。
民泊とゲストハウスでは、利用者層やそのニーズが大きく異なります。それでは、それぞれの利用者層の特徴について見ていきましょう。
民泊の利用者の特徴
**プライバシーを重視する層に人気**
- 家族やカップル、友人グループなど、共に旅行する仲間だけで過ごしたい層
- 他の宿泊者と顔を合わせることなく滞在できる点が魅力
- 一棟貸しや個室貸しの形式が多い
**「現地の生活」を体験したいニーズを持つ層**
観光地ではなく住宅街に立地する民泊は、地元のスーパーで買い物をしたり、地域の飲食店を利用したりと、まるでその街に住んでいるかのような体験を提供します。こうした「非日常の中の日常」を求める旅行者にとって、民泊は理想的な宿泊形態です。
**経済的な観点では広いスペースを確保したい層**
宿泊費を抑えながらも広いスペースを確保したい層にも民泊は支持されています。複数人で利用する場合、一人当たりのコストが大幅に下がるため、コストパフォーマンスを重視する利用者には魅力的な選択肢となります。
客層としては、30〜40代の夫婦やファミリー層、仲の良い友人グループが中心です。子連れファミリーにとっては、子どもの声や動きを気にせず過ごせる環境は大きな魅力です。
ゲストハウスの利用者の特徴
**「人との出会い」を重視する層**
- 一人旅のバックパッカーやソロトラベラー
- 新たな出会いや異文化交流を求める旅行者
- 旅先での孤独感を解消し、旅仲間を見つける場としての役割
**若年層の利用が目立つ**
年齢層としては、20代を中心とした若年層の利用が目立ちます。学生や社会人経験の浅い若者など、予算に制約がある層がコストパフォーマンスを重視してゲストハウスを選ぶケースが多いです。ドミトリータイプ(相部屋)の宿泊形態は、一泊あたりの料金が大幅に抑えられるため、長期旅行者にも人気があります。
**海外からの旅行者の割合が高い**
欧米やオーストラリアからのバックパッカーは、自国での「ホステル文化」に慣れ親しんでいるため、日本旅行においてもゲストハウスを積極的に利用します。彼らは日本人宿泊者との交流を通じて生きた日本文化を体験したいというニーズを持っています。
滞在スタイルとしては、「拠点」というよりも「通過点」として利用されるケースが多く、平均宿泊日数は1〜2泊程度と比較的短いのが特徴です。
民泊とゲストハウスの初期投資額の違い

宿泊施設を始める際に最も気になるのが初期投資額です。
民泊とゲストハウスでは必要となる初期投資額に大きな差があります。ここでは、それぞれの宿泊形態で実際に必要となる費用の内訳について見ていきましょう。
民泊運営に必要な最低限の費用
**一般的には100万円〜300万円程度が目安**
すでに民泊として使用可能な状態の物件であれば、大規模な改修工事は不要なため、比較的低コストで開業できるのが民泊の魅力です。
まず必要となるのが、民泊届出のための費用です。住宅宿泊事業法に基づく届出自体の手数料は数千円程度ですが、消防設備点検や管理規約の確認、近隣への説明など、付随する手続きを含めると10万円前後の費用を見込んでおくべきでしょう。
**内装や設備の整備費用**
基本的な家具(ベッド、テーブル、椅子など)に加え、家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど)、寝具、調理器具、食器類などの準備が必要です。これらの費用は、新品で揃える場合で80万円〜150万円程度を見込んでおきましょう。
IT環境の整備も欠かせません。高速Wi-Fiの設置(工事費用込みで5万円〜10万円)やスマートロック(3万円〜10万円/台)の導入は、現代の宿泊者にとって重要な要素です。
宿泊者を迎え入れるためのアメニティやリネン類(タオル、シーツなど)の初期費用として20万円〜40万円程度を見込みましょう。リネン類は複数セット用意する必要があります。
運転資金としては、最低でも3ヶ月分の固定費(家賃、水道光熱費、通信費など)を確保しておくことをお勧めします。
関連:民泊を始める資金はいくら必要?融資をうけることは可能?内容や条件、必要書類など解説!
ゲストハウス開業のための必要な資金
**一般的には800万円〜3,000万円程度が目安**
物件の規模や立地、改修の程度にもよりますが、これだけの資金が必要です。これは旅館業法に基づく施設基準を満たすための改修費用が大きな割合を占めるためです。
**建物の改修工事費が最大の投資項目**
旅館業法では、玄関・廊下・階段などの幅や、客室の広さ、トイレ・浴室の数など、細かな設備基準が定められています。これらの基準を満たすための改修工事には400万円〜1,500万円程度の費用がかかるケースが一般的です。防火関連の設備(スプリンクラー、防火区画、非常用照明など)の設置は大きなコストとなります。
**許可申請関連の費用**
旅館業の営業許可申請(5万円〜10万円)、消防設備の検査申請(10万円〜30万円)、建築確認申請が必要な場合はその費用(30万円〜50万円)、さらに設計士や行政書士への依頼費用(30万円〜100万円)なども発生します。
**内装や家具・設備の整備費用**
ドミトリータイプの場合は二段ベッド(1台15万円〜25万円)を複数台設置するほか、共用スペース用の家具(ソファ、テーブル、椅子など)、家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)の購入費用として200万円〜500万円程度を見込む必要があります。水回り設備(シャワー、トイレ、洗面台など)の整備にも100万円〜300万円程度のコストがかかります。
リネン類や備品の初期費用も民泊より規模が大きくなります。多数の宿泊者を受け入れるため、シーツ、枕カバー、タオルなどを大量に用意する必要があり、その費用は50万円〜100万円程度になります。
運転資金としては、最低でも6ヶ月分の固定費(家賃、人件費、水道光熱費、通信費など)を確保しておくことが望ましいです。
民泊とゲストハウスの収益性の違い

「収益性ではどちらが有利なのか」という質問は、宿泊施設の運営を検討する上で避けて通れない重要なポイントです。
一概にどちらが収益性に優れているとは言えません。それぞれに異なる収益構造があり、運営条件や外部環境によって優位性が変わるためです。ここでは、民泊とゲストハウスの収益性を多角的に比較していきましょう。
関連:【利回り率8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
季節ごとの収益構造の違い
**民泊は季節変動の影響を大きく受ける**
観光シーズンやイベント時期には宿泊料金を通常の1.5〜2倍に設定できる一方、オフシーズンでは予約が極端に減少するリスクがあります。
**ゲストハウスは比較的安定した稼働率を維持**
料金設定は柔軟性に欠けるものの、複数の部屋を運営することによるリスク分散効果があり、オフシーズンでも一定の収益を確保しやすいです。
立地による利益率の違い
**民泊は住宅地でも高い収益性を実現できる**
観光地から少し離れた住宅地でも高い収益性を実現できる点が特徴です。観光客が「地元の生活」を体験できる立地として、一般住宅地の物件でも十分な集客が可能です。
**ゲストハウスは交通アクセスの良さが収益性に直結**
駅から徒歩10分以内の立地と、それ以上離れた立地では稼働率に20%以上の差が出ることも珍しくありません。公共交通機関の利用が前提となる外国人バックパッカー層をターゲットにする場合、交通の利便性は最重要条件となります。
地価や賃料の観点では、民泊は比較的高額な物件でも収益化しやすい傾向があります。都心の高級マンションを活用した民泊では、一泊あたり3万円〜5万円の料金設定も可能で、月間10日程度の稼働でも十分な収益を上げられるケースがあります。
インバウンド需要での収益性の違い
**民泊は欧米からのファミリー層やカップルに人気**
外国人観光客は一般的に滞在期間が長く(平均5〜7泊)、一回の予約あたりの総額が大きくなる傾向があります。リピート率も高く、一度気に入った民泊には次回の旅行でも予約を入れるケースが多いです。
**ゲストハウスはアジア圏からの若年層旅行者に人気**
東南アジアや韓国、台湾からのバックパッカーは予算を重視する傾向が強く、ドミトリータイプの安価な宿泊施設を好みます。滞在期間は比較的短い(平均2〜3泊)ものの、回転率が高く、年間を通じて安定した集客が期待できます。
単価と稼働率の違い
**民泊は高い宿泊単価が特徴**
一般的に、同じエリアのビジネスホテルと比較して1.5〜2倍、ゲストハウスと比較すると2〜3倍の料金設定が可能です。都心部では一泊あたり2万円〜3万円、人気観光地では3万円〜5万円の料金設定も珍しくありません。
稼働率は比較的低く、年間平均で40〜60%程度に留まるケースが一般的です。これは、一棟または一室を一組の利用者に貸し出す形式であるため、キャンセルがそのまま収益ゼロにつながることや、連泊の前後に清掃のための空室期間を設ける必要があることが理由です。
**ゲストハウスは低い宿泊単価と高い稼働率が特徴**
ドミトリータイプ(相部屋)の場合、一泊あたり2,500円〜4,000円程度、個室タイプでも5,000円〜8,000円程度の料金設定が一般的です。複数のベッドや部屋を同時に運営できるため、施設全体としての収容力は高くなります。
稼働率は比較的高く、人気エリアでは年間平均70〜80%の稼働率を達成するケースも少なくありません。これは多くの部屋やベッドを運営することによるリスク分散効果と、低価格による予約障壁の低さが要因です。営業日数の制限がないため、年間365日の営業が可能である点も重要です。
収益構造の視点では、民泊は「高単価×低回転」、ゲストハウスは「低単価×高回転」のビジネスモデルと言えます。
長期運用での安定性の違い
**民泊は法規制の変更リスクが比較的高い**
住宅宿泊事業法(民泊新法)は2018年に施行された比較的新しい法律であり、今後も規制強化の可能性があります。
**ゲストハウスは長年にわたり安定した法的枠組みの下で運営**
旅館業法という長年にわたり安定した法的枠組みの下で運営されます。営業許可を取得すれば、営業日数の制限なく運営できる点が大きな強みです。いったん許可を取得すれば、法改正などによって既存の営業が制限されるリスクは比較的低いと言えます。
運営コストによる収益の違い
**民泊の最大の強みは人件費の低さ**
自己所有物件の場合、清掃を自分で行えば人件費はほぼゼロとなります。チェックインやチェックアウトもスマートロックを活用した非対面方式を採用することで、人的コストを大幅に削減できます。
**ゲストハウスでは人件費が最大の経費項目**
24時間対応のフロントを設置する場合、最低でも3〜4名のスタッフが必要となり、月間人件費は80万円〜150万円に達するケースも珍しくありません。
水道光熱費の面でも大きな差があります。民泊は利用者がいない期間は基本的に電気や水道をほとんど使用しないため、固定費を最小限に抑えられます。
消耗品費にも違いがあります。民泊ではアメニティの提供が一般的ですが、宿泊者数が限られるため、月間の消耗品費は5,000円〜15,000円程度です。ゲストハウスでは多くの宿泊者が利用するため、トイレットペーパーやハンドソープなどの消耗品の消費量が多く、月間15,000円〜40,000円程度のコストがかかります。
一般的に民泊は売上に対する営業利益率が40〜60%と高い傾向にあります。ゲストハウスの営業利益率は20〜40%程度にとどまるケースが多く、初期投資の回収にも時間がかかる傾向があります。
民泊とゲストハウス、どちらが「より良い」ということはありません。それぞれに強みと弱みがあり、目標に合った選択をすることが重要です。初期投資を抑えて小規模に始めたいなら民泊、本格的な宿泊業として長期的に取り組みたいならゲストハウスといった具合に、選択すべきです。
関連:民泊のランニングコストには何が含まれる?コストが適切でないとどうなる?
まとめ
民泊とゲストハウス、それぞれに明確な特徴があることがおわかりいただけたでしょうか。
民泊は比較的少ない初期投資で始められ、高い宿泊単価と柔軟な運営が魅力です。一方、ゲストハウスは本格的な宿泊業として、規模の経済を活かした安定した運営が可能です。どちらを選ぶかは、あなたの投資余力や関われる時間、目指す事業規模によって変わってきます。
小規模に始めて様子を見たいなら民泊、長期的な宿泊ビジネスとして展開したいならゲストハウスが向いているかもしれません。どちらを選ぶにしても、立地条件や地域特性を十分に調査し、ターゲットとなる宿泊者のニーズを理解することが成功への鍵となります。