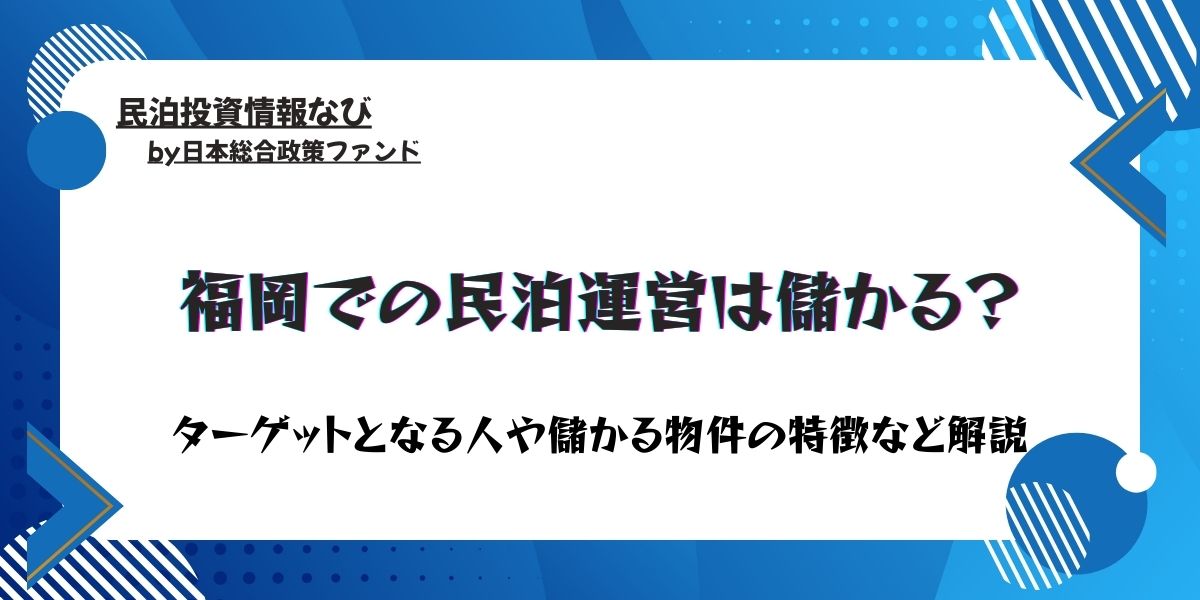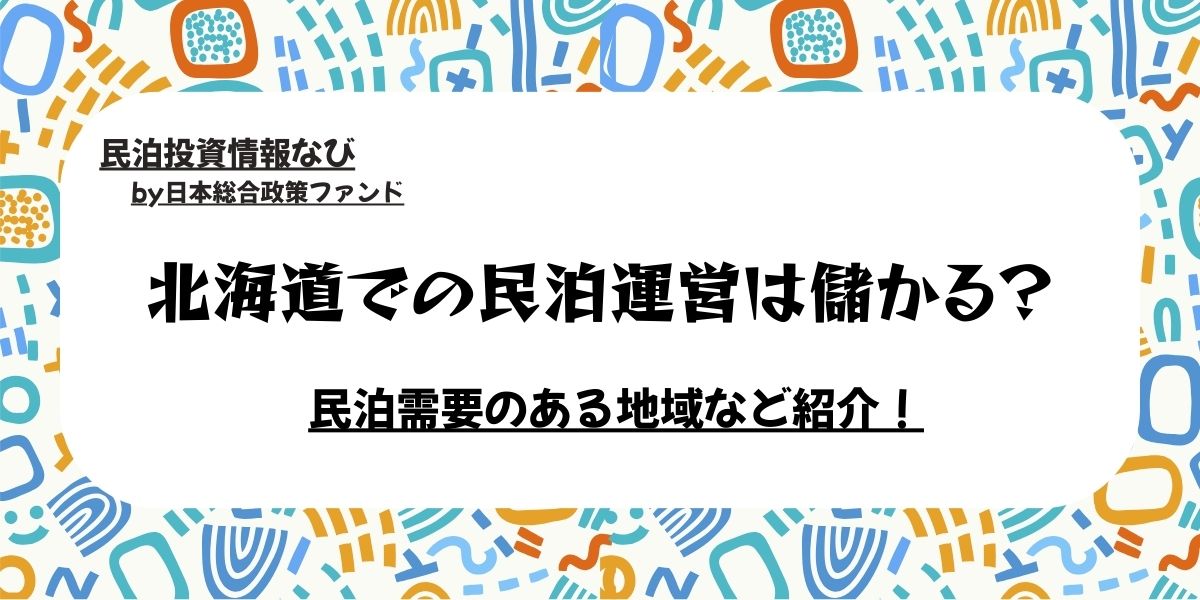「京都で民泊を始めたら本当に儲かるの?」「初期投資はどれくらい必要?」「リスクや規制は大丈夫?」こんな疑問を抱えていませんか?京都は世界有数の観光地として人気が高く、インバウンド需要の回復とともに民泊ビジネスへの注目が再び高まっています。
しかし、高収益の裏には厳しい規制や初期投資の壁も存在します。この記事では、京都の民泊市場の現状から具体的な収益シミュレーション、さらには失敗しないための方法まで、紹介します。
\AIを活用した最先端の民泊特化のM&A仲介/
\ 日本総合政策ファンド /
京都での民泊運営が儲かると注目されている理由

京都には、清水寺や金閣寺、二条城などの日本独特かつ歴史的な観光地がたくさん存在しているといった人気がありますが、これ以外にも京都で民泊運営が注目されている理由というものが存在しています。まず。
なぜ京都での民泊運営が注目されているのか具体的な理由について、見ていきましょう。
世界中から観光客が押し寄せ宿泊需要が爆発しているため
ホテル不足で代替品として民泊が使用されているため
京都市内のホテルの平均稼働率は80%を超えることも多く、繁忙期にはほぼ100%に達することもあります。この供給不足の状況が、民泊への需要を生み出す大きな要因となっています。
特に外国人観光客は異文化体験を求めて民泊を選ぶ傾向が強く、「日本の一般家庭での生活を体験したい」というニーズが高まっています。ホテルとは一線を画す「暮らすような旅」の提供が可能な民泊は、このようなニーズを満たす理想的な選択肢となっています。
また、家族や友人グループなど複数人での旅行の場合、ホテルの部屋を複数取るよりも民泊一棟を借りる方が経済的であるため、グループ向けの需要も非常に高いです。4〜6人用の広めの民泊物件は特に人気があり、高い稼働率を維持しやすい傾向にあります。
さらに、ビジネスホテルやチェーンホテルでは味わえない、その土地ならではの雰囲気や体験を求める旅行者も増えています。彼らにとって民泊は単なる宿泊施設ではなく、旅の思い出の一部となる重要な要素なのです。
町家や立地によっては高単価で貸し出せるため
京都独自の魅力である「町家」は民泊として非常に高い人気を誇っています。
京町家の歴史的価値や伝統的な和の空間は、特に外国人観光客から絶大な支持を得ています。「本物の日本」を体験できる貴重な機会として、高額でも喜んで支払う宿泊客が多いのです。東京などの民泊の宿泊費は一泊1万〜1万5千円程度が相場となっていますが、一泊あたり4万円以上の高単価設定でも十分に集客できる物件も少なくありません。
立地も非常に重要な要素です。清水寺や祇園、嵐山など人気観光地の近くにある物件は、アクセスの良さから高い需要があります。例えば、京都駅から徒歩10分圏内の物件は、観光客にとって非常に魅力的で、高い稼働率と単価を維持しやすいでしょう。
また、京都の観光エリアは比較的コンパクトにまとまっているため、主要な観光地へのアクセスが良好な中心部の物件は特に価値が高いです。祇園や河原町、四条烏丸周辺などの中心部では、1泊あたりの単価を高く設定しても十分な需要があります。
さらに、リノベーションの質も重要な差別化要因となります。伝統的な要素を残しながらも現代的な快適さを兼ね備えた物件は、高級感のある宿泊体験を提供できるため、プレミアム価格での提供が可能です。手入れの行き届いた日本庭園や露天風呂などの特別な設備があれば、さらに高単価での貸し出しが実現できます。
副業でも月に100万円の収入を実現することもできるため
民泊事業は比較的少ない初期投資で始められる点も魅力の一つです。特に自宅の空き部屋や既に所有している不動産を活用する場合は、大きな追加投資なしでビジネスを始めることができます。
京都で2〜3部屋の民泊を運営した場合、繁忙期には月に100万円以上の売上を達成することも十分に可能です。特に効率的な運営システムを構築できれば、本業と並行して副業として民泊ビジネスを展開できます。
物件の管理や清掃、ゲスト対応などの業務は、最近では専門の代行サービスも充実しています。これらのサービスを上手く活用することで、物理的な作業時間を最小限に抑えながら収益を上げることが可能です。
関連:民泊を経営の平均年収はどれくらい?成功するためのコツなど紹介
京都での民泊運営の収益はどれくらい?

京都での民泊投資を検討するなら、収益性は最も気になるポイントでしょう。一般的な不動産投資と比較して民泊はどれくらい儲かるのか、具体的な数字で見ていきます。
特に京都の民泊市場は独自の特性を持っており、インバウンド需要の高さから収益性も高い傾向にあります。
京都民泊の平均利回り
京都の民泊投資は一般的な不動産投資と比較して高い利回りが期待できます。通常の賃貸物件の利回りが3〜5%程度であるのに対し、民泊の平均利回りは8〜18%と大幅に高くなっています。京都であれば、立地や物件タイプによりますがそれ以上の利回りも十分に可能です。
京都市内でも地域によって利回りには差があります。例えば、京都駅周辺や祇園・東山エリアなどの観光地に近い物件は、高い稼働率と単価を実現できるため、15〜20%の利回りも珍しくありません。一方、少し中心部から離れた場所でも、アクセスの良さや物件の魅力で十分な利回りを確保できるケースが多いです。
関連:【利回り8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
1年間の想定収入シミュレーション
まず京都市内の中心部にある物件を例に考えてみます。オーダー用に60平米程度の京町家タイプの物件を取得したケースを想定します。取得価格を2,500万円、リノベーション費用を500万円、合計3,000万円の初期投資としましょう。
稼働可能日数は法律上の制限から年間180日です。京都はインバウンド需要が非常に高いため、稼働率は平均75%と高めに設定できます。実質的な稼働日数は180日×75%=135日となります。
宿泊単価は季節によって大きく変動します。繁忙期(桜、紅葉シーズン、祇園祭など)は1泊あたり35,000円、通常期は25,000円、閑散期は20,000円と設定します。年間の平均単価を26,000円とすると、年間の売上は26,000円×135日=351万円円となります。
ここから運営コストを差し引いていきます。
- 固定費(年間)
固定資産税:約25万円
- 火災保険料:約5万円
- インターネット回線費:約7万円
- 設備維持費:約10万円
- その他経費:約8万円 固定費合計:約55万円
- 変動費(年間)
清掃費(1回あたり8,000円):約108万円(135日)
- アメニティ費(1泊あたり1,000円):約13.5万円
- 水道光熱費:約24万円
- 小規模修繕費:約15万円 変動費合計:約160.5万円
年間経費の合計は、55万円+160.5万円=215.5万円となります。
したがって、年間の純利益は135万円となります。この場合の利回りは4.5%となりますが、これは180日の制限がある場合の数字です。
しかし、京都市では旅館業法の簡易宿所として営業許可を取得すれば365日営業が可能になります。この場合、稼働率を同じ75%と仮定すると、年間稼働日数は365日×75%=273.75日≒274日となります。
年間の売上は26,000円×274日=712万円となり、変動費も約325万円に増加しますが、固定費は変わらないため、年間純利益は332万円となります。
この場合の利回りは11.1%となり、一般的な不動産投資と比較して非常に高い利回りが期待できます。特に京町家などの特色ある物件では、宿泊単価をさらに高く設定できるケースもあり、15〜18%の利回りも十分に視野に入れることができるでしょう。
京都で民泊投資のリスクは何がある?

京都で民泊ビジネスを始める前に、収益性だけでなくリスク要因も十分に理解しておく必要があります。高い収益が期待できる一方で、京都ならではの特有のリスクや障壁も存在します。
投資判断を行う前に、これらのリスク要因を把握し、対策を講じることが必要です。それでは、京都の民泊投資における主なリスク要因を詳しく見ていきましょう。
180日制限や地域条例などの厳しい規制に縛られる
また、近隣住民への事前説明や定期的な報告義務、24時間の管理体制の整備など、運営面での規制も厳しくなっています。これらの規制を守るためには、専門的な知識や対応が必要となり、運営コストの増加につながる可能性があります。
このような厳しい規制環境下では、「簡易宿所」として旅館業法の許可を取得する選択肢も検討価値があります。簡易宿所であれば年間365日の営業が可能ですが、消防法や建築基準法など、より厳格な基準を満たす必要があります。
関連:民泊の180日ルールとは?なぜ制限される?違反するとどうなる?
町家改装や許可の取得に大金が必要になる
京都の民泊、特に人気の高い町家を活用した民泊を始めるには、かなりの初期投資が必要です。町家自体の購入価格は立地によって大きく異なりますが、人気エリアでは数千万円から1億円以上することも珍しくありません。
さらに、古い町家を民泊として利用するには大規模なリノベーションが必要になることがほとんどです。耐震補強、水回りの改修、電気設備の更新、冷暖房設備の導入など、快適な宿泊環境を整えるためには数百万円から1,000万円以上の改装費用がかかることもあります。
また、前述の「簡易宿所」として営業するためには、消防設備(スプリンクラー、自動火災報知器、避難誘導灯など)の設置や、建築基準法に則った改修が必要となり、これらの対応だけでも数百万円のコストがかかります。
このような高額な初期投資は、収益回収までの期間を長くし、投資リスクを高めています。しかし、民泊物件を売却した時のキャピタルゲインも見込むことができるため需要のある地域を購入することも良いでしょう。
文化の違いによる外国人とのトラブルが発生する可能性がある
京都の民泊は外国人観光客からの需要が高いですが、文化や生活習慣の違いによるトラブルのリスクも存在します。
まず、日本独特の生活ルール(ゴミの分別、騒音への配慮、靴の脱ぎ方など)を理解していない外国人客とのトラブルが発生することがあります。特に、町家は木造建築で防音性が低いため、騒音問題は深刻になりやすいです。
次に言語の壁も大きな課題です。緊急時や問題発生時にスムーズにコミュニケーションが取れないと、小さな問題が大きなクレームに発展するリスクがあります。多言語対応の準備や通訳サービスの導入などが必要になる場合もあります。
さらに、文化的な誤解から生じるトラブルも考えられます。例えば、伝統的な畳や障子、ふすまなどの扱い方を知らない外国人客が、誤って破損させてしまうケースもあります。また、日本独特の設備(お風呂の使い方、エアコンの操作方法など)の使用方法を理解できず、トラブルになることもあります。
関連:知らないと危険!民泊でのトラブルとは?トラブル回避のための対策法を解説!
無許可運営や条例違反によって罰金や閉鎖のリスクがある
民泊に関する法規制を遵守せずに営業を行うと、厳しいペナルティを受けるリスクがあります。無許可営業や条例違反が発覚した場合、罰金や営業停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。
住宅宿泊事業法違反の場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。また、旅館業法の無許可営業の場合は、6月以下の懲役または100万円以下の罰金の罰金となる可能性もあります。
京都市では、違法民泊の取り締まりが特に厳しく行われています。専門の監視チームが定期的なパトロールを行い、違法と思われる物件には立入調査が行われることもあります。また、近隣住民からの通報による摘発も増えており、発覚のリスクは年々高まっています。
無許可営業が発覚した場合、即時の営業停止命令により収入が途絶えるだけでなく、過去の営業による収益の没収や追徴課税を求められる可能性もあります。さらに、違法営業の事実が公表されることで、オーナーの社会的信用が失われるリスクもあります。
条例に違反した運営を行った場合も、行政指導や改善命令の対象となり、最終的には営業許可の取り消しにつながる可能性があります。特に、近隣への騒音や迷惑行為に関する苦情が多発すると、行政からの監視が厳しくなります。
関連:民泊を無許可で始めるリスクとは?無許可で始まると捕まる?
京都で民泊を始める際に失敗しないための方法

京都で民泊ビジネスを始める際には、先に述べたリスクを回避しながら、効率的に収益を上げる方法を知っておくことが重要です。
特に初めて民泊事業に参入する方にとっては、専門的なサポートを活用することで、多くの失敗を回避できます。どのようなサービスを使用すればよいのでしょうか?
民泊開設代行サービスを使用する
民泊ビジネスを始める際の最大の障壁のひとつが、複雑な許認可手続きと物件の準備です。この過程で多くの時間とコストがかかり、知識不足による失敗も起こりやすい部分です。民泊開設代行サービスを利用することで、このような初期段階の失敗リスクを大幅に軽減できます。
民泊開設代行サービスの大きなメリットは、地域特有の規制や必要な手続きに精通したプロフェッショナルのサポートを得られることです。京都市は特に民泊に関する規制が厳しいため、地域の条例や規制に詳しい代行業者を選ぶことが重要です。
代行サービスは通常、以下のような業務のサポートを行います。
まず許認可申請のサポートが挙げられます。住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や、より収益性の高い簡易宿所としての旅館業法の許可申請など、複雑な行政手続きを代行してくれます。提出書類の作成や行政との折衝も任せられるため、許可取得までの時間短縮になります。
また、物件の適合性チェックも重要なサービスです。購入や賃借を検討している物件が民泊として運営可能かどうか、どのような改修が必要かを事前に専門家の目でチェックしてもらえます。これにより、後から「この物件では営業できない」というトラブルを避けられます。
さらに、設備導入のアドバイスも貴重です。消防設備や防音対策、セキュリティシステムなど、法令遵守と顧客満足度向上の両面で必要な設備について、コストパフォーマンスを考慮したアドバイスを受けられます。同時に、必要な工事の調整や監督も代行してくれることが多いです。
さらに、運営システムの構築サポートも見逃せません。予約管理システム、鍵の受け渡し方法、清掃サービスの手配など、運営に必要なシステムづくりをサポートしてくれます。特に遠隔地からの運営を考えている場合、このサポートは非常に価値があります。
民泊M&A仲介を使用して運営実績のある物件を購入する
一から民泊ビジネスを立ち上げるのではなく、すでに運営実績のある民泊物件を購入する方法も効率的な参入方法です。民泊M&A仲介サービスを利用することで、稼働実績のある物件をスムーズに取得できます。
M&A(買収)による参入の最大のメリットは、即時に収益が発生する点です。一から立ち上げる場合、許認可取得や改修工事、集客までに数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。しかし、稼働中の物件を購入すれば、翌日から収益が発生します。
また、実績に基づいた投資判断が可能になります。過去の稼働率や収益データ、顧客レビューなどの実績を基に投資判断ができるため、収益予測の精度が高まります。特に季節変動の大きい京都市場では、年間を通じた実績データは非常に貴重です。
さらに許認可や設備が整っていることも大きな利点です。すでに営業許可を取得し、必要な設備が整った物件なので、追加投資や手続きの手間が大幅に削減されます。特に簡易宿所の許可取得は難易度が高いため、この点は大きなメリットとなります。
加えて、運営ノウハウの引継ぎができる点も重要です。売主から運営のコツや地域特有の情報、リピーター顧客の特徴などの貴重なノウハウを引き継ぐことができます。これらは独自に蓄積するには時間がかかる貴重な資産です。
民泊M&A物件を選ぶ際のポイントとしては、まず収益性と価格のバランスを見ることが重要です。過去1〜2年間の収益データを詳細に分析し、投資回収期間を計算しましょう。
さらに、立地条件の将来性も重要な判断基準です。現在の収益だけでなく、周辺エリアの開発計画や観光動向などを考慮し、将来的な価値上昇の可能性を評価しましょう。京都では、観光客の動線変化や新たな観光スポットの開発などが将来の収益に大きく影響します。
加えて物件の状態や設備の充実度にも注目しましょう。購入後すぐに大規模修繕が必要な物件は避けるべきです。特に水回りや構造部分のチェックは専門家に依頼することをお勧めします。古い町家物件の場合は特に慎重な調査が必要です。
関連:民泊M&Aが注目される理由とは?市場の動向や適切な価格設定の方法など解説!
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり、改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかっていませんか?さらに、厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか?
しかし、すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
そこでおすすめするのが、日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。

日本総合政策ファンドの最大の強みは、AI/DXテクノロジーを駆使した効率的なマッチングとデューデリジェンスです。お客様の投資条件や希望に最適な民泊物件を、膨大なデータベースから迅速に見つけ出します。以下のような価値ある資産を含む物件も多数取り扱っています。
- 旅館業法または特区民泊に基づく営業許可(年間365日運営可能)
- 即戦力となる清掃スタッフなどの運営体制
- 稼働開始に必要な家具家電や内装設備一式
さらに、物件だけでなく、運営ノウハウも一緒に取得できることが最大のメリットです。成功している民泊事業の運営方法、料金設定、集客戦略などの専門知識も継承できるため、民泊事業未経験の方でも安心して参入できます。
まずは無料で日本総合政策ファンドのコンサルタントに相談してみませんか?お客様の投資条件や希望を分析し、最適な民泊物件候補をご提案します。
まとめ
京都での民泊運営は、世界的な観光地としての強みを活かせば高い収益性が期待できるビジネスです。インバウンド需要の高さ、ホテル不足、町家という独自の文化資源、そして副業でも実現可能な収益性が大きな魅力となっています。利回りは一般的な賃貸物件の3〜5%と比較して8〜18%と高く、条件によってはそれ以上も可能です。
しかし、180日制限をはじめとする厳しい規制、高額な初期投資、文化的な摩擦、法令違反のリスクなど、克服すべき課題も多くあります。これらのリスクを回避するには、民泊開設代行サービスの活用や、すでに実績のある物件の購入といった戦略的なアプローチが効果的です。
京都の民泊市場は変化し続けていますが、地域の特性を理解し、専門家のサポートを受けながら計画的に進めることで、持続可能な収益を生み出すビジネスとなるでしょう。
\AIを活用した最先端の民泊特化のM&A仲介/
\ 日本総合政策ファンド /