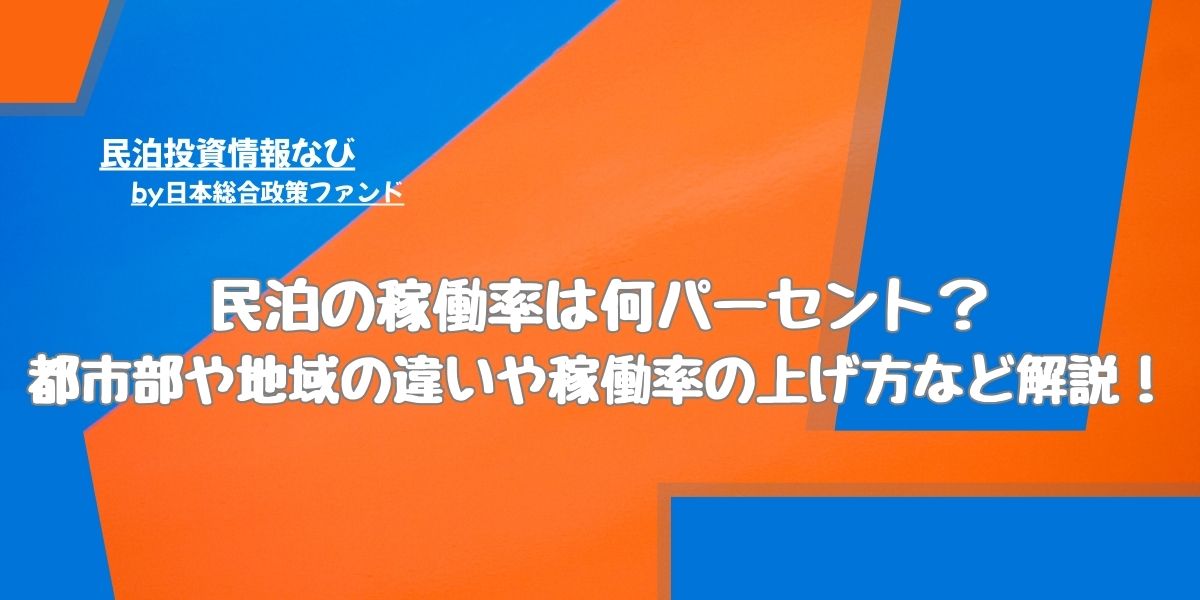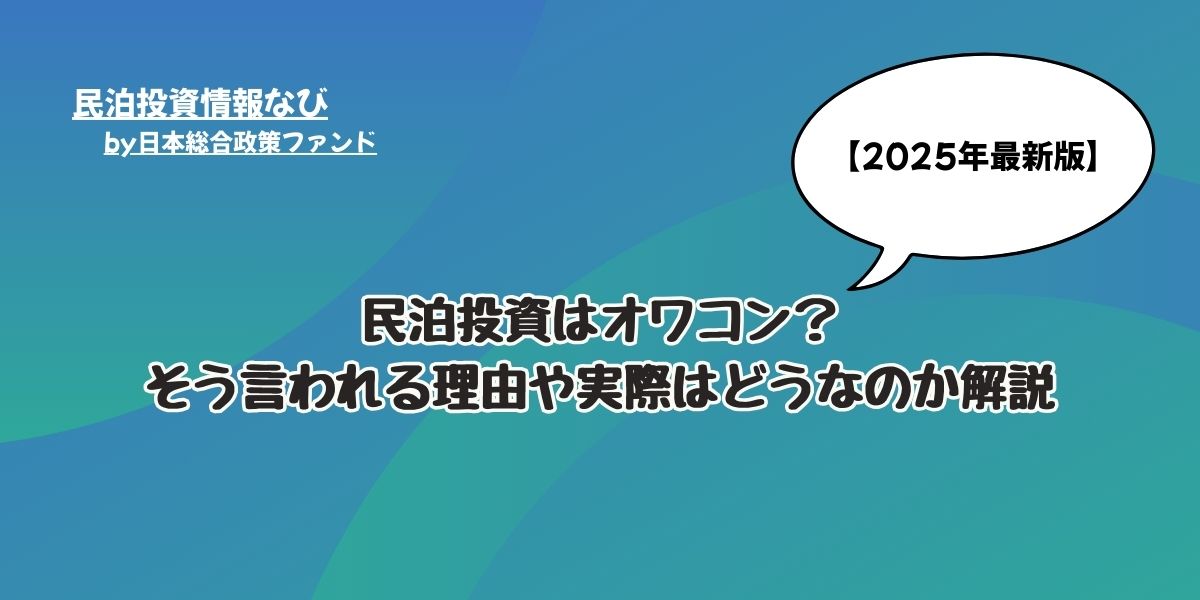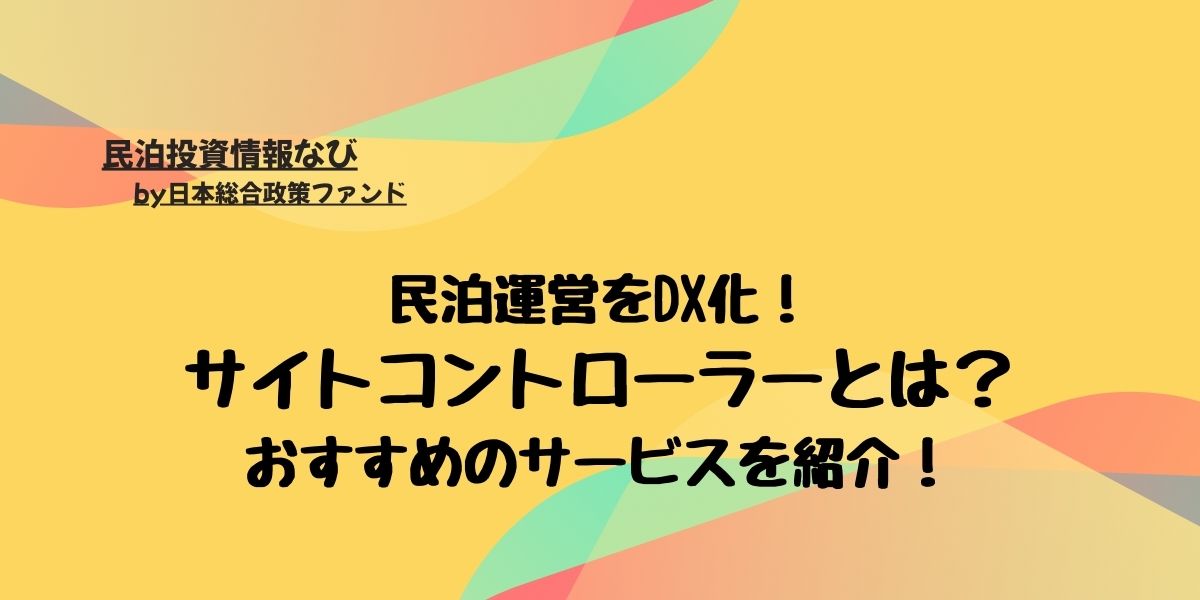民泊を運営する上で稼働率は収益に直結する重要な指標です。「自分の物件の稼働率は適正なのか」「もっと稼働率を上げるにはどうすればいいのか」という悩みを抱えるオーナーは少なくありません。
稼働率は物件タイプや立地によって大きく異なり、全国平均は50〜60%程度とされています。本記事では、都市部と地方の物件タイプ別稼働率の実態、収益への影響、変動する理由、具体的な向上策まで詳しく解説します。
関連:民泊投資はオワコン?そう言われる理由や実際はどうなのか解説
民泊の平均稼働率はどのくらい?

ここでは、民泊の平均稼働率について都市部と地方の物件タイプ別に詳しく見ていきましょう。
民泊物件の種類や立地によって稼働率には大きな差があります。日本全国の民泊市場を見ると、平均稼働率は約50〜60%程度です。東京や大阪などの大都市では観光客やビジネス需要が多いため高い稼働率を記録していますが、地方では観光シーズンによる波があり、年間平均では都市部より低くなる傾向があります。
同じエリアでも物件タイプによって稼働率に違いがあるのも見逃せないポイントです。
都市部:マンションタイプ
都市部のマンションタイプの民泊は、平均稼働率が60〜70%と全国の中でも特に高い水準を維持しています。これは主に、交通アクセスの良さと宿泊施設としての利便性が高く評価されているためです。
東京や大阪などの主要都市では、地下鉄やバスなどの公共交通機関へのアクセスが容易なマンションは観光客やビジネス客から特に人気があります。駅から徒歩5分以内の物件では稼働率が70%を超えることも珍しくありません。
マンションタイプの民泊はチェックインの自由度が高いこともメリットです。多くの物件ではスマートロックを導入しており、ゲストは自分の都合のいい時間に到着できます。
ただし、同じ都市部でも立地条件によって稼働率には差があります。主要観光スポットや繁華街に近いエリアでは稼働率が高くなる傾向がありますが、郊外に行くほど稼働率は徐々に下がり、都心から離れた場所では50%程度まで下がることもあります。
関連:マンションで民泊を始めることができる!?メリット、デメリットなど解説!
都市部:一軒家タイプ
都市部の一軒家タイプの民泊の平均稼働率は約50〜60%で、マンションタイプと比べるとやや低めです。特徴的なのは一棟まるごと貸し出す形態のため、1泊あたりの単価がマンションタイプより高く設定できる点です。
都市部の一軒家タイプは、家族連れやグループ旅行者に特に人気があります。複数の部屋があり、キッチンやリビングスペースを共有できるため、長期滞在のゲストに適しています。
京都や金沢などの伝統的な町並みが残る地域では、町家を改装した一軒家タイプの民泊が外国人観光客に非常に人気です。こうした物件は日本の伝統的な生活様式を体験できるとして高評価を得ており、稼働率も60〜70%と比較的高い水準を維持しています。
都市部の一軒家タイプは物件数自体が少ないため、競合が少なく、独自性を打ち出せば高い稼働率を達成することも可能です。和モダンのインテリアや、ユニークな設備を備えた物件は予約が集中する傾向があります。
地方:リゾート物件
地方のリゾート物件の平均稼働率は約40〜50%で、都市部と比べるとやや低めです。観光シーズンには80%を超える高稼働率を記録する一方、オフシーズンには20〜30%まで下がることもあります。
リゾート物件は1泊あたりの単価が高く設定できるため、稼働率が低くても収益性を確保できるケースも少なくありません。温泉付きの物件や、オーシャンビューなど特別な眺望が楽しめる物件は、高単価でも予約が入りやすい傾向があります。
関連:別荘を民泊として貸し出せる!?メリット、デメリット、必要なものなど解説!
地方:古民家
地方の古民家タイプの民泊の平均稼働率は約30〜40%程度で、他の物件タイプと比べると低めです。
古民家民泊の魅力は、その独自性と文化的価値にあります。日本の伝統的な建築様式や生活文化を体験したいという外国人観光客からの支持が特に高く、インバウンド需要に支えられています。
地方の古民家は交通アクセスが不便なことが多いというデメリットがありますが、それを逆手に取り「隠れ家」としてのブランディングに成功している物件もあります。自然豊かな環境にある古民家は、都会の喧騒から離れてゆっくりと過ごしたいゲストに人気です。
古民家ならではの魅力として「一棟貸し切り」という形態も多く、プライバシーを重視するファミリー層やグループ客に適しています。
関連:空き家を民泊にできる?メリットやデメリット、始め方など解説
稼働率が収益に与える影響

ここでは、稼働率が収益性にどのように影響するのか、具体的なメカニズムと効果について詳しく見ていきましょう。
稼働率は単なる数字以上の意味を持ちます。稼働率は実際に物件が稼働している日数の割合を示すだけでなく、事業全体の健全性や将来性を映し出す鏡でもあります。
関連:高収益が見込めるAirbnb投資とは?賃貸運営との違いなど解説!
収益がグンとアップ!
民泊の稼働率が10%上昇すると、収益はそれ以上に増加します。これは単純な比例関係ではなく、相乗効果によるものです。
稼働率が高まると「需要と供給」の原則により、宿泊料金を適正に引き上げられる可能性が高まります。人気の高い物件は適切な価格戦略により、1泊あたりの単価も上げられます。
稼働率が高い物件は「連泊」の可能性も高まります。連泊はチェックイン・チェックアウト対応やクリーニングの頻度が減るため、運営コストの削減につながります。1回のクリーニングコストが5,000円だとすると、2泊連泊が増えるだけで、1泊あたりのコストは2,500円に半減します。
稼働率の高い物件は価格交渉に強い立場を取れます。割引要求に対して毅然とした態度を保てるため、適正価格での予約が増え、結果的に収益性が向上します。
固定費を賢くカバーできる
民泊経営において避けられないのが「固定費」の存在です。家賃、ローン返済、インターネット回線料、管理システム利用料など、予約の有無にかかわらず発生する費用は意外と多く、収益を圧迫する要因となります。稼働率が高まれば、これらの固定費を効率よくカバーできます。
月間固定費が10万円の物件があるとします。稼働率30%(9日間稼働)の場合、1日あたりの固定費負担は約11,111円ですが、稼働率60%(18日間稼働)になると、1日あたりの負担は約5,556円と半分になります。同じ宿泊料金でも、稼働率が高いほど利益率が向上します。
重要なのが「損益分岐点」を超える稼働率の確保です。1泊15,000円の物件で月間固定費が10万円、変動費(クリーニング代など)が1泊あたり5,000円の場合、損益分岐点となる稼働率は約10日(約33%)です。これを超えれば黒字経営になりますが、下回れば赤字となります。
稼働率の向上は「規模の経済」をもたらします。複数物件を運営している場合、クリーニングスタッフの効率的な配置や、備品の一括購入による単価削減などが可能になります。
安定したキャッシュフローを獲得できる
稼働率が安定していると、キャッシュフローも安定します。民泊収入が毎月ある程度予測できるようになると、資金繰りの計画が立てやすくなります。
安定したキャッシュフローがあれば、突発的な修繕費や設備更新費にも余裕を持って対応できます。エアコンの故障やボイラーの交換といった予期せぬ出費が生じても、通常の収入内でカバーできる余裕があれば、事業の継続性は大きく向上します。民泊物件をM&Aする場合でも、高稼働率な物件の場合高いバリュエーションで評価されます。
稼働率が変動する理由とは?

ここでは、民泊の稼働率が変動する主な理由を詳しく見ていきましょう。
「なぜ今月は予約が少ないのか」「なぜ特定の時期だけ予約が集中するのか」という疑問を持ったことはありませんか。稼働率の変動は、予測不可能な要素もありますが、多くは分析と対策が可能な要因によるものです。
季節要因
稼働率を左右する最も大きな要因の一つが「季節性」です。観光地では特にこの影響が顕著に表れ、ハイシーズンとオフシーズンで稼働率が半減することも珍しくありません。
京都の民泊では桜の季節(3月下旬〜4月上旬)と紅葉の季節(11月)に稼働率が90%近くまで上昇する一方、真夏や厳冬期は50%程度まで下がることがあります。沖縄のビーチリゾートなら夏季が最盛期となり、北海道のスキーリゾートでは冬季に稼働率がピークを迎えます。地域の特性によって「良い時期」と「悪い時期」は大きく異なります。
地域の大型イベントも稼働率に大きな影響を与えます。札幌雪まつり期間中の札幌市内の民泊は軒並み満室になりますし、青森ねぶた祭りの時期も同様です。
シーズンオフの対策も重要です。スキーリゾートの夏季には「避暑地」としての魅力をアピールしたり、海辺のリゾートでも冬季は「温泉」や「グルメ」といった別の魅力を前面に出すことで、オフシーズンの稼働率を底上げすることができます。
立地条件
立地条件は民泊の稼働率を大きく左右する不変の要素です。「交通アクセス」は予約の決め手となることが多く、駅やバス停から徒歩10分以内の物件と20分以上の物件では、稼働率に20%以上の差がつくこともあります。
アクセスの良さは特に海外からの観光客にとって重要で、公共交通機関の利便性が高い物件ほど選ばれる傾向があります。大阪市内の調査では、地下鉄駅から徒歩3分以内の民泊は、同じエリアの徒歩10分以上の物件と比べて稼働率が平均25%高いというデータもあります。
周辺環境も稼働率に大きく影響します。観光スポットや商業施設、飲食店が充実しているエリアの物件は、滞在の利便性が高く評価され、高い稼働率を維持しやすいです。
治安の良さも重要な要素です。女性の一人旅や家族連れのゲストは安全性を重視するため、治安の良いエリアの物件は口コミでも高評価を得やすく、リピーターも増える傾向があります。
競合物件の増加
同じエリア内で民泊物件が増えると、稼働率に影響が出ます。供給過多の状態になれば、価格競争が起こり、稼働率の低下や単価の下落につながる可能性があります。
競合に対抗するには、自分の物件の差別化が重要です。独自の魅力やサービスを打ち出すことで、競合との違いを明確にし、選ばれる物件になる必要があります。
関連:民泊運営に差別化が必須!どのように差別化を行えばいい?
施設の魅力
物件自体の魅力度も稼働率を左右する重要な要素です。清潔さ、設備の充実度、インテリアのセンスなどは、ゲストの満足度と直結し、口コミ評価や再予約率に大きく影響します。
まず基本となるのが「清潔さ」です。Airbnbの調査によると、「清潔さ」の評価が5段階中4.5以上の物件は、3.5以下の物件と比べて予約率が約40%高いというデータがあります。バスルームやキッチン、寝具の清潔さは、ゲストが最も注目する部分です。
快適な寝具も重要な要素です。質の高いマットレスやピローは初期投資はかかりますが、「とても良く眠れた」という評価は口コミでも大きなアピールポイントとなります。
キッチン設備の充実度も長期滞在を検討するゲストにとって重要なポイントです。調理器具や食器が充実していれば、「自炊できる」という点が魅力となり、3泊以上の長期滞在の予約増加につながります。
チェックインの柔軟性やホストの対応の良さも稼働率向上につながります。
OTAのアルゴリズム
AirbnbやBooking.comなどの主要プラットフォームでは、様々な要素を基に物件の表示順位が決定されます。重要視されるのが「レスポンス率」と「応答速度」です。Airbnbでは問い合わせに対して15分以内に返信すると「迅速な応答」というバッジが付与され、検索結果での表示順位が上がる傾向があります。
次に重要なのが「予約承認率」です。Airbnbでは、予約リクエストを断る回数が多いと検索順位が下がる傾向があります。直前のキャンセルはアルゴリズム上のペナルティが大きいため、カレンダーの管理を徹底することが大切です。
「レビュースコア」も検索順位に大きく影響します。「清潔さ」「コミュニケーション」「チェックイン」の評価が重視される傾向があります。5段階評価で4.7以上のスコアを維持している物件は、検索結果の上位に表示されやすくなります。
価格設定もアルゴリズムに影響します。極端に高すぎる、または安すぎる価格設定は、アルゴリズム上で不利になる可能性があります。競合物件と比較して適正な価格帯に設定することが重要です。「スマートプライシング」機能を活用し、需要に応じて価格を自動調整することで、稼働率を最適化している事例も多くあります。
写真の質と数も重要な要素です。プロのカメラマンによる高品質な写真を20枚以上掲載している物件は、スマートフォンで撮影した数枚の写真しかない物件より、予約率が30%以上高いというデータもあります。
OTAのアルゴリズムは定期的に更新されるため、常に最新の傾向を把握することが大切です。
関連:AirbnbのSEO対策とは?上位表示するために必要!?コツなどを解説!
民泊稼働率を向上させる具体的な方法とは?

ここでは、実践的で効果の高い民泊稼働率向上の方法を具体的に見ていきましょう。
民泊の稼働率向上は、単に「もっと予約を取りたい」という願望ではなく、具体的な戦略と実行が必要です。多くのオーナーは「とにかく料金を下げれば予約は増える」と考えがちですが、それは一時的な対症療法に過ぎません。持続可能な稼働率向上には、市場を理解し、自分の物件の強みを活かす総合的な戦略が必要です。
需要に対応した価格を設定する
民泊の価格設定は、「芸術」と「科学」の両面を持つ作業です。適切な価格戦略は稼働率と収益を同時に最適化できますが、誤った価格設定は両方を損なう危険性もあります。ここで重要なのが「イールドマネジメント」と呼ばれる手法です。
イールドマネジメントとは、需要予測に基づいて価格を変動させることで収益を最大化する方法です。航空業界やホテル業界で広く活用されています。需要が高い時期は価格を上げ、需要が低い時期は価格を下げるという基本戦略です。
曜日ごとの価格差も重要です。多くの地域では、金曜・土曜の宿泊需要が高いため、平日より20〜30%高い価格設定が可能です。平日の稼働率を上げるためには、3泊以上の連泊割引を設定するのも効果的です。連泊はクリーニングなどのコスト削減にもつながるため、少し割引をしても利益率は維持できます。
価格設定を最適化するには、「最低2泊」などの滞在条件の設定も検討すべきです。清掃コストが高い物件や、チェックイン対応に時間がかかる物件では、1泊のみの予約を避けることで、運営効率と収益性を高められます。見かけの稼働率は下がっても、実質的な収益と効率は向上するケースも少なくありません。
競合分析も価格戦略の重要な要素です。競合物件の価格を定期的に調査し、自分の物件の相対的な位置づけを理解することが大切です。
ターゲット層に合わせた施設にする
民泊市場が成熟し競争が激化する中、「誰でも歓迎」という万人向けのアプローチでは高い稼働率を維持するのが難しくなっています。特定のターゲット層に焦点を当て、そのニーズに徹底的に応える「ニッチ戦略」が効果を発揮します。
まず必要なのが、自分の物件に最適なターゲット層の見極めです。立地や物件の特性から、最も需要が見込める層を特定しましょう。
外国人観光客をターゲットにする場合は、言語対応と文化体験が鍵となります。多言語の案内表示や説明書を用意し、日本文化を体験できる要素(浴衣、お茶セット、畳スペースなど)を取り入れると効果的です。
差別化のポイントとして、「地域性」の活用も効果的です。沖縄の物件ならシーサーや琉球ガラスを取り入れた内装、京都なら町家風の要素を取り入れるなど、「ここでしか体験できない」要素を提供することで、同価格帯の標準的な物件より高い予約率を実現できます。
マーケティングを強化する
民泊市場の競争が激化する中、単に「良い物件」を提供するだけでは高い稼働率は見込めません。効果的なマーケティング戦略が、あなたの物件を同じエリアの競合から際立たせる重要な役割を果たします。
まず第一歩となるのが、明確な「コンセプト」の確立です。「ただの宿泊施設」ではなく、「〇〇を体験できる場所」というストーリー性を持たせることで、予約者の心に残る物件になります。
コンセプトを視覚的に表現する写真の質にもこだわりましょう。プロのカメラマンによる撮影は初期投資として価値があります。
物件説明文もマーケティングの重要な要素です。単なる設備リストではなく、「この物件で過ごすとどんな体験ができるか」を具体的に伝える文章が効果的です。
OTAプラットフォーム内でのSEO対策も忘れてはなりません。Airbnbなどの検索アルゴリズムでは、タイトルや説明文中のキーワードが重要です。東京の物件なら「東京、新宿、駅近、清潔」などの検索されやすいキーワードを自然に盛り込むことで、検索結果の上位表示につながります。
「スーパーホスト」や「プレミアムパートナー」などのステータス獲得も重要な目標です。これらのバッジは検索順位向上だけでなく、予約率自体も15〜20%引き上げる効果があります。
運営を効率化してコストを削減する
民泊運営の効率化とコスト削減は、単に支出を減らすためだけではなく、サービス品質の向上と稼働率アップのためにも重要です。人的リソースとコストを最適化することで、より多くのエネルギーをゲスト満足度向上に振り向けられます。
まず取り組むべきなのが「チェックイン・チェックアウトの自動化」です。スマートロックの導入により、物理的な鍵の受け渡しが不要になり、24時間チェックインが可能になります。初期投資は2〜5万円程度かかりますが、時間的制約がなくなることで予約機会の損失を防げます。
関連:民泊でスマートロックを導入するメリット、デメリットとは?
ゲストとのコミュニケーション効率化も重要です。テンプレートメッセージの活用や、チャットボットの導入により、よくある質問に迅速に対応できます。Airbnbなどが提供する「自動メッセージ」機能を活用すれば、予約確定時や到着前日、チェックアウト後などに自動でメッセージを送信できます。これにより応答率と評価スコアが向上し、検索順位アップにもつながります。
清掃管理の効率化も見過ごせません。清掃チェックリストの作成とタブレット等での共有により、清掃品質の標準化と時間短縮が可能です。複数物件を運営している場合は、清掃スケジュールの最適化により移動時間と人件費を削減できます。
関連:サイトコントローラーとは?民泊運営に必須の理由とおすすめ5選を徹底比較
まとめ
民泊の稼働率は単なる数字ではなく、事業の健全性を示す重要な指標です。全国平均で50〜60%と言われる民泊の稼働率ですが、都市部のマンションタイプでは60〜70%、地方のリゾート物件では季節変動を伴いながら40〜50%と、物件タイプや立地によって大きく異なります。稼働率の向上は単純な収益アップだけでなく、固定費の効率的なカバーや安定したキャッシュフローの確保にもつながります。
稼働率が変動する理由は、季節要因や立地条件、競合状況、施設の魅力度、OTAのアルゴリズムなど多岐にわたりますが、これらを理解し対策を講じることで改善が可能です。
稼働率を上げるための具体的な向上策としては、需要に応じた柔軟な価格設定、ターゲット層に特化した施設づくり、効果的なマーケティング戦略、そして運営の効率化が挙げられます。