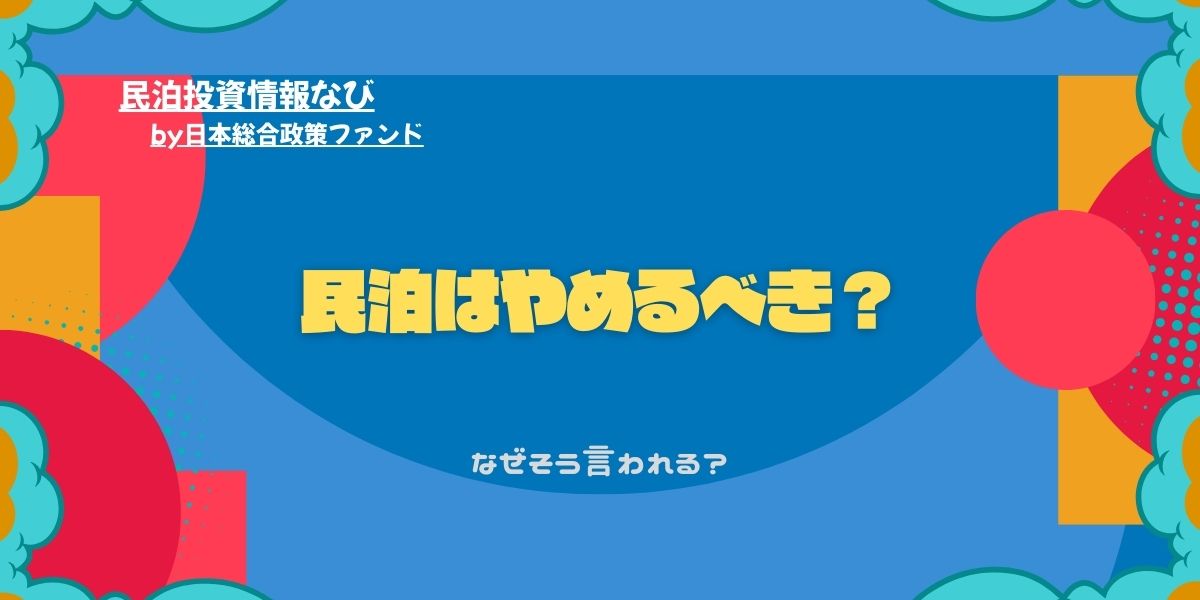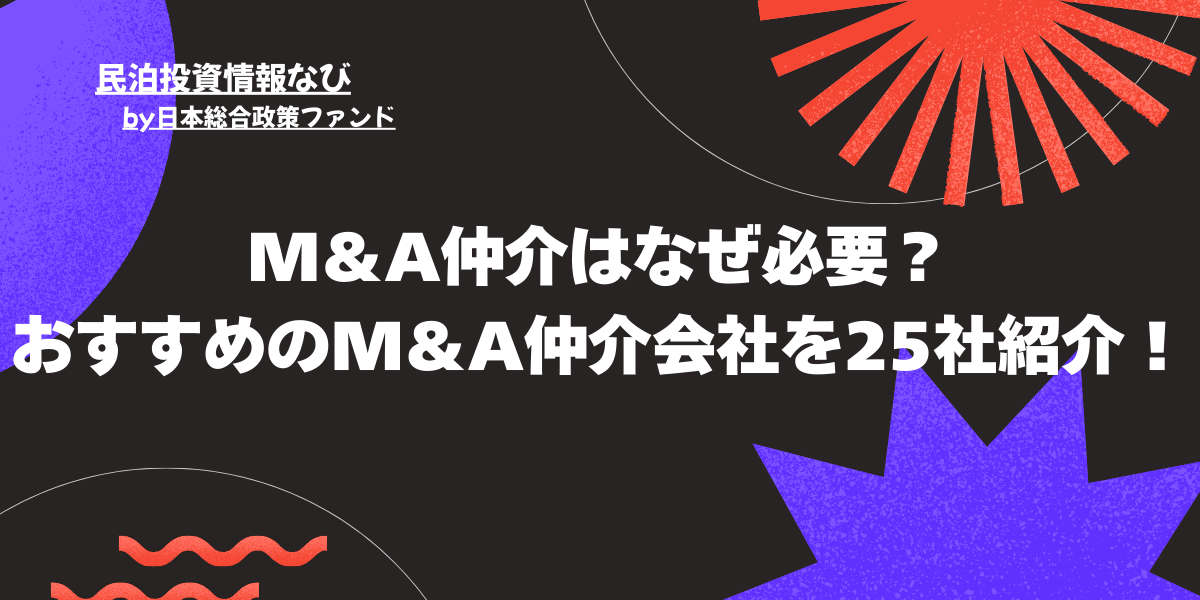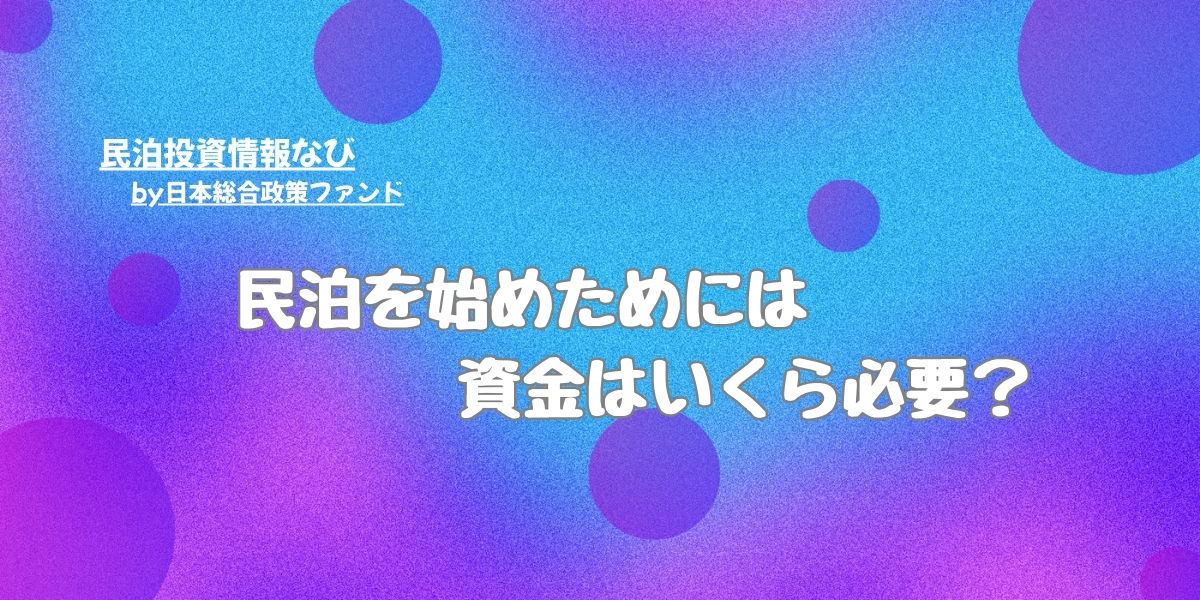民泊運営に興味を持ちながらも「本当に稼げるのか」「リスクは大丈夫なのか」と不安を感じていませんか?インターネット上では「民泊運営はやめとけ」という声が多く聞かれ、実際に撤退を余儀なくされた投資家の体験談も数多く報告されています。
確かに民泊運営には魅力的な面もありますが、法規制の変更リスク、想定以上の運営負荷、収益の不安定性など、一般的な不動産投資とは全く異なる特殊なリスクが存在します。
この記事では、民泊運営の現実的なリスクと課題を詳しく解説します。
関連:民泊はオワコン?そう言われる理由や実際はどうなのか解説!
民泊運営は本当にやめるべき?なぜそう言われる?

民泊運営が「やめとけ」と言われる背景には、一般的な不動産投資や賃貸経営とは全く異なる特殊なリスクが存在するからです。実際に民泊運営を開始した多くのオーナーが、想定していた収益を得られずに撤退している現実があります。
特に2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行以降、規制強化により運営環境は一層厳しくなっています。また、2020年のコロナウイルスが流行した際に民泊物件の売却が大幅に増えました。
どのような理由があるのか見ていきましょう。
法規制が急に変わると運営が難しくなる
墨田区での民泊•旅館業の規制案が発表
主な影響
•住宅宿泊事業を行う期間は、月曜正午から金曜正午まで
•生活環境悪化を認識できる場所に常駐する義務
ただ、条例施行前にある施設に対しては適用対象外になります。そのため、墨田区で民泊などを始めたい場合は施行前に始めるべきです! pic.twitter.com/pooDpWZuJT
— 河原@民泊M&Aコンサルタント (@kawa_nohonsosei) August 29, 2025
また、民泊新法のように年間営業日数の上限が180日に設定されると、この規制だけでも収益は理論上半分以下になってしまいます。
初期投資が回収できないリスクもある
民泊運営における初期投資回収の困難さは、多くのオーナーが直面する深刻な問題です。表面的な収益予測と実際の運営結果との間には、しばしば大きなギャップが存在します。
収益が予測を下回る主な要因は稼働率の低迷です。多くの初心者オーナーは70%から80%の稼働率を想定しますが、現実的には50%から60%程度になることが珍しくありません。特に競合物件が増加している地域では、価格競争により単価も下落傾向にあります。
運営コストも想定以上に高額になりがちです。清掃費用は1回あたり5000円から8000円程度必要で、月20回の清掃で月額10万円から16万円のコストとなります。さらに水道光熱費、インターネット回線費用、火災保険料、管理会社への委託費用なども発生します。
さらに、コロナ禍では訪日外国人観光客の訪問がなくなり、多くの民泊物件が長期間空室状態となりました。反対に2025年現在は、インバウンド需要によって民泊の宿泊需要が増え、稼働率が高まっています。現在の市場環境は、投資資金を回収しやすい時期であると言えます。
想像以上に運営や管理の負担がある
清掃管理だけでも相当な負担です。ゲストがチェックアウトした後、次のゲストのチェックインまでの限られた時間内に室内清掃、ベッドメイキング、アメニティ補充、設備点検を完了させる必要があります。自分で清掃を行う場合、1回あたり3時間から4時間を要することも珍しくありません。
さらに、ゲスト対応の負担も深刻です。チェックイン方法の説明、鍵の受け渡し、Wi-Fiパスワードの案内、周辺施設の案内、騒音苦情への対応、設備故障時の緊急対応など、多岐にわたる業務が発生します。特に外国人ゲストが多い場合、言語の壁により対応時間がさらに長くなります。
まれに設備トラブルの対応も発生します。エアコンの故障、給湯器の不具合、Wi-Fi接続障害、排水管の詰まりなど、ゲスト滞在中に発生したトラブルは即座に対応しなければなりません。深夜や早朝のトラブルに発生することもあるため負担となっています。
これらの業務負担を軽減するため管理会社に委託することも可能ですが、売上の20%から30%程度の手数料が発生し、収益性が大幅に悪化します。その結果として、多くのオーナーが自分で運営せざるを得ない状況に追い込まれています。
季節やイベントによって収益が安定しない
季節変動の影響は地域によって異なりますが、一般的に春と秋の観光シーズンに収益が集中し、冬季や梅雨時期には大幅に収益が減少します。
イベント開催の有無による収益への影響も深刻です。東京オリンピック開催予定だった2020年には多くのオーナーが高収益を期待していましたが、コロナ禍による開催延期と外国人観光客の入国制限により、期待は完全に裏切られました。
しかし、ライブなどのイベントによってホテルの予約がとれない状況になるとホテル並の値段にしても宿泊されることがあります。
民泊と賃貸・ホテル運営の違い
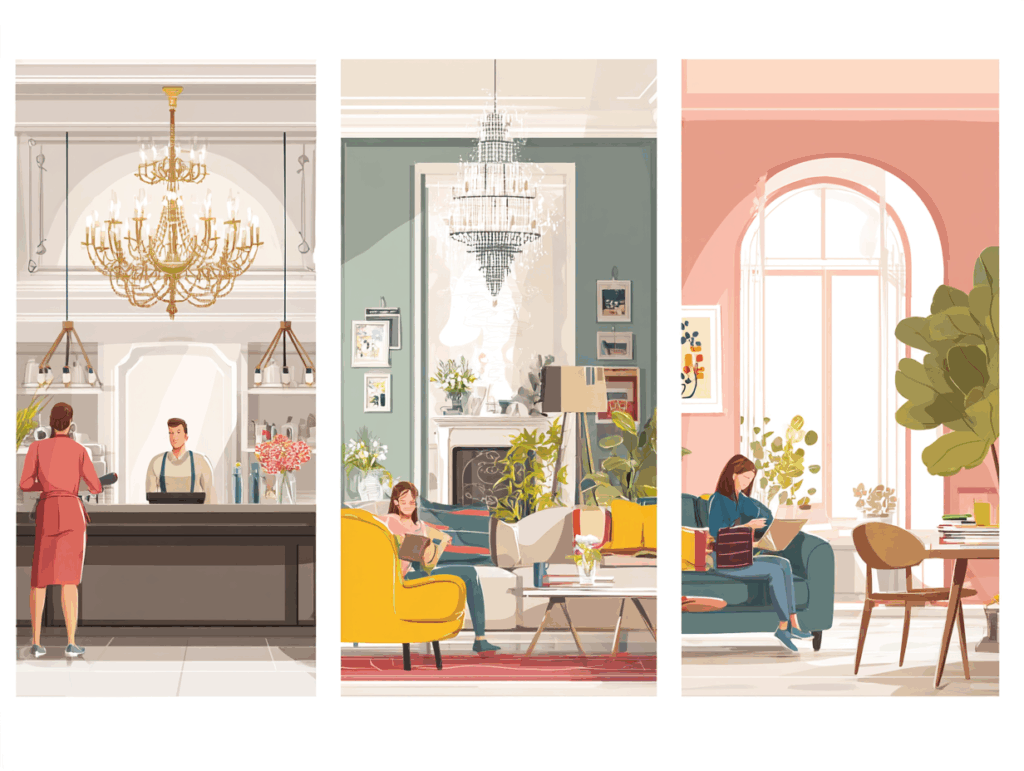
結論として、民泊運営は賃貸経営やホテル運営とは全く異なる事業モデルであり、それぞれに独特のリスクと収益構造があります。多くの方が民泊運営で失敗する理由は、賃貸経営の感覚で参入してしまうことにあります。
民泊と賃貸、ホテル運営との違いを見ていきましょう。
賃貸との違い
運営業務の負荷も大幅に異なります。賃貸経営では入居時と退去時、そして緊急時のみ対応が必要ですが、民泊ではゲストの入れ替わりごとに清掃、チェックイン対応、アメニティ補充が必要になります。
さらに、空室リスクの性質も全く異なります。賃貸では一度空室になると長期間続く可能性がありますが、その代わり入居者が決まれば長期安定となります。民泊では毎日が空室リスクの連続ですが、翌日には満室になる可能性もあります。しかし、この不確実性により資金計画が立てにくくなります。
ホテル運営との違い
民泊運営とホテル運営の最大の違いは、規模の経済とプロフェッショナルなサービス体制の有無です。ホテルでは専門スタッフによる組織的な運営が行われるのに対し、民泊では個人オーナーが小規模で運営するため、効率性とサービス品質の両面で不利になりがちです。
サービス提供体制の違いは顕著です。ホテルでは24時間フロントデスクがあり、専門的な研修を受けたスタッフがゲスト対応を行います。一方、民泊では個人オーナーが電話やメッセージで対応するため、迅速性と専門性の両面で限界があります。特に深夜早朝のトラブル対応では、個人オーナーには大きな負担となります。
コスト構造も根本的に異なります。ホテルでは固定費の割合が高く、稼働率向上により収益性が大幅に改善しますが、民泊では清掃費用などの変動費の割合が高く、稼働率向上によるメリットが限定的です。
ブランド力と集客力の差も重要な要因です。大手ホテルチェーンでは確立されたブランドと予約システムにより安定した集客が可能ですが、民泊では個別にOTAサイトで競争しなければなりません。同じ立地でも、有名ホテルブランドの客室単価が民泊の1.5倍から2倍になることも珍しくありません。
設備投資の効率性にも差があります。ホテルでは多数の客室で設備を共有するため、1室あたりの投資効率が高くなります。エレベーター、ロビー、レストラン、ランドリー設備などを多くの客室で共有できるためです。民泊では各室に個別の設備が必要で、投資効率が劣る傾向があります。
人材確保と育成の仕組みも違います。ホテルでは専門的な研修制度により人材を育成し、組織的なサービス提供が可能です。民泊では個人オーナーのスキルと時間に依存するため、サービス品質の維持が困難になりがちです。
民泊を運営している人の口コミや体験談
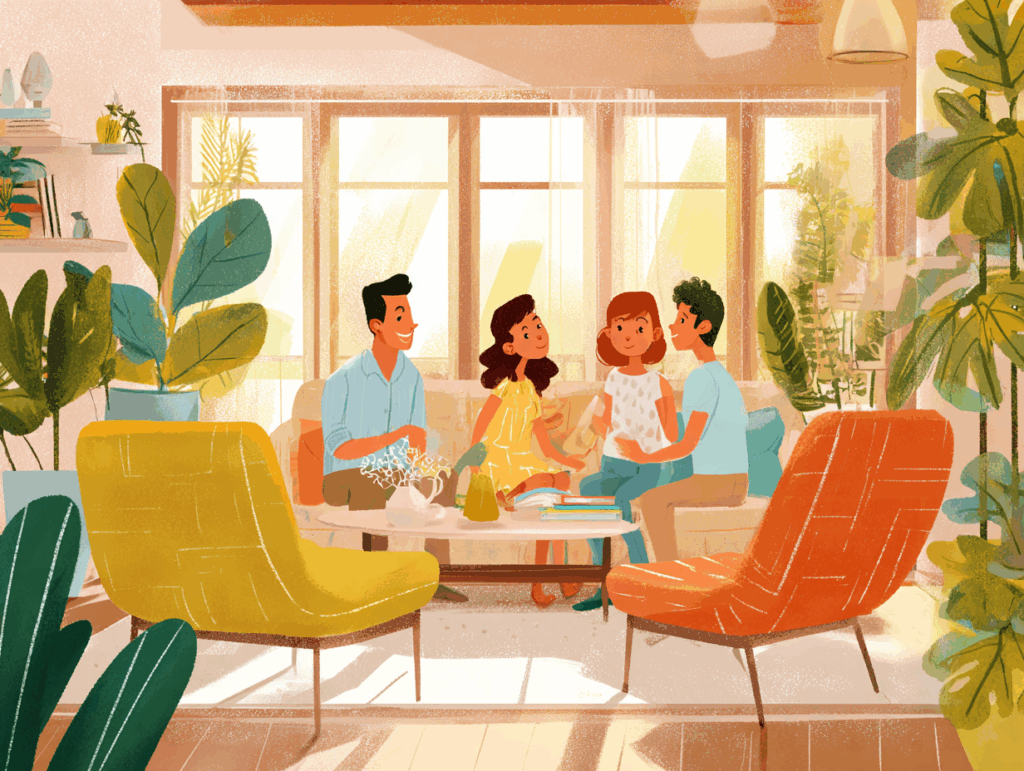
民泊運営している人の実際の運営者からの声を総合すると、民泊運営の最大の問題は「見えないコスト」と「予想以上の労働負荷」です。表面的な売上高だけを見れば魅力的に見えても、実際には手数料、清掃費、修繕費、税金などを差し引くと手元に残る利益は大幅に減少します。
特に個人で運営を始めた多くのオーナーが共通して指摘するのは、時間コストの高さです。ゲスト対応、清掃、予約管理などに費やす時間を時給換算すると、一般的なアルバイト以下の収入になってしまうケースも少なくありません。
運営代行会社に任せきりでほぼ利益なし
運営代行会社への委託は一見すると魅力的な解決策に見えますが、実際には手数料負担により収益性が大幅に悪化するケースが多発しています。多くのオーナーが「楽に稼げる」という期待で代行会社を利用しましたが、結果的に利益がほとんど残らない状況に陥っています。
大阪市内でワンルームマンションを民泊運営している会社員のケースでは、運営代行会社への委託により月売上20万円のうち手数料として6万円、清掃費として4万円、その他諸費用として3万円が差し引かれ、手元に残るのは月7万円程度という結果になりました。
運営代行会社の手数料体系は複雑で、基本的な運営代行手数料として売上の20%から30%に加え、清掃費、リネン交換費、消耗品補充費、修繕対応費などが別途請求されます。さらに予約サイト手数料やシステム利用料なども発生し、総合的な手数料率は売上の40%から50%に達することも珍しくありません。
この場合は、自社にあった運営代行を選ぶ必要があります。手数料体系がどれくらいなのかについて注意する必要がありますが、サービス内容についても注意しましょう。運営代行の中にはサービスの質が低く、稼働率の低下を引き起こすことも少なくありません。
副業で運営し、利益が出ても負担が大きく困っている
特に、緊急対応の発生も副業運営者には大きな負担となっていました。深夜にエアコンが故障した場合や、早朝に鍵が開かないトラブルが発生した場合、即座に対応しなければゲストに重大な迷惑をかけることになります。
副業として継続可能な民泊運営を実現するには、相当な効率化と割り切りが必要です。しかし、ゲストサービスの質を下げれば評価が悪化し、稼働率低下につながるため、結果として高い負担を維持せざるを得ない構造的な問題があります。そんな時には運営代行を使用すべきですが、収益は減少します。しかし、資産運用の手段として民泊を運営するなら運営代行を使用すべきです。
撤退や売却を決断する基準は?

結論として、民泊運営からの撤退判断は感情的な判断ではなく、明確な数値基準と将来予測に基づいて行うべきです。多くのM&A事例を分析すると、撤退タイミングを逸したことで損失が拡大するケースが圧倒的に多いからです。
実際の撤退事例を見ると、早期撤退により損失を最小限に抑えた成功例と、判断を先延ばしして大きな損失を被った失敗例が明確に分かれています。
どのような時に決断すべきでしょうか?
収益性が悪化し赤字が続く
さらに、累積損失額も重要な判断基準です。初期投資額の20%に相当する累積赤字が発生した時点で本格的な撤退検討を開始し、30%に達した時点で撤退実行というルールを設定している投資家もいます。
法改正や条例で運営継続が困難になる時
法規制変更による撤退判断は、施行前の情報収集段階から準備する必要があります。自治体の議会動向や条例案の公表時点で撤退可能性を検討し、規制内容が確定した時点で迅速に判断することが損失最小化の鍵となります。
民泊新法施行時には、180日規制により理論上最大50%の収益減少が確実視されました。この時点で多くの賢明な投資家が撤退を決断しましたが、「何とかなる」と考えて継続した投資家の多くが後に大きな損失を被りました。
特に近年では自治体条例による追加規制は特に注意が必要です。住居専用地域での平日営業禁止、学校周辺での営業禁止、営業時間制限などの条例が成立した場合、事実上の営業停止状態となります。
近隣住民からの反対運動が激化している地域では、将来的な規制強化リスクが高まり、実際に特区民泊であった大阪府の一部の地域では規制が強化されました。住民説明会での反対意見が多数を占めた場合や、自治体に対する請願書が提出された場合は、早期撤退を検討すべきタイミングです。
清掃や管理の負担が限界を超えた
運営負荷による撤退判断は、数値化が困難な要素が多いものの、心身の健康を害するレベルに達した場合は即座に撤退すべきです。長期的な健康被害は金銭的損失以上に深刻な問題となるからです。
また。運営業務に対する情熱や楽しさを完全に失った状態も撤退のサインです。民泊運営が単なる苦痛になった時点で、経済的利益があっても継続する意味は失われています。人生の質的向上を考慮すれば、撤退が最適な選択となります。
まとめ
民泊運営は表面的な収益性とは裏腹に、多くの構造的な問題を抱えています。法規制の頻繁な変更、初期投資回収の困難さ、想定以上の運営負荷、収益の不安定性など、個人投資家には厳しい現実が待ち受けています。
実際の運営者の体験談からも明らかなように、運営代行会社への委託では手数料負担により利益がほとんど残らず、個人運営では時間的負担が本業や家庭生活に深刻な影響を与えます。賃貸経営やホテル運営と比較しても、民泊は労働集約性が高く効率性に劣る投資手法といえます。
撤退判断については、感情的な判断ではなく明確な数値基準を設定することが重要です。累積損失が初期投資の30%に達した場合、6ヶ月連続の赤字が続いた場合、週40時間を超える労働負荷が継続した場合は、迷わず撤退を検討すべきでしょう。
運営を新たに考えている人は、投げ売りされる物件を購入することができるチャンスかもしれません。
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり、改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかっていませんか?さらに、厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか?
しかし、すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
そこでおすすめするのが、日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。