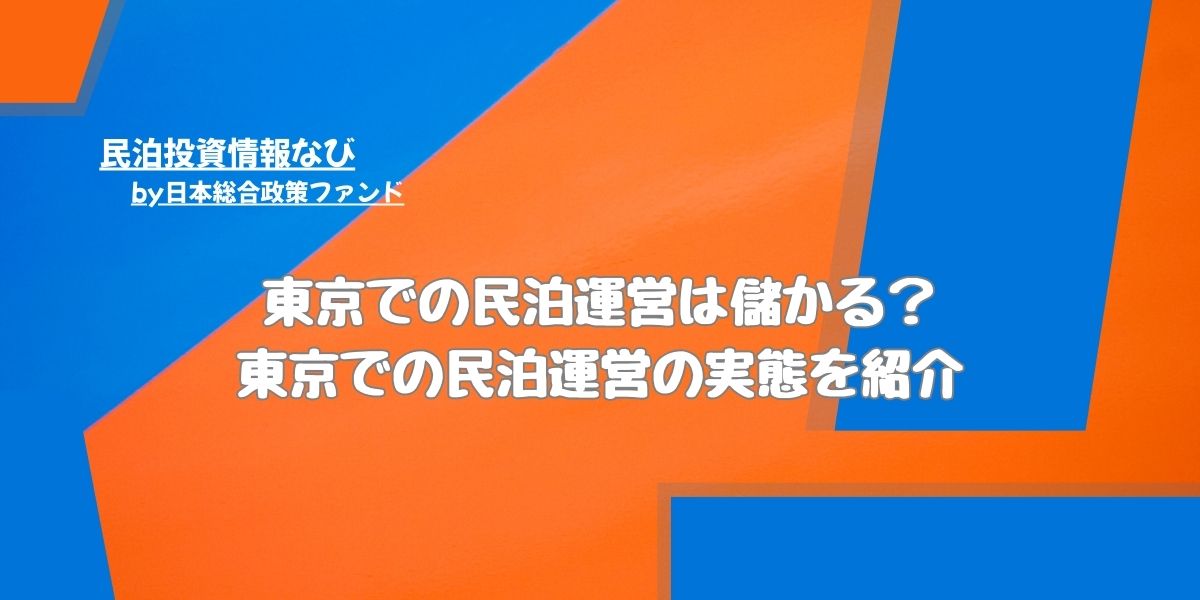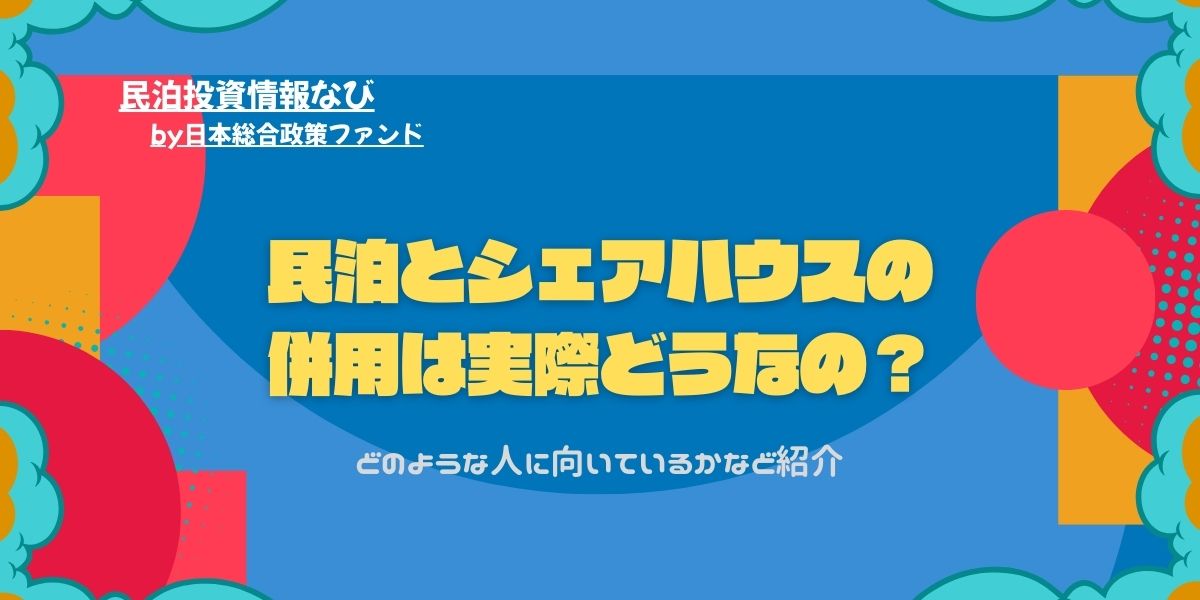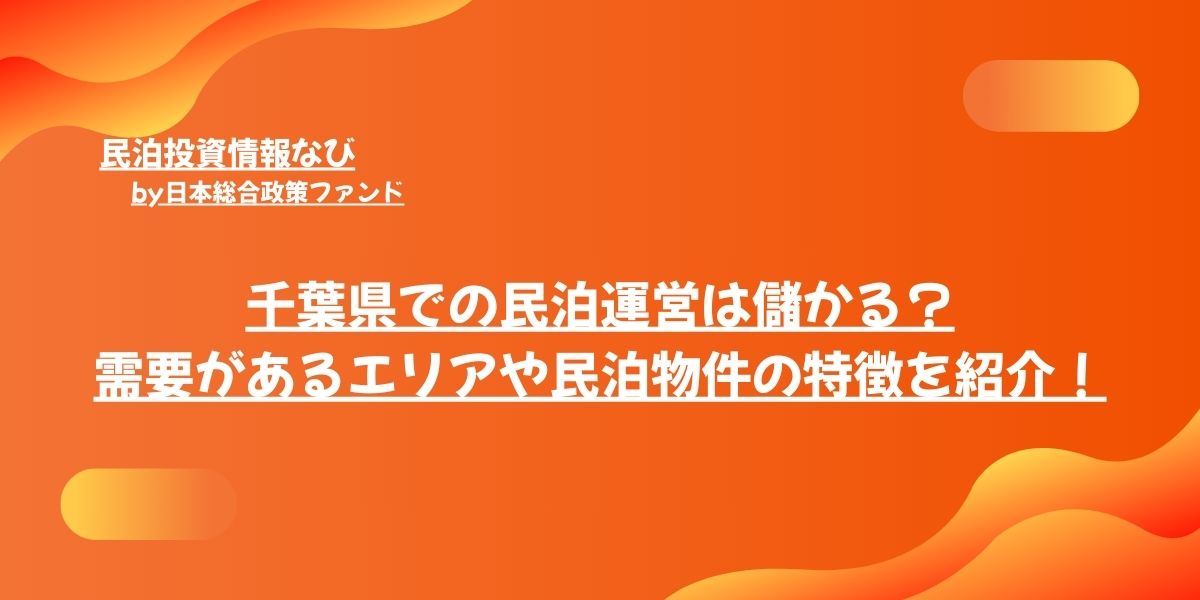「東京で民泊を始めたら本当に儲かるの?」「初期投資はどのくらい必要?」「リスクは何があるの?」民泊ビジネスに興味はあるものの、実態がわからずに踏み出せないでいませんか。
東京という大都市での民泊運営は、高い収益が期待できる反面、競争の激しさや法規制の複雑さなど独自の課題も抱えています。しかし、戦略的に取り組めば安定した収益源になり得るのは事実です。
この記事では、東京での民泊ビジネスの実際の収益性から成功のポイント、見落としがちなリスク、さらには効率的な始め方まで詳しく紹介します。
\AIを活用した最先端の民泊特化のM&A仲介/
\ 日本総合政策ファンド /
東京での民泊運営は本当に儲かる?

ここでは、東京での民泊運営の収益性について詳しく見ていきましょう。
東京での民泊運営は、戦略的に取り組めば安定した収益源になり得ます。世界有数の観光地である東京では、宿泊需要が依然として高い水準を維持しているためです。
正しい戦略と運営で取り組めば、十分に収益性のあるビジネスになり得るでしょう。東京は国際的な観光都市であり、今後もインバウンド需要の増加が見込まれることから、長期的な視点で見れば成長性のある市場といえます。
都心部で賃貸ではなく民泊運営が選ばれる理由は?

ここでは、多くの物件オーナーがなぜ長期賃貸ではなく民泊運営を選ぶのか、その理由について詳しく見ていきましょう。
物件オーナーや不動産投資家が民泊運営を選ぶ背景には、収益性の高さだけでなく、東京という都市の特性を活かした様々なメリットがあります。
賃貸に比べて高い収益性が期待できる
民泊は需要と供給のバランスに応じて柔軟に料金設定ができる大きなメリットがあります。大型イベント開催時や観光シーズンのピーク時には通常の1.5倍から2倍の料金設定も可能です。これは賃貸では得られない収益チャンスといえます。
物件の魅力を高めることで直接的に収益アップにつなげられる点も特徴です。内装のグレードアップやサービスの充実により宿泊料を上げることができます。賃貸では家賃の値上げは容易ではなく、設備投資をしても家賃に反映させるのは難しい場合が多いのです。
関連:【不動産投資】民泊投資と賃貸経営どちらがいい?管理や利益率、リスクなど解説
アクセスの良さを活かして集客しやすいため
山手線沿線の物件であれば、主要観光地へのアクセスの良さをアピールポイントにできます。浅草から東京スカイツリー、上野公園、秋葉原へは数分で移動可能です。新宿や渋谷からは都内各所へのアクセスが容易といえます。
民泊予約サイトの検索アルゴリズムでは、駅からの距離や主要観光地へのアクセスが重視される傾向にあります。東京の民泊物件は、アクセス面での優位性により予約サイト上で上位表示されやすく、結果として高い稼働率を維持しやすいのです。
関連:渋谷で民泊を始める方法とは?始めるメリット、デメリット、必要なものなど解説
運営代行を利用すれば無人で高利回りな運用ができるため
東京には数多くの民泊運営代行会社が存在し、物件オーナーは実質的にほぼ無人で民泊事業を展開できます。これは多忙なビジネスパーソンや遠方に住んでいる投資家にとって大きな魅力です。
運営代行会社は、予約管理からゲスト対応、清掃、メンテナンスまで一括して請け負ってくれます。代行会社によっては24時間体制でのゲスト対応や多言語サポートも提供しており、オーナー自身が外国語を話せなくても外国人観光客を受け入れることが可能です。
代行料金は一般的に売上の15%程度ですが、人件費と時間的コストを考えれば十分に元が取れる投資といえるでしょう。
関連:東京のおすすめ民泊運営代行会社6選!東京で運営代行を使用するメリットとは?
副業として賃貸物件を借りて民泊運営を始めることができるため
東京の民泊市場のもう一つの特徴は、必ずしも不動産を所有していなくても参入できる点です。賃貸物件を借り上げて民泊として運営するビジネスモデルが広がっています。これにより初期投資を抑えながら民泊事業に参入できるため、副業としての人気が高まっています。
通常の賃貸契約と民泊での収入の差額が利益となります。月額10万円で借りたマンションを民泊として運営し、月額25万円の収入が得られれば、経費を差し引いても月5万円から10万円の利益を得られる可能性があります。
物件購入のための多額の資金や住宅ローンが不要な点が魅力です。そのため20代や30代の若い世代でも比較的参入しやすく、副業としての収入源を確保できます。固定資産税や大規模修繕などの長期的なコストを気にする必要もありません。
東京での民泊運営をするリスクは?

ここでは、東京で民泊を運営する際のリスクについて詳しく見ていきましょう。
東京で民泊を運営する際には、高い収益性とともに様々なリスクが存在します。収益だけを見て参入を決めてしまうと、後々思わぬトラブルに見舞われることになりかねません。民泊ビジネスを長期的に成功させるためには、これらのリスクを事前に理解し適切な対策を講じておくことが不可欠です。
法規制・行政指導リスク
法令遵守のために必要な設備投資も見逃せません。火災報知器や避難経路の確保、非常灯の設置など消防法に基づく設備が必要となり、これらの初期コストは50万円程度かかることもあります。定期的な設備点検や報告義務もあり、継続的なコストと手間が発生します。
法律違反が発覚した場合のペナルティも厳しく、無許可営業には100万円以下の罰金が科される可能性があります。近隣からの通報により立入検査が行われることもあり、違反が発覚すると営業停止処分を受けることもあります。
関連:東京23区の民泊上乗せ条例を完全解説|区ごとの営業制限と対策
近隣住民とのトラブル
東京のような人口密集地域では、近隣住民とのトラブルが深刻な問題になりやすいです。特にマンションでの民泊運営では、隣接する住民の生活に直接影響を与える可能性があります。
最も多いトラブルは騒音問題です。外国人観光客の生活習慣の違いから、深夜の会話や足音が騒音として苦情につながることがあります。
ゴミ出しルールの不徹底も問題になりがちです。東京のゴミ分別は複雑で、外国人ゲストにとっては理解しづらいものです。分別されていないゴミや指定日以外の日に出されたゴミにより、管理組合やご近所からクレームが来ることもあります。
関連:民泊はなぜ近隣住民から反対される?反対された時の対処方法を解説!
競合激化による稼働率低下
季節変動も大きな課題です。春や秋のハイシーズンは高い稼働率を維持できても、梅雨時期や冬季などのオフシーズンでは稼働率が30%を下回ることもあります。この変動は収益計画に大きな影響を与え、安定した収益確保を難しくします。
ホテルの価格競争も激化しています。東京都内では新規ホテルの開業が相次ぎ、特に3つ星以下のビジネスホテルでは民泊と競合する価格帯での提供が増えています。ホテルは朝食サービスやフロント対応など民泊にはない付加価値を提供できるため、単純な価格競争では不利になることも少なくありません。
差別化戦略が鍵となります。単なる宿泊施設ではなく、その地域ならではの体験や特別なインテリア、ユニークなサービスなど、他にはない魅力を提供することが重要です。
悪質なゲストによるトラブル
民泊運営において、悪質なゲストによるトラブルも無視できないリスクです。通常のホテルと異なり、フロントスタッフがいない民泊では問題が発生した際の即時対応が難しいという弱点があります。
実際に発生しているトラブルとしては、物品の破損や盗難が挙げられます。高価な家電製品や家具が破損されるケースや、アメニティや備品が持ち去られるケースもあります。
予約時に申告した人数より多くの人数で宿泊するケースも問題です。設備の利用限度を超えた使用により、水道トラブルやエアコンの故障などが発生することもあります。
事前スクリーニングの徹底が重要です。予約前にゲストとのコミュニケーションをしっかり取り、過去の評価を確認することで問題を起こしそうなゲストを事前に避けることができます。デポジット(保証金)の設定も効果的で、破損や違反があった場合の補償を確保できます。
災害・感染症など外部要因リスク
東京は自然災害のリスクが比較的高い地域です。地震、台風、洪水などの災害が発生した場合、民泊事業は大きな影響を受ける可能性があります。新型コロナウイルスのような感染症の拡大も観光需要に直接影響を与えるリスク要因です。
2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には、東京の民泊需要は前年比で80%以上減少し、多くの事業者が撤退を余儀なくされました。このような外部要因は予測が難しく、短期間で状況が大きく変化するため柔軟な対応が求められます。
政治的・経済的要因による為替変動も訪日外国人の動向に影響を与えます。円安時には外国人観光客が増加する傾向がありますが、円高になると訪日コストが上がり需要が減少するリスクがあります。
東京で民泊を始めるならどうすればいい?

ここでは、東京で民泊ビジネスを効率的に始める方法について詳しく見ていきましょう。
東京で民泊ビジネスを始めるには、単に物件を用意して予約サイトに掲載すれば良いというわけではありません。法的要件、物件選定、運営方法など様々な要素を慎重に検討する必要があります。
初期投資を抑えながら効率的に開業する方法から、すでに実績のある物件を取得する方法まで、状況に応じた選択肢があります。自分の予算や目標、関われる時間などを考慮しながら最適な参入方法を選ぶことが重要です。
自力で民泊が可能な物件を開拓する
自力で民泊ビジネスを立ち上げる方法は、初期から自分の裁量で事業を構築したい方に適しています。物件選びから許認可取得、内装設計、運営方法まで全てを自分でコントロールできる一方で、専門知識や手続きの煩雑さに悩まされることもあります。
民泊開設エージェントは、民泊ビジネスの立ち上げに必要な一連の手続きをサポートしてくれます。多くのエージェントでは、物件探しから行政への申請手続き、運営開始までをワンストップでサポートしており、初めて民泊事業に参入する方でも安心して始められる環境を提供しています。
エージェントを活用する最大のメリットは、複雑な許認可手続きの負担軽減です。住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出や保健所への申請など、行政手続きは専門的な知識が必要な上に時間もかかります。エージェントを利用すれば必要書類の作成から申請までをプロに任せられるため、承認までの時間を大幅に短縮できます。
物件の内装設計や必要な設備導入についてもアドバイスが得られます。ゲストの満足度を高めるインテリアや法的に必要な防火設備など、エージェントは民泊運営に最適な環境づくりをサポートしてくれます。
民泊M&A仲介会社を使用し運営実績がある物件を購入する
運営実績のある物件を購入する最大のメリットは、過去の実績データに基づいた投資判断ができる点です。新規に民泊を始める場合、収益予測は市場調査や類似物件の情報を基に推測するしかありません。既存物件であれば過去の稼働率や売上データ、顧客評価などの実績を確認できます。これにより投資リターンの見通しがより正確になり、リスクを大幅に低減できます。
すでに必要な許認可を取得済みの物件であれば、開業までの時間を大幅に短縮できます。新規に申請する場合、許認可取得には数ヶ月かかることもありますが、既存物件であれば権利の譲渡手続きのみで済むケースが多いです。
民泊M&A仲介会社は、こうした既存物件の売買をサポートする専門家です。物件の価値評価から売買契約のサポート、さらには引継ぎまでをトータルでコーディネートしてくれます。
物件を選ぶ際には、立地や施設の質だけでなく競合状況や今後の市場動向も考慮すべきです。購入前には必ず現地視察を行い、物件の状態や周辺環境を直接確認することも重要です。
関連:他の地域より大田区で民泊を始めた方が儲かる?メリット、デメリットなど解説
\AIを活用した最先端の民泊特化のM&A仲介/
\ 日本総合政策ファンド /
まとめ
東京での民泊ビジネスは、適切な戦略と運営方法を選べば魅力的な収益を生み出す可能性があります。一般的な賃貸経営の2倍から3倍の利回りも十分に実現可能であり、運営代行サービスを活用すればほぼ手間をかけずに運用することもできます。東京の充実した交通網や観光資源は大きな強みとなり、初期投資の負担を抑えて副業として始められる点も魅力的です。
同時に、法規制への対応や近隣トラブル、競合激化、悪質なゲスト対応、外部要因リスクなど見落としがちな課題も存在します。これらのリスクを最小化するためには、事前の綿密な調査と準備が欠かせません。
参入方法としては、民泊開設エージェントを活用して自力で物件を開拓する方法と、M&A仲介会社を通じて運営実績のある物件を購入する方法があります。どちらを選ぶにせよ、自分の状況や目標に合った方法を選び、長期的な視点で取り組むことが成功への鍵となるでしょう。
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり改装工事、許認可取得、運営システム構築まで膨大な時間とコストがかかっていませんか。厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか。
すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスは、「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。