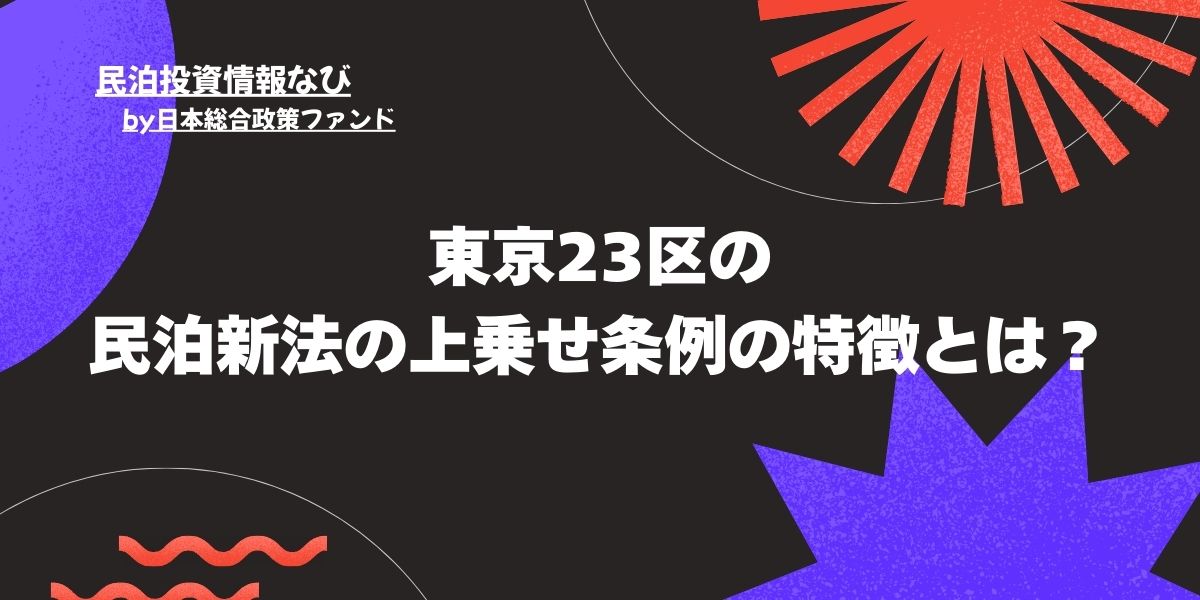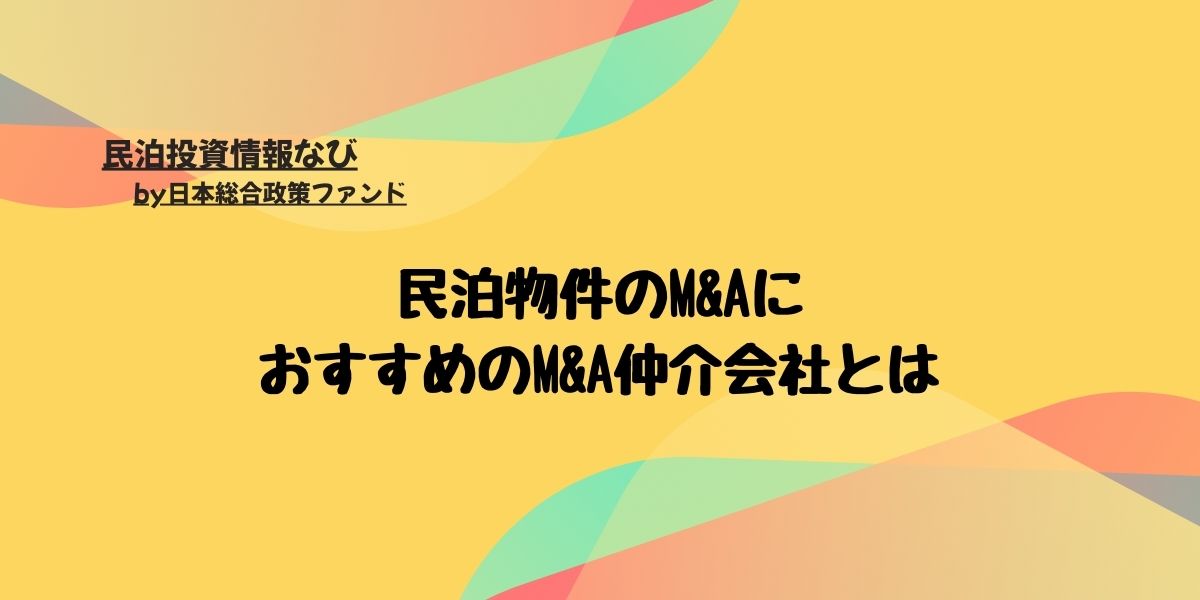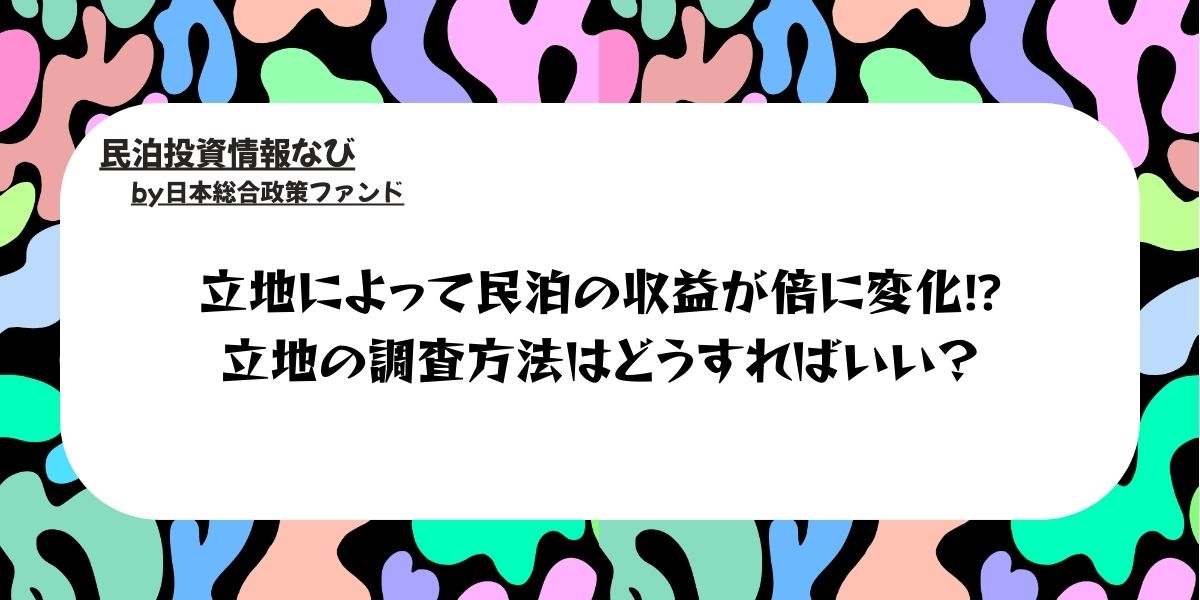東京23区で民泊を始めたいけれど、どの区で営業できるのか分からない。そんな悩みを抱えていませんか。
民泊新法(住宅宿泊事業法)は2018年6月に施行されましたが、各区が独自に定める「上乗せ条例」により、営業日数や地域に厳しい制限が課されています。千代田区や中央区では住居専用地域での営業が原則禁止、新宿区では週末限定の営業など、区によって規制内容は大きく異なります。
物件選びの段階で条例を理解していないと、「想定していた収益が得られない」「実質的に営業できない」といった事態に直面するリスクがあります。
この記事では、東京23区の上乗せ条例の特徴と区ごとの規制内容、民泊事業を成功させるためのポイントを詳しく解説します。
民泊新法の上乗せ条例とは?

民泊新法(住宅宿泊事業法)は2018年6月に施行され、それまでグレーゾーンだった民泊を合法化しました。全国一律で年間180日までの営業が認められる一方、各自治体は住宅宿泊事業法第18条に基づき、独自の規制を追加する「上乗せ条例」を制定できます。
上乗せ条例の規制内容は自治体ごとに異なりますが、主な規制対象は以下の3点です。
- 営業可能な用途地域の制限(住居専用地域での禁止など)
- 営業日数のさらなる制限(180日以下への短縮、曜日指定など)
- 届出時の追加書類(近隣説明の証明、管理規約など)
ここでは、上乗せ条例が制定される背景や東京23区における規制の特徴について詳しく見ていきましょう。
上乗せ条例が制定される主な理由
上乗せ条例が制定される背景には、以下の4つの要因があります。
**1. 住環境の保全**
住居専用地域では、住民の静穏な生活環境を守ることが最優先されます。民泊が急増した地域では、深夜の騒音、ゴミ出しルール違反、不特定多数の出入りによる防犯上の不安など、住民生活への影響が問題視されています。
**2. 既存宿泊業との公平性の確保**
ホテルや旅館は旅館業法に基づき、フロント設置や消防設備など厳格な基準を満たす必要があります。民泊の規制が緩すぎると、既存宿泊業との間で不公平が生じるため、一定の規制により市場バランスを保つ意図があります。
**3. 行政サービスへの負担軽減**
観光客の急増は、ゴミ収集、インフラ整備、治安維持など行政サービスへの負担を増大させます。住宅地での民泊を制限することで、行政サービスの質を維持しています。
**4. 地域特性への対応**
文教地区や高級住宅街など、地域の性質に応じた規制が必要とされます。学校周辺では教育環境の保全、観光地では観光客の受入れと住環境のバランスなど、地域ごとの事情が反映されています。
上乗せ条例の代表的な規制内容
東京23区の上乗せ条例では、以下5つの規制が民泊事業に大きな影響を与えます。
**1. 用途地域による営業区域の制限**
第一種・第二種低層住居専用地域など住居系地域での営業を禁止または大幅に制限する区が多数あります。千代田区、中央区、港区などでは、住居専用地域での営業を原則禁止としています。
**2. 営業日数・期間の制限**
民泊新法の年間180日に加え、さらに厳しい制限を設ける区があります。新宿区では住居系地域で週末のみの営業(金・土・日・祝日)に制限され、実質的な営業日数は年間約100日程度となります。
**3. 届出時の追加書類**
近隣住民への事前説明書、マンション管理規約の写し、廃棄物処理計画書などの提出を求める区が多くあります。書類の準備に1〜2ヶ月を要するケースもあり、開業スケジュールに影響します。
**4. 管理体制の追加要件**
緊急時の駆けつけ時間(10分以内、30分以内など)、24時間対応の連絡体制、苦情処理体制などが義務付けられています。これらは運営コストの増加要因となります。
**5. 家主居住型と家主不在型の区別**
家主が同居する「家主居住型」には緩やかな規制、家主が不在の「家主不在型」には厳格な規制を適用する区があります。文京区や中野区では、家主不在型に特に厳しい制限を設けています。
上乗せ条例で営業可能日数はどう変わる?

民泊新法では年間180日までの営業が認められていますが、東京23区の上乗せ条例により実質的な営業日数はさらに制限されます。区によって制限内容が大きく異なるため、物件選びの際は必ず確認が必要です。
**東京23区の主な営業日数制限**
- **千代田区・中央区・港区**:住居専用地域では原則営業禁止(営業日数0日)
- **新宿区**:住居系地域で週末のみ営業可能(年間約100日)
- **渋谷区**:住居専用地域で特定期間のみ営業禁止(年間約120日)
- **商業地域**:多くの区で年間180日の営業が可能
営業日数の制限は「期間指定」「曜日指定」の2パターンがあります。期間指定は「4月〜9月は営業禁止」のように特定期間を制限し、曜日指定は「平日のみ営業可」「週末のみ営業可」のように営業曜日を限定します。
収益計画への影響は大きく、年間180日営業できる物件と100日しか営業できない物件では、単純計算で収益が約45%減少します。物件取得前に、必ず当該区の条例を確認しましょう。
営業日数制限が事業に与える影響
営業日数の制限は収益性だけでなく、運営方法にも大きく影響します。
**収益面への影響**
年間100日しか営業できない場合、固定費(物件賃料、管理費など)の回収が困難になります。例えば、月額家賃15万円の物件では年間180万円の固定費に対し、営業日数が半減すると売上も半減するため、利益率が大幅に低下します。
**運営戦略への影響**
営業禁止期間の活用が課題となります。民泊営業できない期間は、マンスリーマンションとしての貸出、レンタルスペースとしての活用、撮影スタジオやコワーキングスペースへの転用など、多角的な収益化が求められます。
**関連記事**
営業可能日数が減るエリアの特徴
東京23区において、営業制限が厳しいエリアと緩やかなエリアには明確な傾向があります。
**制限が厳しいエリア**
- **住居専用地域**:第一種・第二種低層住居専用地域では、住環境保全を理由に営業を原則禁止または大幅に制限する区が多数
- **文教地区**:学校周辺や教育機関が集中する地域では、教育環境保護のため厳格な制限
- **高級住宅街**:目黒区、世田谷区などの高級住宅地では、住民の要望により厳しい規制
**制限が緩やかなエリア**
- **商業地域・近隣商業地域**:渋谷駅周辺、新宿駅周辺など商業活動が盛んな地域では年間180日の営業が可能
- **準工業地域**:住宅と工場が混在する地域では比較的緩やか
- **大田区の特区民泊**:羽田空港周辺では年間365日営業可能な特区民泊制度を利用可能
東京23区の上乗せ条例について

東京23区では、各区が独自の上乗せ条例を制定しており、営業可能な区域、営業日数、管理体制などが区ごとに大きく異なります。同じ東京都内でも、千代田区と大田区では営業条件が全く異なるため、物件選びの際は必ず該当区の条例を確認する必要があります。
ここでは、東京23区それぞれの主な規制内容を紹介します。なお、条例は改正されることがあるため、最新情報は各区の公式ホームページで確認してください。
**関連記事**
千代田区
住居専用地域での営業は原則禁止です。文教地区が多く、学校周辺では特に厳格な制限があります。マンションでの営業には管理規約の確認と管理組合の許可が必須となります。
中央区
住居専用地域では原則営業禁止です。銀座・日本橋など商業地域では比較的緩やかですが、集合住宅では管理組合の許可と近隣説明が求められます。
港区
住居専用地域では原則営業禁止ですが、他の都心区と比べると規制はやや緩やかです。外国人観光客が多いため、多言語対応と24時間管理体制が重視されます。
新宿区
住居系地域では金・土・日・祝日のみの営業に制限され、実質的な営業日数は年間約100日となります。繁華街が近いエリアでは、騒音・防犯対策が厳格に求められます。
文京区
教育施設が多く、住環境保全が重視されます。住居系地域では営業日数の制限があり、家主不在型には特に厳格な条件が課されます。
台東区
浅草・上野など観光地を多く抱え、他区と比べて規制は比較的緩やかです。観光客向けの案内や多言語対応が求められますが、家主居住型は営業しやすい環境にあります。
墨田区
スカイツリー周辺では観光需要が高く、比較的営業しやすいです。マンションでは管理組合の許可が必要ですが、規制は全体的に緩やかな傾向にあります。
江東区
有明・豊洲など新興エリアでは需要が高いものの、多くのマンションで管理規約により民泊が禁止されています。事前の管理規約確認が必須です。
**関連記事**
品川区
駅周辺の商業地域では営業しやすく、ビジネス客の需要が高いエリアです。住居専用地域では制限があり、家主不在型には管理体制の整備が求められます。
目黒区
高級住宅地が多く、住環境保全が最優先されます。住居専用地域での営業には厳しい制限があり、家主居住型でも厳格な条件が設けられる場合があります。
大田区
羽田空港に近く、特区民泊制度により年間365日の営業が可能です。空港利用者の需要が高く、多言語対応と交通案内の充実が求められます。
**関連記事**
世田谷区
広大な住宅地を抱え、住居専用地域での営業には厳しい制限があります。高級住宅地では住民の反対も強く、家主不在型には特に厳格な条件が課されます。
渋谷区
駅周辺の商業地域では営業しやすいものの、住居専用地域では期間制限があります。外国人観光客が多く、多言語対応と24時間管理体制が必須です。
中野区
住居専用地域と学校周辺では厳しい規制があります。家主不在型には厳格な管理体制と近隣説明が求められますが、駅周辺の商業地域では比較的営業しやすいです。
杉並区
住宅地が多く、住環境保全が重視されます。住居専用地域での営業には厳しい制限があり、家主不在型には厳格な管理体制が求められます。
豊島区
池袋駅周辺の商業地域では営業しやすく、外国人観光客とビジネス客の需要が高いです。住居専用地域では制限があり、家主不在型には厳格な管理体制が必要です。
北区
駅周辺の商業地域では比較的営業しやすいです。家主居住型は規制が緩やかですが、家主不在型には管理体制の整備と近隣説明が求められます。
荒川区
下町情緒が残るエリアで、商業地域では営業しやすいです。日暮里は成田空港へのアクセスが良く、訪日外国人の需要があります。防火・騒音対策は厳格です。
板橋区
駅周辺の商業地域では営業しやすいですが、住居専用地域では制限があります。家主不在型には厳格な管理体制と近隣説明が必須で、騒音・ゴミ対策が重視されます。
練馬区
広大な住宅地を抱え、住居専用地域での営業には厳しい制限があります。学校・公園周辺では特別な規制があり、家主不在型には厳格な管理体制が求められます。
足立区
北千住など交通の便が良いエリアではビジネス客の需要があります。駅周辺の商業地域では営業しやすく、家主居住型は比較的規制が緩やかです。
葛飾区
柴又など観光地として人気のエリアがあり、観光客向けの需要が見込めます。商業地域では営業しやすいですが、近隣住民への配慮が強く求められます。
江戸川区
葛西はディズニーリゾートへのアクセスが良く、観光客の需要が高いエリアです。駅周辺の商業地域では営業しやすく、適切な管理体制があれば家主不在型でも営業可能です。
まとめ
東京23区で民泊事業を成功させるには、各区の上乗せ条例を正確に理解することが不可欠です。
**重要ポイント**
1. **区による規制の違い**:千代田区・中央区・港区では住居専用地域での営業が原則禁止、新宿区では週末のみの営業、大田区では特区民泊として年間365日営業可能など、区によって大きく異なります。
2. **営業日数の制限**:民泊新法の年間180日に加え、上乗せ条例によりさらに制限される区があります。週末のみの営業に制限される場合、実質的な営業日数は年間約100日となり、収益計画に大きく影響します。
3. **物件選びの重要性**:住居専用地域では営業できない、またはできても厳しい制限がある一方、商業地域では比較的緩やかです。物件の用途地域を必ず確認してください。
4. **管理体制の整備**:24時間対応の連絡体制、緊急時の駆けつけ体制、近隣への配慮など、適切な管理体制の構築が求められます。
5. **最新情報の確認**:条例は改正されることがあるため、各区の公式ホームページで最新情報を確認し、必要に応じて行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
東京23区での民泊事業は、上乗せ条例を理解し、適切に対応することで、安定した収益を得られるビジネスモデルとなります。地域との共存を前提とした運営を心がけましょう。