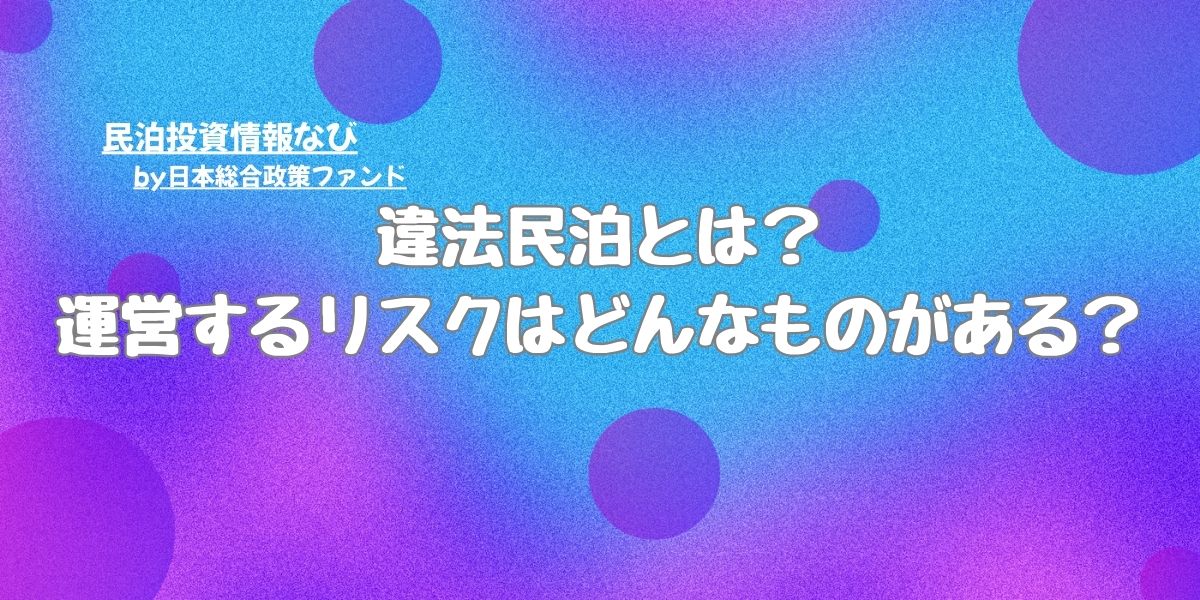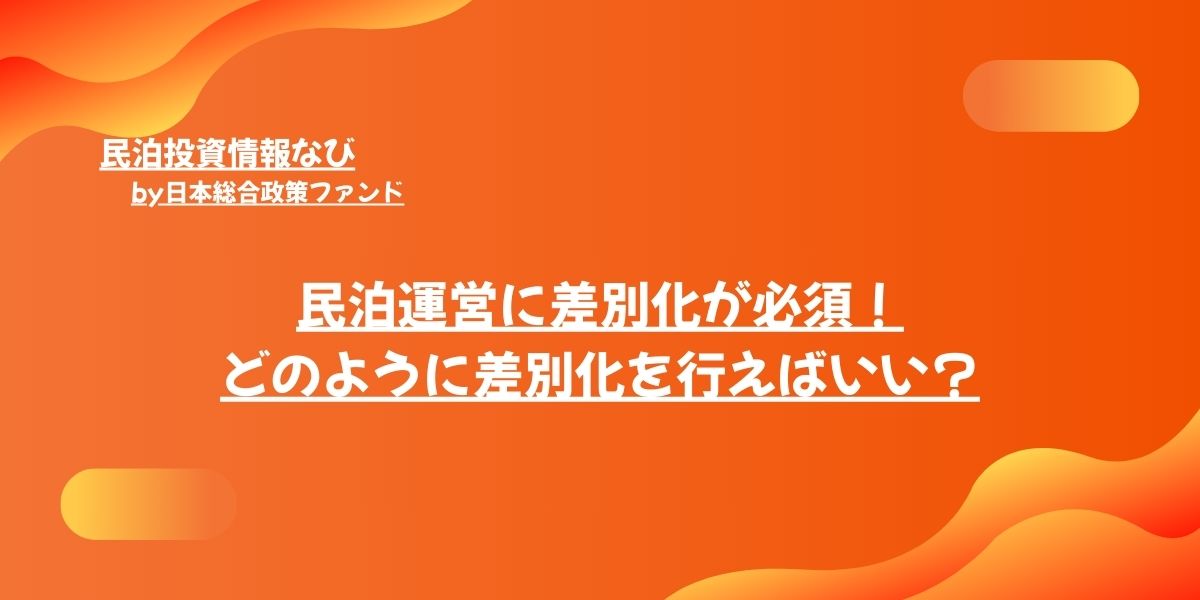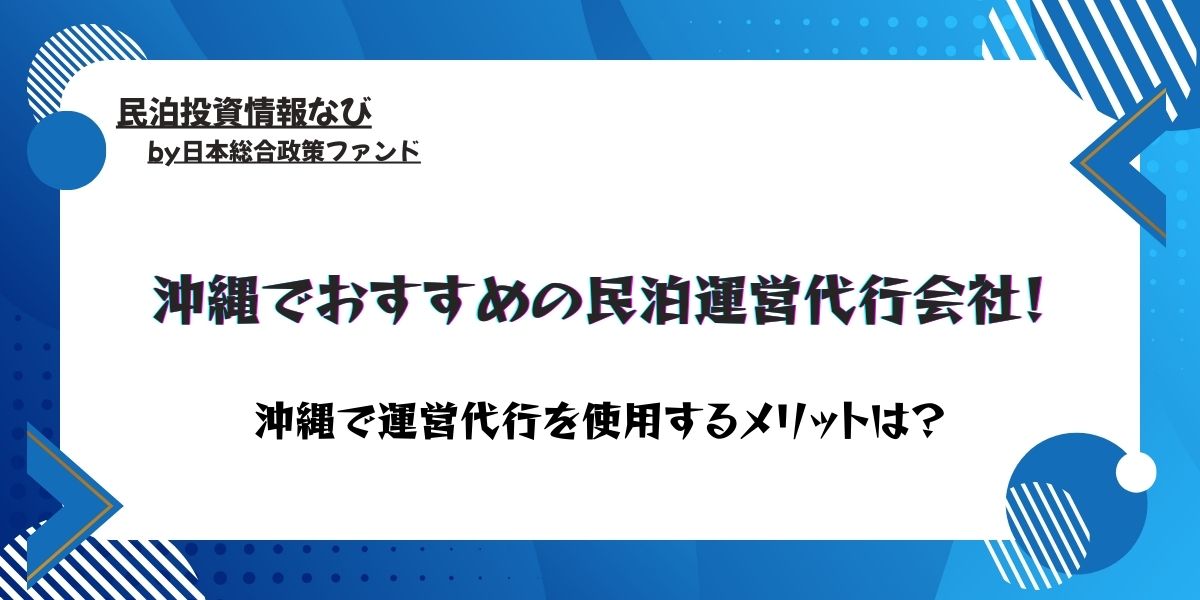民泊を始める際、必要な許可や届出を把握していますか。無許可で運営すると違法民泊となり、罰金や営業停止といった重いペナルティを受けるリスクがあります。
実際に、近隣住民からの通報や行政の立入検査により違法民泊が発覚し、運営者が多額の罰金を科せられる事例が後を絶ちません。2018年には大阪市で4か月間に1,800件以上の違法民泊が摘発され、全国的にも取り締まりが強化されています。
本記事では、違法民泊の定義や合法民泊との違い、運営時のリスク、実際の摘発事例について詳しく解説します。民泊運営を検討中の方は、法令を正しく理解し、安全に事業を始めましょう。
違法民泊とは何か?

違法民泊とは、住宅宿泊事業法(民泊新法)や旅館業法に基づく必要な許可・届出を行わずに運営されている宿泊施設を指します。
訪日外国人の増加や宿泊需要の高まりを背景に、民泊サービスは急速に拡大しました。一方で、法的手続きを省略した無許可営業も増加し、社会問題化しています。違法民泊は無許可営業にとどまらず、近隣住民とのトラブルや宿泊者の安全確保の欠如など、深刻なリスクを生み出しています。
ここでは、違法民泊が存在する理由と合法民泊との違いについて詳しく見ていきましょう。
違法民泊が存在している理由
違法民泊が広がる背景には、複数の社会的・経済的要因があります。
最も大きな要因は収益性の高さです。通常の賃貸契約と比較して、短期宿泊の方が数倍の収入を得られるケースも珍しくありません。観光地や都市部の人気エリアでは、その傾向が顕著です。
許認可手続きの煩雑さも違法民泊を生み出す一因となっています。合法的に民泊を運営するには、消防設備の設置や定期検査など、様々な法的要件を満たす必要があります。手続きにかかる時間やコストを避けるため、無許可で営業する事業者が存在します。
インターネットの普及により、個人間での宿泊施設の貸し借りが容易になったことも影響しています。Airbnbなどの民泊仲介サイトを通じて、専門知識がなくても集客できる環境が整いました。プラットフォーム側も違法物件対策を行っていますが、完全なチェックは難しい状況です。
不動産投資の一環として民泊運営に参入する個人や企業も増加しています。法規制についての理解不足や、規制を無視するケースもあり、違法民泊の増加につながっています。
合法民泊との主な違い
合法民泊と違法民泊の最も基本的な違いは、法的手続きの有無です。
合法民泊は住宅宿泊事業法に基づく「届出」または旅館業法に基づく「許可」を取得して運営されています。住宅宿泊事業法では届出番号が発行され、その番号を広告や予約サイトに表示することが義務付けられています。
安全基準においても大きな差があります。合法民泊では、消防法に基づく設備の設置や定期的な安全検査が実施されています。非常口の表示、避難経路図の掲示、消火器の設置などが義務付けられており、火災や災害時に宿泊者の安全を確保する措置が講じられています。
衛生管理面でも違いがあります。合法民泊では設備の清掃や消毒、寝具の洗濯など、衛生管理に関する基準を満たすことが求められています。保健所による立入検査も行われるため、一定の衛生水準が保たれています。
運営ルールにも明確な差があります。合法民泊では年間営業日数の上限(住宅宿泊事業法では原則180日以内)や、宿泊者名簿の作成・保管義務が定められています。宿泊者に対して外国語対応を含む必要な情報提供を行うことも求められています。
地域との共存という点でも、合法民泊は近隣住民への事前説明や、トラブル発生時の対応窓口の設置など、コミュニティとの調和を図る取り組みが義務付けられています。管理者の駐在や緊急時の連絡体制なども整備されており、近隣とのトラブル防止に努めています。
関連:民泊の始め方とは?物件選定から運営開始までの流れを紹介!
違法民泊を運営するリスク

違法民泊は手軽に始められる副業や投資に見えるかもしれませんが、実際には深刻なリスクを伴います。リスクは法令違反にとどまらず、宿泊者の安全や地域コミュニティの秩序を脅かす可能性があります。
違法民泊を避けるためには、リスクを正しく理解することが重要です。ここでは、違法民泊が抱える主な6つのリスクについて詳しく解説します。
法的処罰の可能性が高く罰金や営業停止が課される
違法民泊が摘発されると、旅館業法違反として6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。住宅宿泊事業法違反の場合も、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
摘発されると即座に営業停止命令が出され、施設は封鎖されます。収入は途絶え、すでに予約が入っている宿泊者への対応も必要です。キャンセル料の負担や代替宿泊施設の手配など、追加コストが発生します。
違法営業で得た収入は脱税とみなされ、追徴課税の対象となります。本来納めるべき税金に加え、延滞税や重加算税が課され、金銭的な負担は当初の想定をはるかに超える可能性があります。
法的処罰を受けると、その記録は公的に残り、将来的なビジネス展開や就職活動にも影響を及ぼします。一時的な利益と引き換えに、長期的な信用やキャリアを損なうリスクがあるのです。
近隣住民とのトラブルが発生する
違法民泊の運営に伴い、近隣住民とのトラブルは避けられません。
集合住宅では、頻繁に入れ替わる宿泊者による騒音や生活音が深刻な問題となります。夜間の話し声やパーティー、スーツケースの引きずる音など、通常の居住者であれば気をつける生活音も、短期滞在者には伝わりにくいものです。
ゴミ出しルールの不徹底も大きな問題です。地域や建物によって異なるゴミ出しルールを宿泊者に正確に伝えることは難しく、不適切なゴミ出しが発生します。分別されていないゴミや指定日以外の排出は、近隣住民の不満を招きます。
セキュリティ面での不安も無視できません。建物のセキュリティコードや鍵の共有、不特定多数の出入りにより、建物全体のセキュリティが脅かされます。見知らぬ人が頻繁に出入りすることへの不安を感じる住民も少なくありません。
これらのトラブルが蓄積すると、近隣住民からの直接的なクレームや管理組合への苦情につながります。最終的には行政への通報という形で表面化し、違法営業の摘発に直結します。実際に、違法民泊の摘発のきっかけは近隣住民からの通報であるケースが大半です。
関連:知らないと危険!民泊でのトラブルとは?トラブル回避のための対策法を解説!
無許可運営により事故時の補償がない
違法民泊における最も深刻なリスクの一つが、事故発生時の補償問題です。
合法的な民泊や宿泊施設では営業許可取得の過程で適切な保険加入が義務付けられていますが、違法民泊ではこうした安全網が欠如しています。通常の火災保険や家財保険は営業目的での使用を想定していないため、民泊利用中の事故では適用外となるケースがほとんどです。保険会社による調査で違法民泊の実態が判明した場合、保険金の支払いが拒否されるだけでなく、契約自体が解除されることもあります。
宿泊者が施設内で怪我や病気になった場合、違法民泊運営者は全ての医療費や損害賠償を自己負担で支払う必要が生じます。重大な事故や死亡事故の場合、賠償金額は数千万円に達することもあり、個人の資産では対応しきれない可能性が高いです。
違法民泊では消防設備や非常口の整備が不十分なケースが多く、火災などの緊急事態が発生した際の人的被害リスクが高まります。このような事態が発生した場合、民事上の賠償責任だけでなく、業務上過失致死などの刑事責任を問われる可能性もあります。
建物の構造上の問題や設備の不備による事故も懸念されます。旅館業法や住宅宿泊事業法の許可過程では安全面のチェックが行われますが、違法民泊ではこの段階を省略しているため、潜在的な危険を見逃しやすくなっています。
無許可運営による補償の欠如は、運営者にとって財政的破綻のリスクであると同時に、宿泊者の生命や安全を脅かす深刻な問題です。
関連:民泊保険って必要?一般の火災保険と何が違う?メリット、デメリットなど解説!
宿泊者の安全確保が難しく緊急時の責任問題が生じる
違法民泊では宿泊者の安全を確保するための法定基準が満たされていないため、様々な危険が潜んでいます。
合法民泊では必須とされる防火設備や避難経路の確保、定期的な設備点検などが行われていないケースが多く、緊急時の対応に大きな不安があります。特に外国人観光客が宿泊するケースでは、言語の壁による緊急時のコミュニケーション問題も深刻です。火災や地震などの災害時に適切な避難指示ができなければ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。合法民泊では多言語対応のマニュアル整備が義務付けられていますが、違法民泊ではこうした対応が不十分なことが多いです。
宿泊者の体調不良や急病の際の対応体制も大きな問題です。合法民泊では管理者の常駐や24時間対応の連絡体制が求められますが、違法民泊ではこれらが整備されていないケースが一般的です。宿泊者が緊急医療を必要とする状況になった際、適切な対応ができず、状況を悪化させるリスクがあります。
宿泊者による犯罪行為や不適切な行為を監視・制御する体制も不十分です。宿泊施設には宿泊者名簿の作成・保管義務があり、犯罪抑止や捜査協力の役割を果たしますが、違法民泊ではこうした管理が行われていないことが多いです。施設が犯罪の温床となるリスクも否定できません。
違法民泊運営者は、安全管理の不備による事故や事件が発生した場合、民事上の損害賠償責任だけでなく、状況によっては刑事責任を問われる可能性もあります。宿泊者の安全確保は宿泊業の最も基本的な責務であり、この点での不備は違法民泊の最も深刻な問題の一つです。
プラットフォームからBANされることで予約や収入が途絶える
Airbnbなどの民泊プラットフォームは、違法物件の掲載を厳しく取り締まっています。
プラットフォームによる違法物件の特定方法はいくつかあります。住宅宿泊事業法に基づく届出番号の表示が義務付けられており、この番号がない、または虚偽の番号を掲載している物件は調査対象となります。ユーザーからの通報システムも整備されており、宿泊者や近隣住民からの通報によって違法物件が特定されるケースも増えています。
行政機関との連携も進んでおり、自治体から違法物件のリストが提供された場合、プラットフォーム側で一斉に該当物件を削除する取り組みも行われています。東京都や大阪市などの主要都市では、プラットフォームとの情報共有協定を結び、効果的な違法民泊対策を実施しています。
アカウントがBANされると、その影響は即座に現れます。すでに入っている予約はキャンセルとなり、キャンセル料や代替宿泊施設の手配費用などの負担が生じる可能性があります。プラットフォーム経由の新規予約がすべて停止するため、収入は突如として途絶えます。
多くの違法民泊運営者は、プラットフォームに依存した集客モデルを取っているため、代替の集客手段を持たないケースが多いです。プラットフォームからのBANは違法民泊運営者にとって深刻なリスクであり、安定した収入源を一瞬で失う可能性があります。
悪評やレビュー悪化により信頼性や集客力が低下する
違法民泊は法的リスクだけでなく、評判という点でも大きな弱点を抱えています。
宿泊者が違法性に気づいた場合、オンラインレビューで厳しい評価を下されるリスクがあります。「届出番号がない」「安全設備が不十分」といった指摘は、他の潜在的な宿泊者に警告を発する効果があります。
海外からの観光客は、安全面や法令遵守に対する意識が高いケースが多く、違法運営が発覚した場合に強い不信感を抱く傾向があります。否定的なレビューは長期間インターネット上に残り続け、将来的な集客に悪影響を及ぼします。レビュースコアが下がると、検索結果での表示順位も下がり、露出機会の減少につながります。
一度ネガティブな評判が広まると、その回復には膨大な時間と労力が必要です。特にSNSでの拡散力は強く、一人の不満を抱えた宿泊者の投稿が数千人、数万人の目に触れる可能性があります。
集客力の低下は価格競争力の低下にも直結します。同等の条件を持つ他の物件より大幅に安い価格を提示しなければ宿泊予約を獲得できなくなります。収益性が著しく低下し、事業継続が困難になるケースも少なくありません。
違法民泊運営による評判リスクは、法的リスクと同様に深刻な問題です。
関連:民泊経営が失敗してしまうのには必ず理由がある!失敗を回避する方法は?
違法民泊の摘発事例にはどんなものがある?

違法民泊の摘発は近年急速に増加しており、自治体による取り締まりが強化されています。
許可や届出をせずに民泊を運営することは単なる行政指導の対象にとどまらず、最悪の場合は刑事罰の対象となることもあります。実際の摘発事例を知ることで、違法民泊のリスクを正しく理解できます。
ここでは、京都市、新宿区、大阪市、札幌市など主要都市における違法民泊の摘発事例を見ていきましょう。
京都市で2015年に36室を違法運営し書類送検された事例
2015年、京都市内のマンションで旅館業法の許可を得ずに36室を民泊として運営していた業者が、京都府警に書類送検されました。
この事件は、民泊法(住宅宿泊事業法)が施行される前の事例ですが、旅館業法による無許可営業の摘発として重要な先例となりました。マンションの一室や複数の部屋を使った違法民泊が社会問題化する中、本格的な取り締まりの始まりを示す象徴的な事件でした。
この摘発後、京都市は違法民泊に対する監視体制を強化し、観光地としての質を保つための取り組みを本格化させました。
参考:日本経済新聞 36室で「民泊」 業者摘発 京都のマンション、無許可営業疑い
関連:京都の民泊規制が厳しい理由とは?具体的な規制や守らなかった時の罰則を解説!
大阪市が2018年に4か月で1,800件以上を閉鎖した大規模摘発
2018年、大阪市は「大阪市違法民泊撲滅チーム」を設置し、4か月間で1,800件以上の違法民泊を閉鎖しました。
大阪市の摘発は、観光客の多い地域での違法民泊が社会問題化していたことを背景に行われました。摘発された物件は合法的な民泊への移行を促されましたが、基準を満たせない物件については営業停止となりました。
大阪市の取り組みは、違法民泊の取り締まりにおいて全国的にも先進的な事例として注目されました。専門チームを結成して組織的に対応した点は、他の自治体にも影響を与えました。
参考:大阪府2018年 4月25日 「大阪市違法民泊撲滅チーム」 設置2-4sannkoushiryou.pdf)
札幌市が2017年に13件の違法民泊に行政指導を行った事例
2017年、札幌市は13件の違法民泊に対して行政指導を行いました。
札幌市の事例は、大都市圏以外の地域でも違法民泊の問題が広がりを見せていたことを示しています。雪まつりなどの観光イベントで知られる札幌では、観光客の急増に伴い、合法・違法を問わず民泊が増加していました。
行政指導の対象となった物件は、主に近隣住民からの騒音やゴミ出しに関する苦情がきっかけで発覚したケースが多かったとされています。
参考:日本経済新聞 札幌市、違法民泊の摘発強化
まとめ
違法民泊は、住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく必要な許可・届出を行わずに運営される宿泊施設です。運営者は以下のような多くのリスクを抱えることになります。
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金などの法的処罰
- 近隣住民とのトラブル発生
- 事故時の補償がない
- 宿泊者の安全確保の難しさ
- プラットフォームからのBAN
- 悪評やレビュー悪化による集客力低下
全国各地で摘発事例が増加しており、自治体による取り締まりも厳格化しています。2018年には大阪市で4か月間に1,800件以上、京都市では36室を運営していた業者が書類送検されるなど、厳しい対応が取られています。
安全で持続可能な民泊ビジネスを行うためには、住宅宿泊事業法や旅館業法に基づく適切な手続きを踏むことが必須です。合法的に運営することで、安心して事業を継続できます。
関連:【利回り8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
民泊投資を始める際、物件探しから改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかります。厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じる方も多いでしょう。
すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、失敗するリスクを大幅に削減できます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスは、「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。