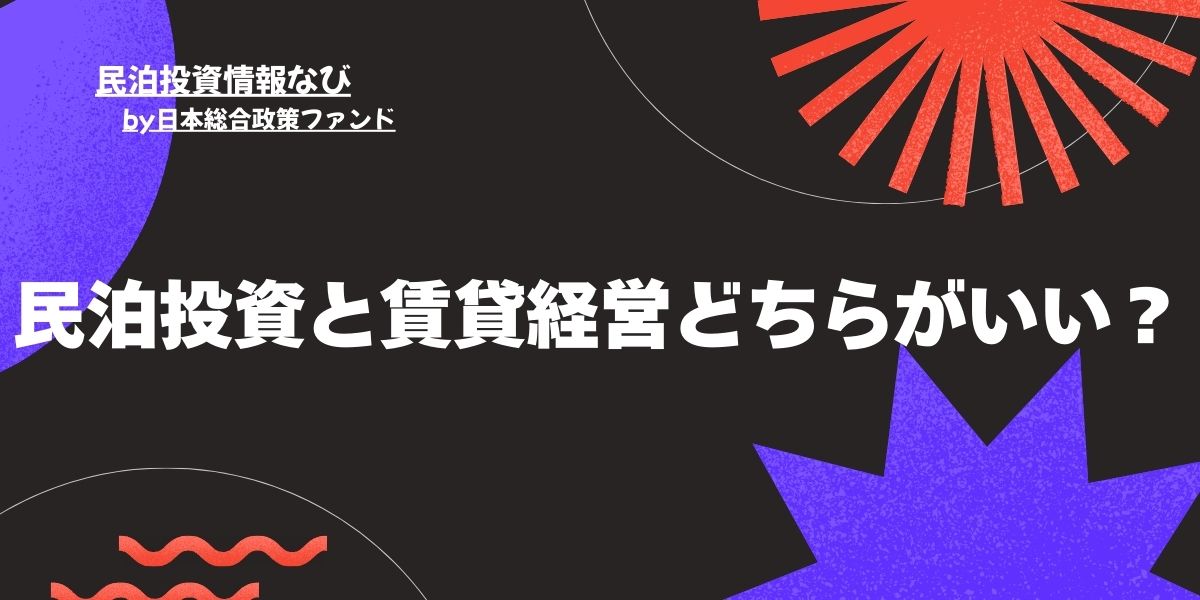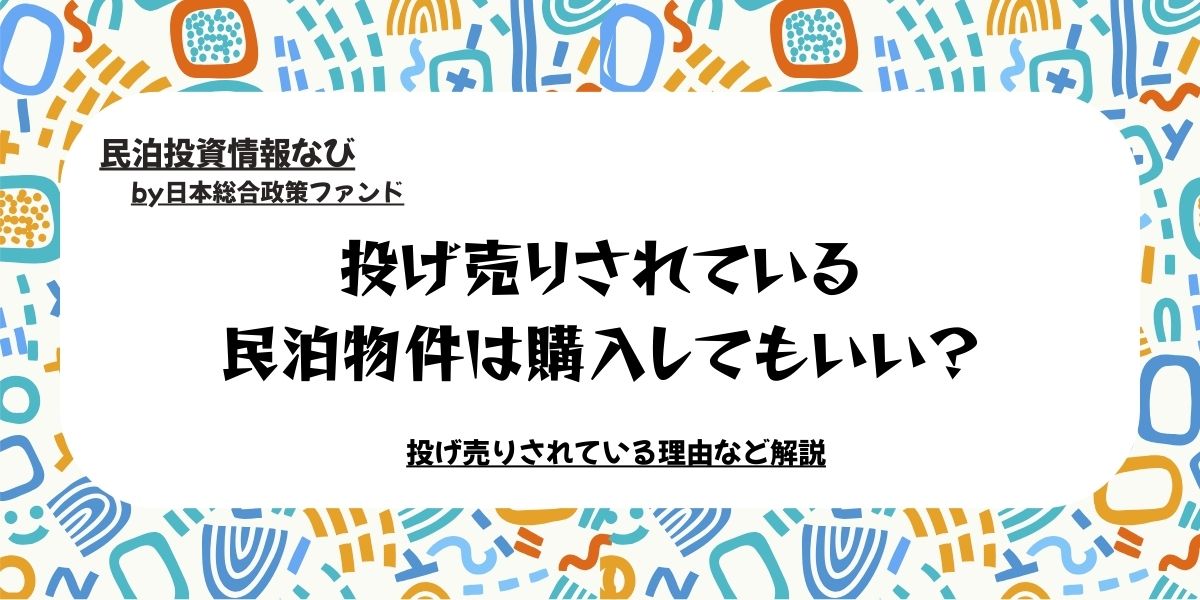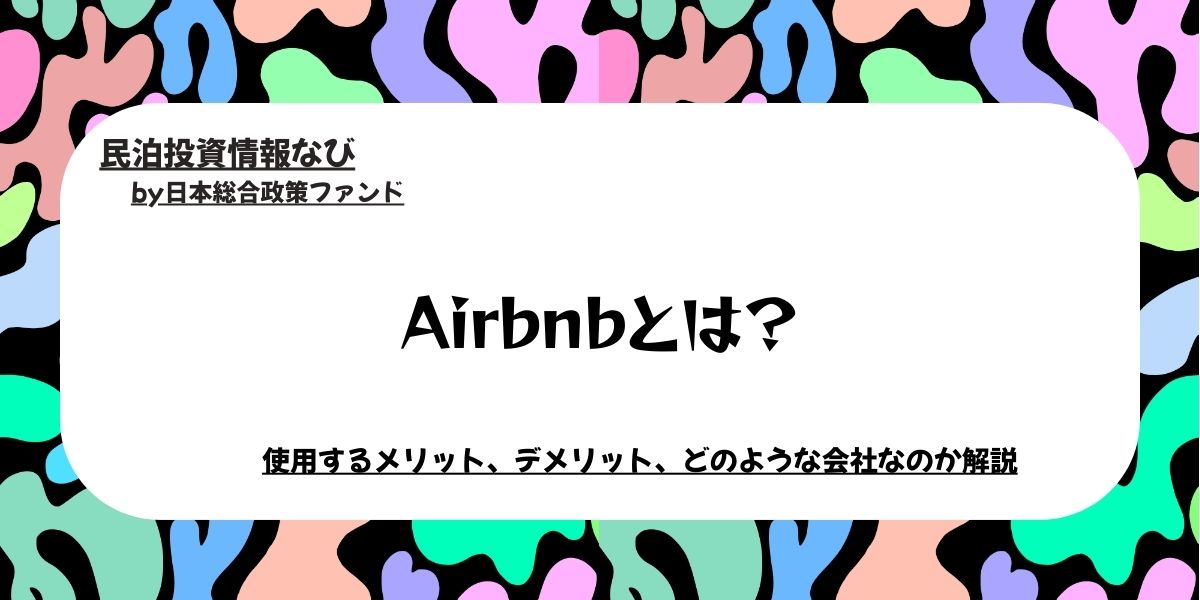不動産投資の選択肢として、民泊と賃貸のどちらを選ぶべきか悩んでいませんか?収益性やリスク、管理の手間など、それぞれに特徴があり、簡単には判断できないものです。「民泊の方が儲かりそうだけど、本当に大丈夫なの?」「賃貸の方が安定しているけど、収益は十分なの?」といった疑問をお持ちの方も多いはずです。
この記事では、民泊と賃貸それぞれのメリット・デメリットを徹底的に解説します。
これから不動産投資を始めようとしている方はもちろん、すでに賃貸経営をしている方で民泊への転換を検討されている方にも役立つ情報をお届けします。
民泊と賃貸、何が違う?

多くの方から「民泊と賃貸の違いがよくわからない」という声を耳にします。両者には明確な違いがあり、事業を始める前に理解しておく必要があります。住宅を活用したビジネスモデルとして注目を集めているこの2つの形態について、詳しく見ていきましょう。
民泊とは?
事業を始める際には、都道府県知事への届出が必要です。届出の際には、周辺住民への事前説明や管理体制の整備など、様々な要件をクリアしなければなりません。
関連:民泊とはどんな宿泊施設?種類や特徴、人気な設備・サービス、始め方など紹介!
賃貸とは?
賃貸借契約には借地借家法が適用され、入居者の居住権が手厚く保護されています。家賃の支払いや住宅の使用方法など、契約で定められた事項を順守する必要があります。
賃貸物件の募集から入居者の選定、契約締結まで、不動産会社が仲介することが一般的です。入居後の設備の修繕や維持管理については、オーナーに責任が発生します。
一般的な賃貸では、入居者が生活の拠点として使用することを想定しています。そのため、賃貸住宅を無断で転貸したり、宿泊施設として使用したりすることは禁止されています。
民泊と賃貸、管理の違いは何?

民泊と賃貸では、必要な管理業務の内容や頻度に大きな違いがあります。民泊はホテルのような宿泊施設としての管理が求められる一方、賃貸は居住用住宅としての管理が中心となります。それぞれの特徴的な管理業務について詳しく解説していきます。
民泊の管理業務とは?
民泊の管理業務は、ホテルのフロント業務に近い性質を持ちます。宿泊者が短期間で入れ替わるため、こまめな対応と徹底した衛生管理が必要不可欠です。
チェックインの際には、宿泊者の本人確認や施設の利用説明を行います。外国人旅行者の場合、パスポートの確認や多言語での対応も求められます。施設内の設備やアメニティの使い方なども丁寧に説明する必要があります。
清掃業務は特に重要です。宿泊者が入れ替わるたびに、リネン類の交換やバスルーム、キッチンの清掃を行います。また、定期的な換気や消毒も欠かせません。衛生管理の不備は、口コミ評価の低下や予約数の減少に直結します。
トラブル対応も重要な業務の一つです。深夜の騒音や設備の不具合など、様々なトラブルに24時間体制で対応できる準備が必要です。近隣住民とのトラブルを未然に防ぐための配慮も欠かせません。
賃貸の管理業務とは?
賃貸の管理業務は、入居者が快適に暮らせる環境を維持することが中心となります。長期的な居住を前提とするため、計画的な修繕と適切な入居者対応が重要になります。
入居者からの問い合わせや修繕依頼への対応が主な業務です。設備の故障や不具合が発生した場合、状況を確認して必要な修理を手配します。また、定期的な設備点検を行い、大規模な修繕が必要な箇所を把握することも重要です。
家賃の集金や滞納対応も管理業務の一つです。家賃の支払い状況を確認し、必要に応じて督促や相談対応を行います。また、契約更新時期には、賃料改定の検討や更新手続きの案内なども必要になります。
入居者の退去時には、原状回復工事の見積もりや工事の手配を行います。また、新たな入居者募集のための広告掲載や内覧対応なども管理業務に含まれます。
長期的な資産価値の維持も重要な観点です。計画的な修繕や設備の更新を行うことで、物件の競争力を保ち、安定した賃料収入を確保することができます。
民泊と賃貸経営、どっちが儲かる?

不動産投資の選択肢として、民泊と賃貸を比較検討される方が増えています。収益性を判断するには、それぞれの特徴やビジネスモデルを正しく理解する必要があります。細かな数字を見ながら、具体的に分析していきましょう。
関連:高収益が見込めるAirbnb投資とは?賃貸運営との違いなど解説!
民泊経営の収益モデル
民泊の収益は、1泊あたりの宿泊料金と稼働率によって大きく変動します。都心部の人気エリアであれば、1泊10,000円から30,000円程度の料金設定が一般的です。立地や設備の充実度によって、さらに高額な料金設定も可能です。
稼働率は季節や立地によって大きく変動します。観光地に近い物件では、ハイシーズンには80%以上の稼働率を達成することも可能です。一方で、オフシーズンには20%程度まで落ち込むケースもあります。
料金設定の柔軟性も民泊の特徴です。需要が高まる時期には料金を上げ、需要が少ない時期には料金を下げることで、稼働率を調整できます。週末や祝日、大型イベント開催時には、平日の1.5倍から2倍程度の料金設定も可能です。
関連:民泊経営の平均年収はどれくらい?成功するためのコツなど紹介
賃貸経営の収益モデル
空室対策として、家賃保証会社の活用や入居者の審査基準の見直しなどが重要になります。また、定期的なリフォームや設備の更新により、物件の競争力を維持することで、空室リスクを軽減できます。
運営コストの比較
賃貸の運営コストは、建物の維持管理費用が中心となります。共用部分の清掃費や設備の修繕費、火災保険料などが主な経費です。また、管理会社に委託する場合は、家賃収入の5%程度の管理手数料が必要です。
民泊と賃貸、どちらがリスクが高い?

不動産投資を始める際に避けて通れないのが、リスクの検討です。民泊と賃貸では、直面するリスクの性質が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な対策を講じることが成功への近道となります。
民泊経営のリスク
民泊特有のリスクとして、まず近隣トラブルが挙げられます。宿泊者の入れ替わりが頻繁なため、騒音や生活マナーの問題が発生しやすい傾向にあります。深夜の出入りや大声での会話、ごみの出し方など、些細なことでもトラブルに発展する可能性があります。
予期せぬ事故やトラブルのリスクも重要です。宿泊者の怪我や設備の破損、貴重品の紛失など、様々なトラブルが発生する可能性があります。特に外国人宿泊者の場合、言語の問題でコミュニケーションが難しく、トラブル解決に時間がかかることもあります。
法規制の変更や新たな規制の導入も、大きなリスク要因です。条例の改正により営業日数が制限されたり、新たな安全基準が設けられたりする可能性があります。これらの変更に対応するための追加投資が必要になることもあります。
需要の変動も無視できないリスクです。観光客の減少や競合施設の増加により、稼働率が低下する可能性があります。また、季節性の強い需要変動は、安定した収益確保を難しくします。
関連:【利回り率8〜18%】民泊投資とは?リスクや失敗しないための方法など解説
賃貸経営のリスク
家賃の滞納も深刻なリスクです。入居者の経済状況の悪化により、家賃の支払いが滞る可能性があります。滞納が長期化すると、法的手続きが必要になることもあり、その間の収入損失や手続き費用が発生します。
入居者による建物の損傷も無視できません。通常の使用による経年劣化以外に、入居者の不適切な使用による損傷が発生することもあります。原状回復費用の負担や、次の入居者募集への影響など、複合的な問題につながる可能性があります。
土地や建物の価値下落リスクも重要です。周辺の開発状況や人口動態の変化により、不動産価値が低下する可能性があります。これは、将来の売却価値や借り入れの担保価値にも影響を与えます。
両者を比較すると、民泊は日々の運営リスクが高く、きめ細かな対応が必要です。一方、賃貸は長期的な資産価値の維持が課題となります。リスク対策には、適切な保険加入や専門家への相談、運営体制の整備など、計画的な取り組みが欠かせません。
賃貸物件で民泊はできる?

多くの不動産オーナーから「賃貸物件を民泊として活用できないか」という相談を受けます。結論から言えば、賃貸物件での民泊運営は可能ですが、いくつかの重要な条件をクリアする必要があります。具体的な手順と注意点について見ていきましょう。
関連:Airbnbで賃貸物件を又貸しすることができる?リスクなど解説!
賃貸で民泊を始める前に確認すべきこと
まず最初に確認が必要なのは、物件の賃貸借契約内容です。多くの賃貸借契約には、転貸禁止条項が含まれています。民泊を始める前に、必ずオーナーの承諾を得る必要があります。
建物の構造や用途地域の確認も重要です。消防法や建築基準法の規定により、一般の賃貸住宅をそのまま民泊として利用できない場合があります。特に、防火設備や避難経路の基準を満たしているかどうかの確認が必須です。
管理規約の確認も忘れてはいけません。マンションやアパートでは、管理組合の規約で民泊を禁止しているケースが少なくありません。規約の改定には区分所有者の合意が必要となり、実現までにかなりの時間と労力がかかります。
区分所有者でない賃借人が民泊を始める場合は、さらに慎重な対応が必要です。オーナーの承諾に加えて、管理組合や近隣住民への説明も必要になります。説明会の開催や同意書の取得など、丁寧なコミュニケーションが求められます。
関連:民泊を無許可で始めると捕まる!?無許可で始めるリスクなど解説!
民泊への転換に必要な手続き
適法に民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。届出には、以下の書類の準備が求められます。
- 事業者の身分証明書
- 建物の登記事項証明書
- 管理規約の写し
- 消防法令適合通知書
- 設備等の配置図
また、宿泊者の安全確保のため、以下のような設備の設置も必要になります。
- 非常用照明
- 消火器
- 避難経路図
- 火災報知器
- 防音設備
これらの設備投資には相応のコストがかかりますが、宿泊者の安全確保のために必要不可欠な投資です。設備の選定にあたっては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
届出が受理されれば、いよいよ民泊の運営を開始できます。ただし、年間提供日数の上限(180日)や、宿泊者名簿の作成・保管など、継続的な遵守事項があることにも注意が必要です。
賃貸物件での民泊運営は、手続きの煩雑さやコストの面でハードルが高いのは事実です。しかし、適切な準備と運営体制を整えることで、新たな収益機会として活用することも可能です。
まとめ
どちらを選択するにせよ、物件の立地条件や市場環境、自身の経営資源を総合的に判断することが重要です。また、リスクヘッジの観点から、民泊と賃貸を組み合わせたポートフォリオ運営という選択肢もあります。慎重な検討と十分な準備を行い、長期的な視点で投資を進めていくことをお勧めします。