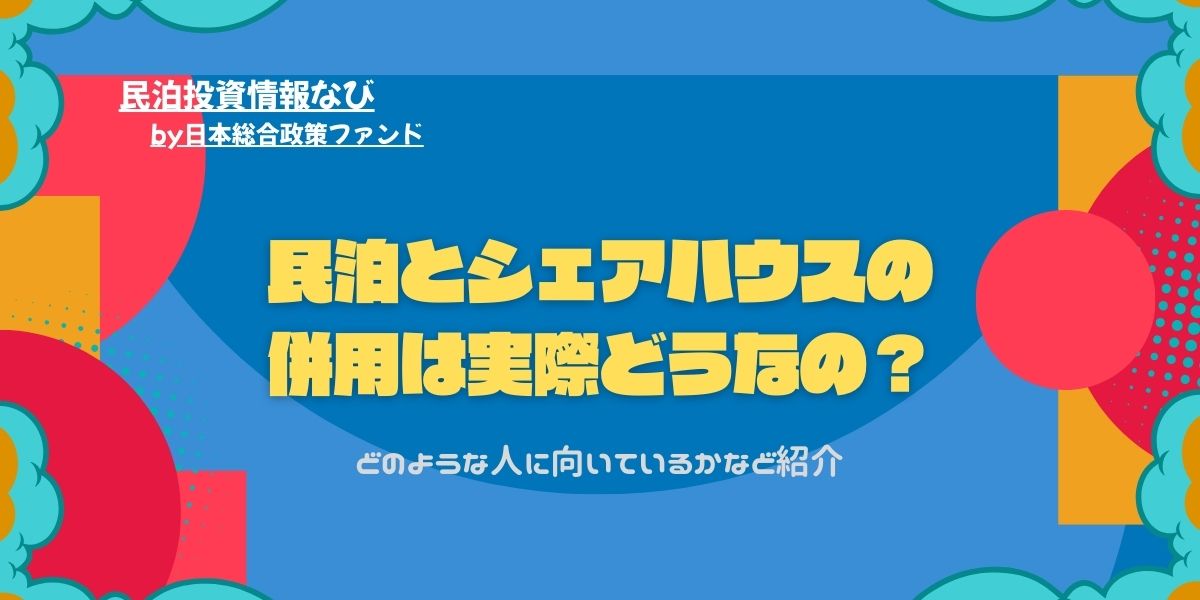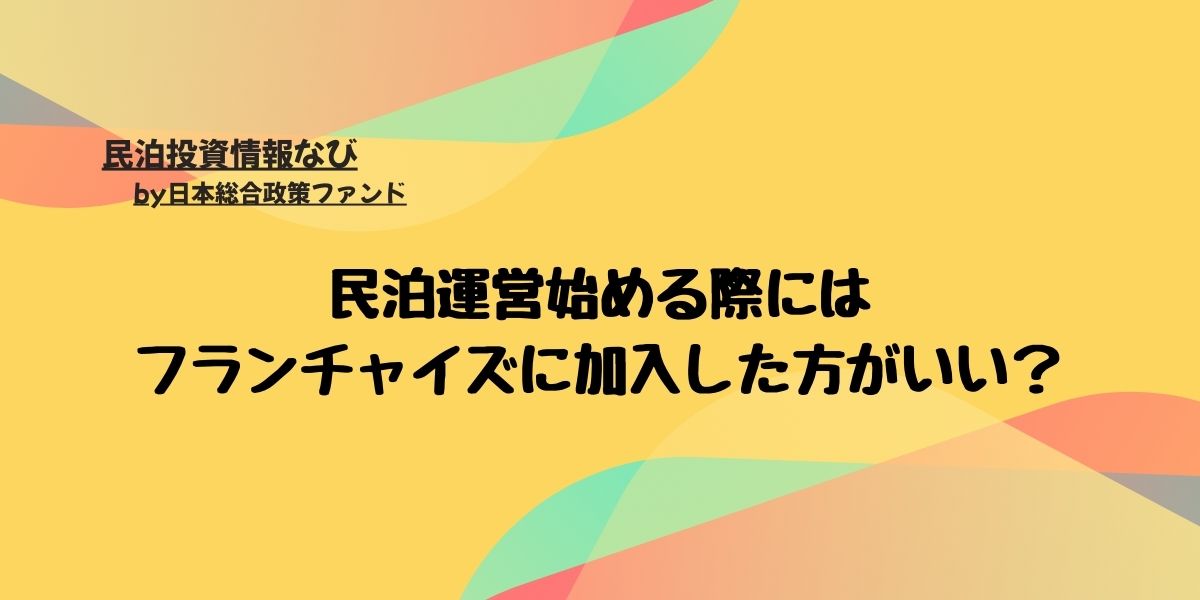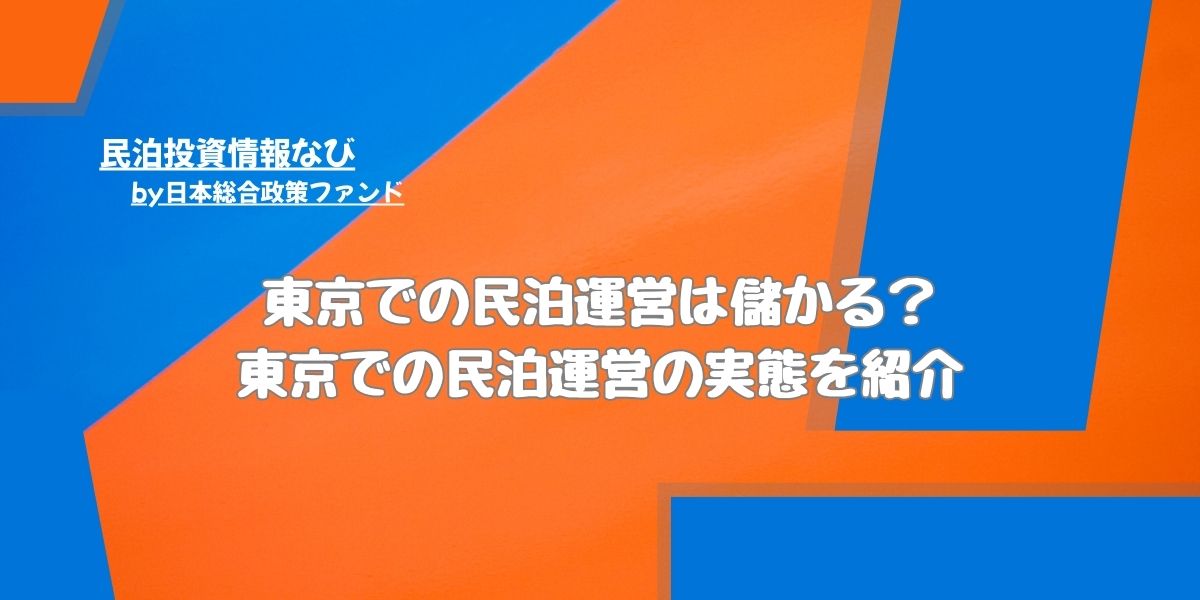「シェアハウスと民泊、両方運営できればいいのに…」と考えたことはありませんか?物件の有効活用と収益最大化を同時に実現する方法として、シェアハウスと民泊の併用運営が注目されています。しかし、実際に始めようとすると、法的手続きの複雑さ、物件選びの難しさ、運営ノウハウの不足など、様々な壁にぶつかりがちです。
この記事では、シェアハウスと民泊の併用が可能なのか、どのような条件が必要なのか、実際の収益性はどうなのかなど、併用運営のすべてを徹底解説します。
シェアハウスと民泊の併用は可能?

シェアハウスと民泊の併用についてよく質問を受けますが、結論から言うと併用は可能です。しかし、単純に「可能」と言い切れるほど簡単ではありません。併用するためには、物件の特性や法的条件、運営体制などさまざまな要素を考慮する必要があります。
そもそも、シェアハウスと民泊は運営方式や対象者が異なるため、それぞれの特性を理解した上で併用を検討することが大切です。
併用可能な物件の条件とは
シェアハウスと民泊を併用するには、物件選びが非常に重要です。どんな物件でも併用できるわけではなく、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
まず、物件の構造と間取りが併用に適しているかを確認しましょう。シェアハウスは長期居住者向け、民泊は短期滞在者向けという性質の違いがあるため、これらを物理的に分離できる構造が理想的です。例えば、1階と2階で分ける、または棟が分かれている物件なら、生活音や生活リズムの違いによるトラブルを防ぎやすくなります。
戸建て住宅の場合、各階で用途を分けられる2階建て以上の物件が適しています。1階を共用スペースとシェアハウス居住者の個室、2階を民泊用の客室として運用するパターンが多く見られます。
また、立地条件も重要なポイントです。民泊需要の高いエリアであることはもちろん、シェアハウス需要も同時に見込めるエリアが理想的です。駅から徒歩10分以内、もしくは観光スポットへのアクセスが良いエリアが望ましいでしょう。特に、インバウンド需要が見込める地域では民泊の需要が高まる傾向があります。
施設面では、共用設備と専用設備の区分けが明確にできることが条件になります。キッチンやリビングなどの共用部分は、シェアハウス居住者と民泊利用者が時間帯をずらして使用できるよう、十分な広さを確保することが重要です。また、バスルームやトイレについては、できれば複数設置されている物件が望ましいでしょう。
物件の管理体制についても考慮が必要です。シェアハウスと民泊では入退去の頻度が異なるため、鍵の受け渡しやセキュリティ面での対策が必要になります。スマートロックの導入や監視カメラの設置など、セキュリティ対策がしやすい物件構造かどうかもチェックポイントになります。
併用運営の収益性はどれくらい?

シェアハウスと民泊の併用運営を検討する上で、最も気になるのが収益性ではないでしょうか。単純に「儲かる」とは言い切れませんが、適切な物件と運営方法を選べば、単体運営よりも収益性を高められる可能性があります。
両者を併用することで、空室リスクの軽減や稼働率の向上、さらには季節変動への対応力強化など、さまざまな相乗効果が期待できます。具体的な数字や事例を交えながら、シェアハウスと民泊の併用における収益性について詳しく見ていきましょう。
関連:高収益が見込めるAirbnb投資とは?賃貸運営との違いなど解説!
シェアハウス単体と民泊単体の収益比較
シェアハウスと民泊、それぞれの収益構造には明確な違いがあります。まずはこの違いを理解することが、併用運営の収益性を考える第一歩です。
シェアハウスの収益は「安定性」が最大の特徴です。長期契約が基本となるため、入居者が決まれば月々の家賃収入が安定します。例えば、6部屋あるシェアハウスで1部屋あたり月5万円の家賃設定の場合、満室時には月30万円の収入が見込めます。空室率を20%と想定しても、月24万円程度の収入が期待できるでしょう。
ただし、シェアハウス単体の収益性には上限があります。家賃相場は地域によって異なりますが、一般的な相場を大きく上回る設定は難しく、収入の大幅な増加は見込みにくいのが実情です。また、共用部分のメンテナンスや水道光熱費などの固定費用が発生するため、利益率は一般的な賃貸経営と比べて若干低くなる傾向があります。
一方、民泊の収益は「高収益性」と「変動性」が特徴です。繁忙期には1泊あたりの単価が高く設定でき、同じ物件でもシェアハウスより高い収入が期待できます。例えば、都心部の物件で1泊1万円、月の稼働率が80%とすると、1部屋あたり月24万円程度の収入になります。6部屋あれば月144万円と、シェアハウスの数倍の収入も理論上は可能です。
しかし、民泊には大きな変動リスクがあります。季節や曜日による需要の波、突発的なキャンセル、競合の増加などにより、稼働率が大きく変動します。また、清掃やリネン交換、ゲスト対応などの運営コストも無視できません。実際には、年間を通じた稼働率は50~60%程度に落ち着くことが多く、収益の安定性はシェアハウスに劣ります。
こうした両者の特性を比較すると、立地条件や物件の状態にもよりますが、一般的には以下のような傾向があります。
- 高稼働期(観光シーズンなど)は民泊の方が収益性が高い
- 低稼働期はシェアハウスの方が安定収入を確保できる
- 年間通じた平均では、運営コストを考慮すると両者の純利益には大きな差がないケースが多い
こうした両者の特性を理解した上で、次に併用した場合のシミュレーションを見ていきましょう。
収益シミュレーション事例紹介
それでは、実際にシェアハウスと民泊を併用した場合の収益シミュレーションを、具体的な事例を交えて紹介します。
【都内の木造戸建て(築30年、延床面積80㎡、6部屋)】
この物件では、4部屋をシェアハウス、2部屋を民泊として運用しています。初期投資は、リフォーム費用と設備投資を含めて1,200万円でした。
シェアハウス部分(4部屋):
- 月額家賃:1部屋5.5万円 × 4部屋 = 22万円
- 年間収入:22万円 × 12ヶ月 × 入居率90% = 237.6万円
民泊部分(2部屋):
- 繁忙期(5月~10月):1泊1.2万円 × 2部屋 × 平均稼働率70% = 月50.4万円
- 閑散期(11月~4月):1泊0.8万円 × 2部屋 × 平均稼働率50% = 月24万円
- 年間収入:(50.4万円 × 6ヶ月)+(24万円 × 6ヶ月)= 446.4万円
合計年間収入:237.6万円 + 446.4万円 = 684万円
運営コスト:
- 固定費(ローン返済、修繕費、保険料など):月15万円 = 年間180万円
- 変動費(水道光熱費、インターネット、消耗品など):月10万円 = 年間120万円
- 民泊運営費(清掃、リネン、管理手数料など):年間100万円
年間純利益:684万円 -(180万円 + 120万円 + 100万円)= 284万円
このケースでは、初期投資1,200万円に対して年間純利益284万円となり、投資利回りは約23.7%です。全室シェアハウスにした場合の推定利回り15%、全室民泊にした場合の推定利回り20%と比較しても、併用の効果が表れています。
シェアハウス民泊併用に向いている人は?

シェアハウスと民泊の併用運営は、単なる不動産ビジネスの枠を超えた要素が求められます。この運営形態は誰にでも向いているわけではなく、特定の資質や価値観を持つ人に適しています。
実際に併用運営を成功させている方々には共通する特徴があり、自分がこのビジネスに向いているかどうかを判断する際の参考になるでしょう。
柔軟性と適応力がある人
例えば、民泊の予約状況に応じてシェアハウスの部屋数を調整したり、逆にシェアハウス入居者の状況に合わせて民泊の受け入れ計画を変更したりする必要があります。繁忙期には民泊部分を増やし、閑散期にはシェアハウス部分を増やすという柔軟な運用が収益を最大化するカギとなります。
また、宿泊者や入居者のニーズも多様です。外国人観光客からビジネス客、学生から社会人まで、様々な背景を持つ人々が利用するため、それぞれの要望や文化的背景に合わせたサービス提供が求められます。例えば、外国人宿泊者への英語での対応や、異なる生活習慣への配慮など、状況に応じた対応力が必要です。
トラブル対応においても柔軟性が試されます。シェアハウス入居者同士の人間関係の調整や、民泊利用者からのクレーム対応など、予測不可能な問題が発生した際に、冷静かつ柔軟に解決策を見出せる人が向いています。「こうあるべき」という固定観念にとらわれず、状況に応じた最適解を模索できる思考の柔軟性が成功の鍵です。
さらに、法規制や市場環境の変化にも適応する必要があります。民泊関連の法律は比較的新しく、頻繁に変更される可能性があるため、常に最新情報をキャッチアップし、必要に応じて運営方針を修正できる適応力も求められます。
多文化に興味がある人
シェアハウスと民泊の併用運営は、様々な国籍や文化背景を持つ人々と交流する機会に恵まれています。特に民泊部分では、世界各国からの旅行者を受け入れることになるため、異文化への興味や理解がある人に向いています。
多様な文化や価値観に触れることを楽しめる人は、このビジネスから金銭的な報酬以上の充実感を得られます。例えば、フランスからの旅行者に地元の観光スポットを紹介したり、アジアからの留学生と料理を通じて文化交流したりする経験は、単なるビジネスを超えた価値をもたらします。
また、異なる文化を尊重し、コミュニケーションを取ることが得意な人は、入居者や宿泊者との関係構築がスムーズになります。言語の壁があっても、おもてなしの心や相手を理解しようとする姿勢があれば、多くの問題は解決できるものです。
さらに、多文化に関する知識や興味は、施設の設計やサービス内容にも反映されます。例えば、様々な国の料理が作れる設備を整えたキッチンや、多言語対応の案内表示など、多文化を意識した空間づくりができる人は、差別化されたサービスを提供できます。
コミュニティを築きたい人
シェアハウスと民泊の併用運営において、単なる「部屋貸し」を超えてコミュニティ形成に価値を見出せる人は、大きな強みを持っています。特にシェアハウス部分では、入居者同士の良好な関係性が長期的な入居継続につながり、安定収入の基盤となります。
コミュニティ形成に関心があり、人と人をつなげることが得意な人は、このビジネスモデルで真価を発揮します。例えば、定期的な食事会やイベントを企画したり、入居者同士の共通の趣味や関心事を見つけて引き合わせたりすることで、単なる「住む場所」ではなく「帰りたくなる場所」を創出できます。
民泊部分においても、一時的な宿泊者とシェアハウス入居者との交流の機会を設けることで、「地元の人と触れ合える宿」としての付加価値を生み出せます。旅行者にとって、現地の生活者との交流は貴重な体験となり、高評価や再訪問の動機になります。
コミュニティ形成のためには、共用スペースの設計も重要です。自然と人が集まるようなリビングやキッチン、気軽に会話が生まれるようなラウンジスペースなど、交流を促進する空間づくりができる人に向いています。
時間管理が得意な人
シェアハウスと民泊の併用運営では、様々な業務が並行して発生するため、効率的な時間管理能力が不可欠です。シェアハウスの入居者対応と民泊のチェックイン/チェックアウト、清掃やメンテナンス、予約管理など、多岐にわたるタスクを適切に処理できる人に向いています。
特に民泊部分では、チェックインの時間帯が不規則であったり、急なリクエストへの対応が必要だったりするため、柔軟な時間管理能力が求められます。例えば、深夜到着の宿泊者への対応と、翌朝の清掃スケジュールの調整など、異なるタイムラインで動く業務を効率的に組み合わせる必要があります。
また、繁忙期と閑散期でワークロードが大きく変動するため、忙しい時期に備えたタスクの前倒しや、余裕がある時期にメンテナンス作業を集中させるなど、先を見据えた時間配分が重要です。
さらに、自分の時間だけでなく、スタッフや外部サービス(清掃会社など)との連携も必要になります。複数の関係者のスケジュールを調整し、効率的な業務フローを構築できる人は、運営の効率化に成功します。
デジタルツールの活用も時間管理の重要な要素です。予約管理システムやスマートロック、防犯カメラなど、テクノロジーを活用して遠隔管理や自動化を進められる人は、物理的な拘束時間を減らし、より多くの物件を効率的に管理できます。
併用運営に必要な手続きと許可は?

シェアハウスと民泊の併用運営を始める際には、それぞれに必要な手続きと許可を適切に行う必要があります。両者は管轄する法律や必要な許認可が異なるため、すべての要件を満たさなければなりません。併用運営は単純に両方の手続きを行えば良いというわけではなく、相互に影響し合う部分もあるため、慎重な対応が求められます。それぞれの制度を理解し、正しい手順で手続きを進めることが、トラブルなく事業を続けるための基盤となります。
ここでは、シェアハウスと民泊それぞれの手続きに加え、併用する際の特有の注意点についても解説します。
シェアハウス運営に必要な手続きと許可
シェアハウスの運営開始にあたっては、不動産賃貸業としての基本的な手続きに加え、いくつかの特有の許認可が必要になります。これらを適切に行うことで、法的に問題のないシェアハウス運営が可能になります。
まず、建築基準法上の用途に関する確認が必要です。一般的な住宅をシェアハウスとして使用する場合、建築基準法上は「寄宿舎」または「共同住宅」に該当する可能性があります。部屋数や構造によって判断が異なるため、事前に管轄の建築指導課に相談することをおすすめします。
次に、消防法に関する手続きです。シェアハウスは複数の人が生活する場所であるため、消防設備の設置が義務付けられています。具体的には、自動火災報知機や誘導灯、消火器などの設置が必要です。これらは建物の規模や構造によって要件が異なるため、最寄りの消防署に相談し、必要な設備を確認しましょう。
また、賃貸借契約の形態にも注意が必要です。シェアハウスの契約形態には主に「家主との直接契約」と「転貸借契約」の2種類があります。前者は各入居者が家主と個別に契約を結ぶパターン、後者は運営者が家主から一括借り上げし、入居者に転貸するパターンです。転貸借の場合は、家主からの転貸借許可を得ることが不可欠です。この許可なしに転貸すると、契約違反となり、トラブルのもとになります。
最後に、地方自治体によっては独自の条例や規制がある場合があります。
民泊運営に必要な手続きと許可
まず、住宅宿泊事業の届出が必須です。これは、住宅宿泊事業法に基づき、物件の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)に届け出るものです。届出には物件の図面や設備の状況、周辺地図などの添付書類が必要で、安全面や衛生面の基準を満たしていることを示す必要があります。
次に、管理業務主任者の設置または住宅宿泊管理業者への委託が必要です。家主が不在となる「家主不在型」の民泊では、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託するか、自ら管理業務主任者となる必要があります。管理業務主任者になるには試験に合格し、登録を受ける必要があります。
また、周辺住民への説明も重要な手続きです。多くの自治体では、民泊開業前に周辺住民への説明会開催や通知を求めています。これは法的義務ではない場合もありますが、トラブル防止のために積極的に行うべきでしょう。具体的な方法や範囲は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
さらに、宿泊者名簿の作成と保管も義務付けられています。宿泊者全員の氏名、住所、職業、宿泊日等を記録し、チェックイン時に本人確認を行う必要があります。この名簿は一定期間保管する義務があります。
消防法に関する手続きも必要です。火災警報器の設置や消火器の備え付け、避難経路の表示などが求められます。規模によっては消防署への届出や検査が必要になることもあります。
重要なのが、自治体独自の条例や規制への対応です。例えば、東京都千代田区や大阪市では、住居専用地域での民泊営業を制限する条例があります。また、営業日数の制限(年間180日以内)についても、自治体によってはさらに厳しい制限を設けている場合があります。地域の条例を確認し、遵守することが不可欠です。
マンションやアパートで民泊を行う場合は、管理規約の確認も必須です。多くの集合住宅では、管理規約で民泊を禁止または制限しています。規約に違反して営業すると、トラブルや法的問題につながる可能性があります。
関連;【民泊を始めたい方必見!】民泊の始め方とは?物件選定から運営開始まで紹介!
併用運営に必要な手続き
シェアハウスと民泊を併用して運営する場合、それぞれの制度に必要な手続きをすべて行う必要があるだけでなく、併用特有の手続きや注意点も存在します。これらをしっかりと押さえておくことで、法令違反のリスクを回避できます。
まず、建物の用途区分の整理が重要です。同じ建物内でシェアハウスと民泊を併用する場合、建築基準法上の用途をどのように区分するかが問題になります。
次に、消防設備の基準についても注意が必要です。シェアハウスと民泊では求められる消防設備が異なることがあります。
また、物件内のゾーニングも重要です。シェアハウス入居者と民泊利用者の動線を分けるなど、プライバシーや安全面に配慮した区分けが必要です。これは法的要件というよりは運営上の工夫ですが、トラブル防止のためにも重要な点です。
さらに、賃貸借契約と宿泊契約の区別も明確にしておく必要があります。シェアハウス入居者との契約は賃貸借契約(借地借家法が適用)、民泊利用者との契約は宿泊契約(民法の一般原則が適用)と、法的性質が異なります。それぞれに適した契約書を用意し、権利義務関係を明確にしておきましょう。
届出や許可申請の際には、併用することを明記することも重要です。特に民泊の届出時には、同じ建物内にシェアハウスが存在することを明示し、図面等で区分を明確にすることが望ましいでしょう。
オーナーの体験談
大阪・難波の元旅館をコンバージョンしたケース(Bさん、38歳)
「大阪・難波にある祖父の代から続いていた小さな旅館を引き継ぎましたが、旅館業としては厳しい状況でした。そこで、1階部分を民泊として運営し、2階と3階をシェアハウスとして改装することにしました。
旅館だった建物なので、元々共同浴場や広い台所があり、シェアハウスに適した構造でした。ただ、完全に分離するのではなく、民泊利用者もシェアハウスの共用スペースを一部利用できるようにしています。これが予想以上に好評で、海外からの旅行者が日本人入居者と交流する場として機能しています。
運営面では、民泊部分は予約サイトを活用した完全非対面チェックインにし、シェアハウス部分は月1回のコミュニティイベントを開催して入居者の定着率を高めています。入居者には自主的にコミュニティマネージャーを担当してもらい、家賃の一部を免除する代わりに新入居者のサポートや共用部の管理を手伝ってもらっています。
収益的には、シェアハウス15室で月収60万円、民泊5室で月収50〜80万円と、旅館時代の約2倍の収入になっています。特に民泊部分は稼働率の変動が大きいですが、シェアハウスの安定収入があることで資金繰りの心配がなくなりました。
苦労した点は、防火設備の充実や避難経路の確保など、安全面の対策でした。特に民泊とシェアハウスでは適用される規制が異なるため、最も厳しい基準に合わせる必要がありました。また、シェアハウス入居者と民泊利用者のルール作りも試行錯誤の連続でしたが、今ではお互いがリスペクトし合える関係が築けています。」
シェアハウス民泊併用の注意点

シェアハウスと民泊の併用運営は魅力的なビジネスモデルですが、成功させるためには様々な注意点があります。特に法規制や運営面でのハードルは決して低くありません。
ここでは、併用運営を成功させるための重要な注意点について解説します。
法的区分の明確化が必要である
シェアハウスと民泊を併用する際に最も重要なのが、法的区分の明確化です。これを怠ると、思わぬ法的リスクやトラブルに発展する可能性があります。
まず、シェアハウス部分と民泊部分の区別を物理的・契約的に明確にする必要があります。同じ建物内でも、シェアハウスは賃貸借契約に基づく居住施設、民泊は宿泊契約に基づく宿泊施設という全く異なる法的性質を持ちます。この区別があいまいだと、例えば賃借人の権利保護を定めた借地借家法が民泊利用者にも適用されるのかなど、予期せぬ法的問題が生じる可能性があります。
物理的な区分としては、シェアハウス部分と民泊部分を別フロアにする、専用の出入口を設けるなどの工夫が有効です。また、契約書や館内表示でも区分を明確にし、入居者や宿泊者にも理解してもらう必要があります。
特に注意すべき点として、住居専用地域に物件がある場合、民泊部分の運営に制限がかかる可能性があります。住宅宿泊事業法では住居専用地域でも民泊運営が可能ですが、自治体によっては条例で制限している場合もあります。例えば、東京都千代田区では住居専用地域での民泊営業を禁止しています。また、マンションなどの区分所有建物では、管理規約で民泊を禁止している場合が多いため、事前に確認が必須です。
さらに、税務上の区分も重要です。シェアハウス部分の収入は不動産所得、民泊部分の収入は事業所得として区分経理が必要になることが多いです。共用部分の経費をどのように按分するかなど、複雑な会計処理が必要になるため、税理士への相談をおすすめします。
住人とゲストの共存できるようにする
シェアハウスと民泊の併用運営における最大の課題の一つが、長期居住者(シェアハウス住人)と短期滞在者(民泊ゲスト)の共存です。生活リズムや文化背景が異なる両者が同じ空間を共有することで、様々なトラブルが発生する可能性があります。
まず、共用スペースの利用ルールを明確に定めることが重要です。キッチンやリビング、バスルームなどの共用部分をいつ、どのように使用できるのかを明示しましょう。
次に、言語の壁も大きな課題です。特に海外からの民泊利用者が多い場合、コミュニケーション不足からトラブルが生じやすくなります。多言語対応のルールブックを作成したり、館内表示を複数言語で行ったりするなどの工夫が必要です。
また、プライバシーの確保も重要な要素です。シェアハウス住人にとって、自分の生活空間に見知らぬ人が出入りすることは不安要素になり得ます。セキュリティ対策として、シェアハウス部分と民泊部分のアクセス制限を設けたり、各部屋の鍵を強化したりすることをおすすめします。スマートロックやセキュリティカメラの導入も検討しましょう。
加えて文化や習慣の違いへの配慮も欠かせません。例えば、ゴミの分別や騒音に対する感覚は国によって大きく異なります。入居時や宿泊時のオリエンテーションで日本の生活習慣について説明したり、視覚的にわかりやすいガイドを用意したりすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、シェアハウス住人の中から「ハウスマネージャー」や「コミュニティリーダー」を任命し、民泊ゲストへの対応や共用部の管理を手伝ってもらう仕組みも効果的です。家賃の割引や特典と引き換えに協力してもらうことで、運営コストの削減にもつながります。
消防・建築基準を厳守できるようにする
シェアハウスと民泊の併用運営において、消防法や建築基準法の遵守は絶対に譲れない重要事項です。これらは入居者・宿泊者の安全に直結するだけでなく、違反が発覚した場合には営業停止や罰則の対象となります。
まず、消防設備については、シェアハウスと民泊それぞれに必要な設備を把握し、より厳しい基準に合わせて以下のものを整備する必要があります。
- 自動火災報知設備:特に延床面積が300㎡以上の場合は、感知器と受信機を連動させた本格的なシステムが必要。
- 誘導灯・誘導標識:非常口や避難経路を示す誘導灯や標識の設置が必要。
- 消火器:各フロアや共用スペースに適切な数の消火器を設置する。
- 避難経路の確保:2方向避難の原則に従い、複数の避難経路を確保することが重要。
さらに、定期的な設備点検と記録の保管も重要です。消防設備は年に1〜2回の点検が義務付けられており、これを怠ると罰則の対象となります。点検結果は記録し、保管しておくことが必要です。
まとめ
シェアハウスと民泊の併用運営は、適切な物件選びと法的手続きの遵守、効果的な運営ノウハウがあれば、単体運営よりも高い収益性と安定性を実現できる可能性があります。併用には、シェアハウスの安定収入と民泊の高収益性というメリットを組み合わせられる反面、法的区分の明確化や入居者と宿泊者の共存ルール作り、厳格な安全基準の遵守など、クリアすべき課題も少なくありません。
成功のカギは、柔軟性と適応力、多文化への興味、コミュニティ形成への情熱、そして効率的な時間管理能力にあります。これらの要素を備え、適切な物件と運営方法を選択することで、安定した長期的な収益源としてのシェアハウス民泊併用ビジネスを構築できるでしょう。
民泊投資を始めようとすると、物件探しから始まり、改装工事、許認可取得、運営システム構築まで、膨大な時間とコストがかかっていませんか?さらに、厳しい法規制や市場の変動リスクに直面し、思うような収益化に不安を感じていませんか?
しかし、すでに稼働中の民泊物件を購入することで、これらの時間やコスト、そして失敗するリスクを大幅に削減することができます。ゼロから始める不安を解消し、即収益が見込める物件へスムーズに投資するために、専門の民泊M&A仲介会社の活用がカギとなります。
そこでおすすめするのが、日本総合政策ファンドの民泊M&A仲介サービスです。「観光大国日本を、金融の力でサポートする」をミッションに掲げ、民泊やホテルなどの観光業界に特化したM&A仲介を提供しています。すでに営業許可を取得し、安定した収益を上げている民泊物件を買収することで、新規参入の障壁を大きく下げることが可能です。